27年半ぶりの両賞ともに受賞作なしが大きなニュースとなった、2025年7月の第173回芥川賞・直木賞。この産みの親である菊池寛の生涯を、作家・門井慶喜さんは『文豪、社長になる』で綴りました。
『真珠夫人』をはじめとするベストセラー作家であり、天才プロデューサーでもあった菊池寛の多彩な姿、菊池寛と直木三十五の関係、秋元康さんが寄せた文庫解説など、文庫化を記念して門井さんに話を聞きました。
◆◆◆
――7月16日に行われた第173回芥川賞直木賞の選考では、両賞ともに該当作なしということが話題になりました。
門井:はい、僕もニュースを見てびっくりしました。芥川賞・直木賞ともに受賞作なしは、27年半ぶりでした。
――門井さんは、この両賞の創設者である菊池寛を描いた、小説『文豪、社長になる』の文庫版を2025年7月に上梓されたところですが、その菊池寛について追う中で、賞のことは色々とお調べになったと思います。
門井:そうですね。菊池寛が芥川賞・直木賞を制定したのは戦前の昭和10年です。直接のきっかけは、その前の年に直木三十五が亡くなったことなんです。直木三十五は、今ではなかなか読者が少なくなりましたが、当時の大花形大衆作家でした。
彼は、脳の病気で入院して亡くなってしまうのですけれど、その時には、今日の直木先生の体温は何度だった、というようなことがラジオで流されるぐらいの人気だったんです。

――その日の体調までレポートされる作家さんというのは、昨今考えにくいですよね。
門井:直木は菊池寛の盟友でもありました。当時はもう、菊池寛の文藝春秋という会社は大きな雑誌社だったんですけれど、文藝春秋の発行する雑誌にも色々書いてもらっていた。その直木三十五が亡くなって、彼を顕彰する賞を作ろう、という風に思いついた。順番から言うと、それが最初だと思うんです。
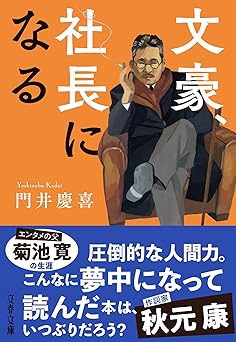
――なるほど。芥川龍之介よりも前に、まず直木さんだったわけですかね。
門井:ただ、直木三十五は大衆作家ですから、それとは別に、もっと一般文芸、今日で言うと純文学に近いニュアンスの方でもやっぱり賞を出したい、という風に思った。じゃあ誰の名前を冠しようかっていう風に考えた時に、芥川龍之介だったんだろうと。
芥川龍之介というのは、その8年ぐらい前の昭和2年に亡くなっていますので、直接のきっかけとは言えないとは思うんですけれども、その時に、じゃあ芥川と直木の名前を記念して賞を作ろう、ということで、賞が昭和10年に発足した。これが歴史的な経緯です。
芥川龍之介との親愛
――『文豪、社長になる』を読みながら、芥川龍之介と菊池寛の関係性って、こんなに深かったんだと改めて思いました。やっぱり菊池寛という人にとって特別な存在だったことは間違いないだろうなと感じました。
門井:そうですね。まず知り合ったのが一高時代ですから、芥川龍之介の方が直木三十五よりはるかに古い友達なわけですね。ただ、高校生の頃はあまり深い付き合いではなかったらしいのですが、そのあとお互いに大学に行きます。芥川は東大、菊池寛は京大に行くんですけれど。
で、それからまた菊池寛が東京に帰ってきて就職した時に、もう芥川龍之介の方は花形作家なんですね。もう菊池寛よりも一歩も二歩も先を行っちゃってるわけです。菊池寛には、それに対するジェラシーもあったろうし、焦りもあったろうと思います。
そういった時に、芥川龍之介の方が手を差し伸べてくれるんです。俺はもう文壇の伝手があるから、お前に雑誌の編集者を紹介してあげるよ、というような形だったんだと思うんですけれども、そういうのを足がかりにして菊池寛は文壇にデビューすることができたので、芥川には、本来頭が上がらない。芥川は恩人である。これがまず基本にあるんだと思うんですね。
――芥川龍之介の方もなにがしかの親愛と言いますか、友情を超えた信頼感を感じていたことが窺えるエピソードが本の中にも出てきます。
門井:そうなんです。なんと言っても芥川龍之介は、長男に「ひろし」と名前をつけてるんですね。

――菊池寛の本名「寛」から。
門井:菊池寛の本名は菊池寛(ひろし)と言うんですけれど、その名前をそっくり、漢字だけ変えて「芥川比呂志(ひろし)」と子供につけた。もう明らかに友情の印であると。
この子供が生まれる頃には、2人の経済力や知名度は逆転してるんです。菊池寛は芥川の推挙によって、文壇に色々なつながりができたんですけれど、なんといっても東京日日新聞で書いた『真珠夫人』が大ヒットをして、一躍流行作家の仲間入りをするわけですね。その時に芥川龍之介に子供ができて「ひろし」という名前をつけたということですから、この辺でちょっと2人の関係性は変わっているということですね。
――一方で、菊池寛という人にとって、文学的な意味で芥川龍之介に対する眼差しは最後まで強くあったのではないでしょうか。門井さんとしては、どんな経緯で、賞に芥川という名前を冠したと思われますか。

門井:僕の感触なんですけれど、昭和10年時点でおそらく菊池は、芥川龍之介と直木三十五を並べた時に、後世まで読まれるのは直木の方だと思ったはずなんです。
なぜかと言うと、当時は社会主義の勃興時代でして、ロシア革命が起きてすでにソ連ができている時代ですから、ゆくゆくは日本でも社会革命が起きるか、社会革命が起きないまでも大衆が天下を取る時代になるのが歴史的必然だと、菊池寛は思っていました。
そうなった時に、典型的なブルジョア小説、小金持ちの小説である芥川の小説が読まれるわけがない、大衆作家の直木だよ、という風に思ってたんだろうと。逆に言うと、直木はともかく、芥川は今ここで俺が賞の名前にでもしてあげなきゃ、もう永遠に残らないと危惧してたんだと思います。
菊池寛も予想していなかったこと
――そうなんですね。
門井:現実はその逆になりましたけどね。
――年に2回選考会があり、長年続いてきた賞が今年該当作なしということで、待ち望んでいた皆さんにとっては衝撃がありました。菊池寛はどう考えると思いますか。
門井:うーん……、昭和10年にやり始めた当初は、まだ当然、そこまで注目されている賞ではなく、ただ単に文藝春秋という一私企業がやってるお祭りに過ぎないんだ、という風に周りの人は見てたと思うんですね。
――なるほど。
門井:菊池寛も最初は、自分がこんなに一生懸命芥川賞・直木賞をやって、受賞者が出て、頭を低くしてお辞儀をして「来てください」って言っているのに新聞社も取材に来ない、と怒ってるんですよね。
――菊池寛は両賞ともに選考委員を自らかって出て、それはもうウキウキと選んでいたという逸話があります。
門井:そうですね。今は芥川賞と直木賞って綺麗に選考委員の顔ぶれは分かれてますけれど、当時は両方を兼任している人が何人かいたんです。おそらく選考会も別の日に行っていたのだと思いますが。日程を調整して選考委員の先生方に来てくれとお願いをして、そこまでやっても、取材に来てもらえなかったっていうのが出発点ですね。

――今か今かと選考結果が出るのを待つ状況は、菊池寛から見たら奇跡といいますか。
門井:そう思います。菊池寛も予想してなかったんじゃないかな。おそらく、戦後、昭和31年に石原慎太郎さんが非常に若くして芥川賞を取ったことが一つの契機になっていて、そこから今日見るようなジャーナリズムの注目を浴びるような賞になったと思います。
――両賞は毎回必ず出ていたのでしょうか。
門井:石原慎太郎以前にはわりと頻繁に「受賞作なし」がありました。両賞とも受賞作なしは少なかったかもしれませんが、片方が出ないとか、2年連続で出ないこともあったと思います。
――そんなにためらいなく、受賞作が無い年もあるだろう、というぐらいの心持ちだったんですかね。
門井:そう思います。もともと芥川賞も直木賞も、今はちょっとニュアンスが違いますけど、当時は完全な新人賞でして、本当に有望な若手を押し出してあげよう、という賞でしたから。菊池寛としては、若い君たちはお金もないだろうから、賞金と時計という形でお小遣いをあげるよ、といった感じもあったんだと思うんです。なので、受賞作がないとしても、今回はお小遣いをあげる相手がいないわ、ぐらいのことだったかもしれません。
秋元康さんの解説には嘘がない
――そんな両賞の話から、菊池寛という人が出版社を立ち上げ社長になっていくところまで、生き生きと活写していただいたのがこの小説です。書き終えてみていかがですか。
門井:菊池寛が文藝春秋で最初に作ったのは雑誌です。菊池寛が作ったというよりは、こんな薄い同人誌ですから、若者にちょっと作らせてやった、ぐらいの感じだったと思うのです。その時にはまさかこんなに、100年も続くような雑誌になるとは思っていなかったのではないでしょうか。
ところが第1号から思いのほか売れてしまい(笑)、その後、号を追うごとに順調に売上を伸ばしていくとなった時に、菊池寛の方が認識が追いついたといいますか、これはちょっとちゃんと作らなければいけないな、これは文藝春秋という会社にして、会計もちゃんとしなきゃいけないなっていう風に、売上に追いつくようにして、菊池寛も、単なる作家から企業人になっていったということかなと思います。

――文庫化にあたり、なんと秋元康さんが解説をご担当くださったのですが、お読みになって何か思ったことありますか。
門井:素朴な感想なんですけども、秋元康さんって本好きなんだなって思ったんです。それはもうとても嬉しいし、だからこそ、この人は菊池寛のことを尊敬してくれる。僕の小説というよりは、菊池寛のことを尊敬してくれているのかもしれませんけれど、それも決して嘘がないと言いますか、今までの読書経験に裏打ちされた、一クリエイターのおっしゃっていることだなという気がしています。おそらく読書ということに対して自信がおありだと思うんですね。自信がなくて、読後感を述べるという感じではない文章ですから。
――菊池寛としてはやはり大衆小説こそ書きたいものだ、世の中に必要だっていう自信を持ってやってきていて、秋元さんはその辺りにもすごくシンパシーを持ってくださってるのかなと感じました。
門井:我々凡人から見ると、秋元さんもそうですし、菊池寛もそうですけれど、やっぱり、ものすごく能力のある人が、時代を手玉に取っていると言いますか、手のひらの上で転がしてるような感じに見えてしまいますけれども、いや、そうではない。
2人ともまずこの大衆社会というものを心から尊敬していて、1mmもなめていない。その上で、自分はどうするかということを常に真剣に仕事として考えておられる人だということが、まさに菊池寛と秋元さんに共通してるんだなっていう風に、僕自身が解説で勉強しました。
――最後に一言お願いいたします。
門井:とにかく、まず菊池寛という人が面白くて、エピソード満載な人なので、エピソード集だと思って読んでいただいても結構です。そこにもっと大きなストーリーももちろんございますので、それに感銘を受けていただくとなお結構でございます。ありがとうございました。


















