〈「保守」の枠に収めてはもったいない! カトリックの通念に果敢に挑戦した教皇ベネディクト16世。その革新性とは?〉から続く
映画『教皇選挙』のヒットに続き、フランシスコ葬儀の場でのトランプとゼレンスキーの会談、ヴァンス米副大統領を批判するレオ14世のXでの発言など、国際政治とのクロスにおいてもローマ教皇の存在感が注目を集めている。
学者から転身したベネディクト16世、世界の分断に橋をかけようと奮闘したフランシスコ、そして19世紀末のレオ13世の名を引き継ぐレオ14世――『聖書』に登場するイエスの使徒ペトロ以降、2000年以上連綿とバトンが受け継がれてきたローマ教皇とはいかなる存在か。混迷をきわめる国際政治に一石は投じられるのか?
トマス・アクィナスの研究者であり神学者・哲学者の著者が、フランシスコの遺産とともに綴る現代ローマ教皇論『ローマ教皇 伝統と革新のダイナミズム』(文春新書)の執筆の経緯、読みどころなどをきいた。
◆◆◆
映画と現実が地続きになった「教皇選挙」
――映画『教皇選挙』がヒットし、いまはAmazonプライムで配信されていますね。ちょうど映画がヒットしたタイミングで教皇フランシスコが逝去し、現実にも「教皇選挙」の流れになり、新教皇レオ14世が選出された。この偶然の一致は多くの人に強い印象を残しましたが、フランシスコの逝去がきっかけとなって書かれたのが『ローマ教皇 伝統と革新のダイナミズム』です。
山本 私自身も映画が公開されたときに新聞からインタビューを受けたりして、教皇のことを意識している最中にフランシスコが亡くなられた。本当に映画と現実が地続きになった出来事で驚きました。
映画では誰も予想していなかった人物が最後に教皇に選ばれますが、現実の選挙でもメディアで取りざたされていた有力候補ではなく、思いがけずアメリカ人のレオ14世が選ばれた。時間的に近接していただけでなく、内容もまた重なったのです。
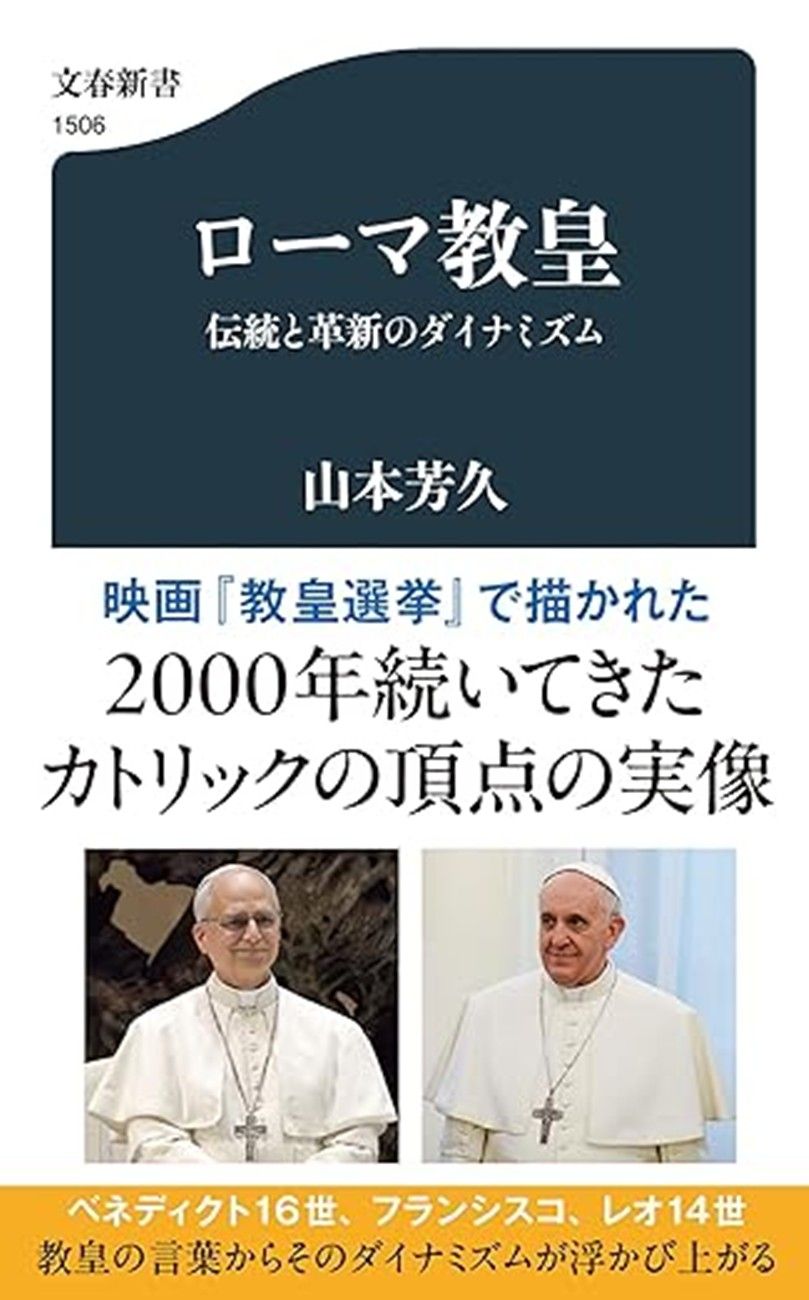
教皇は思いがけない人物が選ばれる
――教皇選挙で有力視されていた人物ではなく「予想外の人」が選ばれるのは珍しくないのですか? 「予想外」の選出が結果的には必然だった、という分析が本書でもなされていますね。
山本 「教皇としてコンクラーベに入る者は枢機卿として出てくる」という格言があります。あらかじめ有力視されている人は選ばれにくく、むしろ思いがけない人が選ばれるのは教皇選挙ではよくあることです。その意味で、映画も現実も「予想外の人が予想通り選ばれた」と言えるでしょう。
思いがけない人が選ばれて、それが全く頓珍漢な選択だったということではあまり面白くないわけですが、選ばれてみれば、今の教会や世界の課題に応える人物はこの人しかいなかった、と後から分かる。そうした必然性が見えてくるのが面白いところです。
――フランシスコが一番最後に会われた人がアメリカのヴァンス副大統領だったとか、フランシスコの葬儀の時にゼレンスキーとトランプが会談している様子が報道されたりとか、アメリカを軸に世の中が混沌としている中で、アメリカ人の教皇が選ばれるというのも実際驚きだったわけですが、それも何か現実への批評的な視座に貫かれているように感じられるところがありました。
山本 そうですね。今回、アメリカ人が教皇として選ばれたということに関して、アメリカ人だということを強調しすぎないで受け止める方が良いと思っています。様々な課題に対応しうる人物を求めたら、それが結果的にアメリカ人だったというように理解したほうがよいでしょう。と同時に、アメリカを軸とした世界政治への対応という観点からのみ選ばれたのではない人物が、結果的にはその問題にも絶妙に対応しうる人物であったということが面白いところかなと思います。
「読まないのは、もったいない」という思いが執筆の原動力に
――さて、ここからは好評発売中の山本芳久さんのご著書『ローマ教皇 伝統と革新のダイナミズム』について伺います。本書のあとがきで「こんな短期間で書き上げたのは初めて」と書かれていたのが印象的でした。
山本 私は普段、700年以上前の人物であるトマス・アクィナスなどを研究していますので、時事的な動きに合わせて書くことはほとんどありません。今回はフランシスコの死去からレオ14世が選ばれるまでの流れを毎日丹念に追ったり、またレオ14世が選ばれてから公式に発せられる演説をすべて読んだりしながら、現実の展開に合わせて執筆するという、これまでにない経験でした。非常にエキサイティングな時間だったと思います。
私が学部時代にお世話になった哲学者・坂部恵先生が、様々な本をご紹介してくださるときに、ある本について「この本を読まないのは、とてももったいないことだ」という言い方をいつもされていました。その言葉が私の心に強く残っていて、今回の執筆の一つの原動力にもなりました。いま、日本では教皇が出す文書に触れたことがある人はほとんどいないと思います。ですが実際に読んでみると、現実を深く理解する助けとなる言葉や、信仰を超えて響いてくる言葉が多く含まれています。
教皇への関心が高まるこの機会に、歴代の教皇が発してきた言葉に触れてほしい。「教皇の言葉に全く触れずに人生を終えてしまうのはもったいない」という思いを強く持ったことが、本書執筆の直接のきっかけでした。

――日本ではメディアを通じて伝わる教皇の言葉はごく一部に限られ、なかなかアクセスしづらいのが現状です。本書では、山本さんがそこに補助線を引きながら、フランシスコ、レオ14世、ベネディクト16世の3人に焦点を当て、伝統と革新が交錯するダイナミズムが描き出されていますね。
山本 教皇の言葉は、古典的な伝統と現代世界の動きが絶妙に組み合わされているのが特徴です。触れることで、現代を理解する新しい視点が得られると同時に、時空を超えて過去の古典とあらためて出会い直すことができる。非常に豊かな時間がそこにあります。
三人の教皇が織りなす伝統と革新の物語
――本書ではフランシスコ、レオ14世、そしてベネディクト16世を順に取り上げています。新しい教皇から遡っていくならば、レオ14世、フランシスコ、ベネディクト16世になりますが、そうではない。この構成にはどのような意図があるのでしょうか。
山本 まず、亡くなったばかりのフランシスコがどのような人物だったのかを語る必要がありました。彼は「橋を架ける」という言葉を軸に、人と神、人と人、人と自然の間に橋を架け続けた教皇でした。人間同士のあいだに、そして人間と自然界のあいだに大きな分断と不調和が見出される現代世界において、分断を克服し、調和を再び見出すということを訴え続けた人物でした。彼にとって「神」とは、そうした分断の克服の根源にある原動力のようなものでもあったのです。
新たに選ばれたレオ14世は最初の演説で「橋を架けましょう」と繰り返し、フランシスコの精神を引き継ぐことを明らかにしました。同時にキリスト教の根幹を形作った4~5世紀のアウグスティヌスの言葉を頻繁に引用し 、現代世界において革新的なメッセージを発していこうとする姿勢が見られます。伝統を守ることと革新をすることが相反することではなくて、むしろ伝統に依拠することによってこそ新しい言葉が紡ぎ出されていくという在り方を体現している。

そしてベネディクト16世。彼は今回のフランシスコの逝去に際しても、「保守的」というひとことで括られて語られたりしましたが、それではもったいない。20世紀を代表する神学者で、濃縮された言葉の中に2000年の伝統を凝縮して現代に響かせた人です。彼の言葉を本書で紹介できたのは大きな意義があると思っています。
「同行者」としてともに言葉を紡ぐ
――山本さんご自身は、どのようにして教皇の言葉に深く触れるようになったのですか?
山本 私も以前は、教皇の文書は「教会の公式文書の親玉」のようなものだと思い込み、あまり心に響かないだろうと考えていました。
きっかけは、作家の堀田善衞がヨハネ・パウロ2世を「現代思想家」として論じたエッセイを読んだことです(「思想家としてのローマ法王ヨハネ・パウロ二世」、『空の空なればこそ』所収、筑摩書房、1998年)。当時日本でもけっこう売れたヨハネ・パウロ2世の『希望の扉を開く』という一般向けのインタビュー形式の書籍なんかも取り上げつつ、堀田さん自身のヨーロッパ経験なども織り交ぜながら書かれていたんですね。
当時からヨハネ・パウロ2世は非常に保守的なことで知られていて敬遠する向きさえあったんですが、実際に彼の出した様々な文書を手に取ってみると、公式文書としての堅実さと教皇の個人的な熱量が両立していて、非常に面白いものでした。単に信仰者に向けられた言葉ではなく、何かを求める多くの人に開かれている――そう感じたのです。
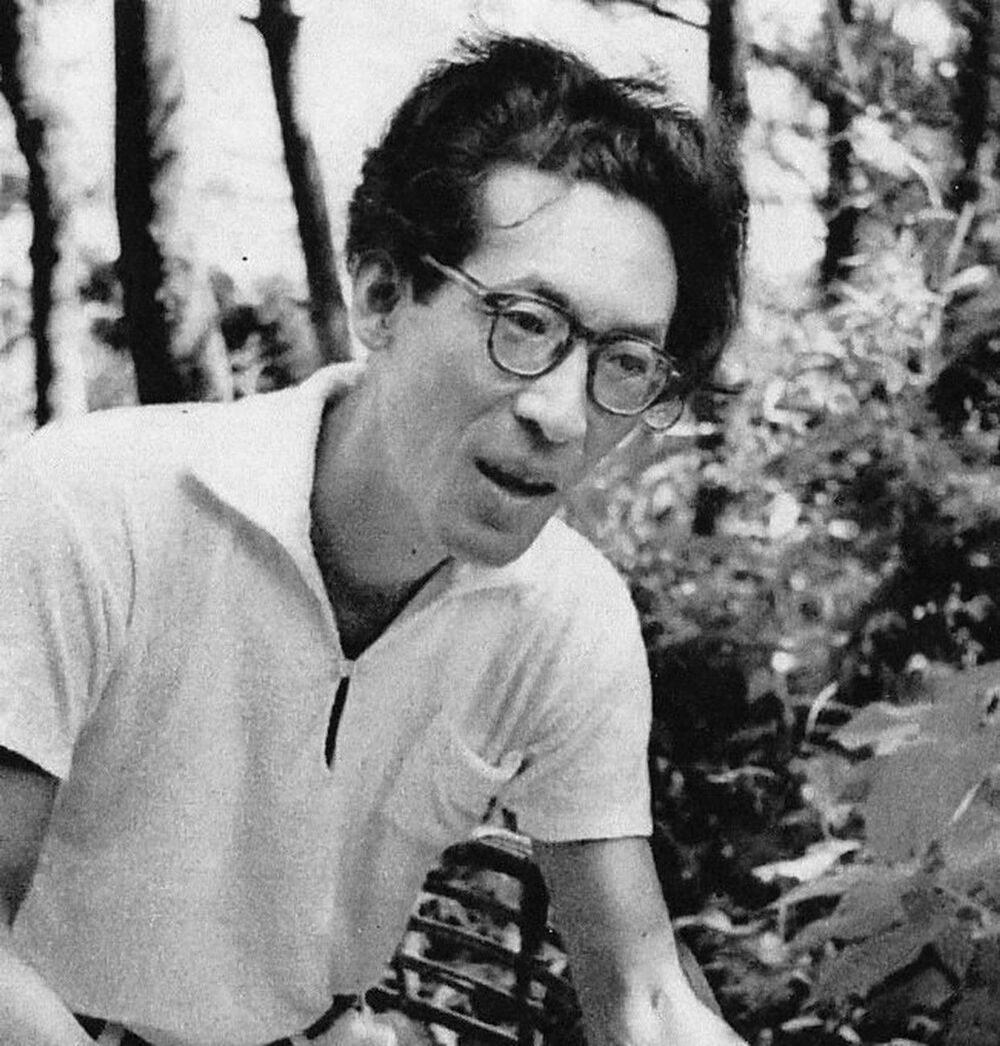
――あとがきでは、ご自身の信仰の歩みについても触れられていました。神について語ることの難しさと、教皇の言葉はどのように繋がっているのでしょうか。
山本 私は、カトリック系の中高の出身なのですが、私自身は、中学生の頃はキリスト教の信仰を持っていたわけではなかったので、信仰を持っている元々カトリックの家庭の友人などに関して、「本当に神などというものを今時信じていたりするのかな」と非常に奇妙に思っていたわけなんですね。それで、あるとき、彼に「信じているといいことがあると思っているのか」というようなことを聞いたら、「今すぐいいことがあるかどうか分からないけども、長い目で見ればいいことがあるかもしれないと思う」という答えが返って来たですね。それに非常に驚いたんです。単なる「迷信」とは異なる「信仰」というものの在り方に初めてありありと触れたという思いがしました。
その後、色々なことがあって自分自身も信仰を持つようになって30年ほど経ちますが、神について語ることの難しさは日々痛感しています。人に説明できないことは、自分自身も本当に理解していないということ。言葉を人に届けて初めて、自分も納得できるのだと思うんです。その点でベネディクト16世の姿勢には特に励まされてきました。彼は現代社会において神について語ることの難しさを熟知しながら、それでもゼロから言葉を紡いでいく。
だから私にとって現代の教皇は単なる研究対象ではなく、ともに言葉を探し続ける「同行者」なのです。
教皇の名に込められた意味とは――名は体を成す
――教皇が選ぶ名前にも深い意味がある、という点も興味深かったです。
山本 とりわけ亡くなったフランシスコは、初めて「フランシスコ」という名を選んだ型破りな人物でした。
アッシジのフランシスコは、皮膚病の人を抱きしめ、イスラムのスルタンと対話し、小鳥に説教した――分断に橋を架け、自然界との調和を大切にした人物です。これはまさに現代世界が必要としている様々なメッセージがアッシジのフランシスコという人物には埋もれていて、それを教皇名として選び取り、実践的に取り組んだ非常に型破りな教皇だったなと。フランシスコが教皇であるときには当たり前のように受け止めていたわけですが、決して当たり前ではない、非常に稀有な人物だったんだなと。教皇名というのは単なるレッテルではない、本当にその教皇の実質を体現しているものだなと思っています。
――最後に、読者の方へのメッセージをお願いします。
山本 繰り返しになりますが、信仰の有無にかかわらず教皇の言葉に一度も触れずに人生を終えるのは本当にもったいないことだと思います。
たとえばベネディクト16世の『神は愛』、フランシスコの環境についての回勅『ラウダート・シ』は、キリスト教への見方を一新させ、現代の危機に深く響いてきます。「世界」や「人生」についての捉え方に、必ずや多くのヒントを与えてくれることと思います。本書が、そうした言葉に触れるきっかけになればと願っています。




















