累計150万部突破の「三河雑兵心得」(双葉文庫)では徳川家康の天下取りを足軽の視点から、26万部突破の「北近江合戦心得」(小学館時代小説文庫)では豊臣秀吉の天下取りを浅井家の忠臣の視点から描き、時代小説界に確固たる地位を築いた井原忠政氏。待望の新シリーズ「真田武士(もののふ)心得」(文春文庫)がいよいよ刊行、「井原戦国三部作」が幕を開ける。
家康、秀吉に続き、なぜ井原氏は真田家、そして実在の無名武士・鈴木右近を主人公に選んだのか。その創作の秘密に迫る。
◆◆◆
――今回はこれまでの2シリーズと異なり、初めて主人公に実在の人物・鈴木右近を据えられました。彼は無名と言っていい存在だと思いますが、この発想はどこから生まれたのでしょうか。

井原 実は「三河雑兵心得」シリーズの第11巻『百人組頭仁義』を書いている時から、構想はあったんです。作中に名胡桃城の落城場面(名胡桃城事件:北条氏側の猪俣邦憲が偽の文書を使って真田氏の城代・鈴木主水〈もんど〉を城外に誘い出し、その隙に名胡桃城を占領させた謀略事件。秀吉の小田原征伐のきっかけとなった)が出てきて、悲劇的な運命を辿る鈴木小太郎という主水の嫡男が登場します。それが後の鈴木右近なのですが、その時から「ああ、こんな悲惨な境遇にあった子供がいたんだ」と強烈に印象に残っていて。「この子の人生は、一つの独立した物語になる」という確信がありました。
――『百人組頭仁義』の執筆時点では、まだ鈴木右近という人物の全体像はご存知なかったのですか?
井原 ええ、最初は「かわいそうな少年」というだけだったんです。でも、調べていくうちに、その子が大人になり、やがて非常に珍しく印象的な最期を遂げる、という事実を知りました。その両極端な事実に触れた時、「この人生は書かなきゃだめだ!」と強く思いました。物語がそこで生まれたんです。

――実在の人物を主人公にする上で、ご苦労や、逆に描きやすい部分はありましたか?
井原 私の執筆スタイルは2つありまして、歴史に明確に記されている事実には逆らいません。主人公が史実でやっていないことを書くことはできない。これは絶対です。
でも一方で、戦国時代は記録に残っていない空白の部分が非常に多い。そこは、もう私の想像力で、勝手にやらせてもらっています(笑)。右近の場合、最初と最後の記録はあれど、その間の人生はほとんどが空白です。だからこそ、彼の人間性を深く掘り下げ、物語として構築する自由がありました。
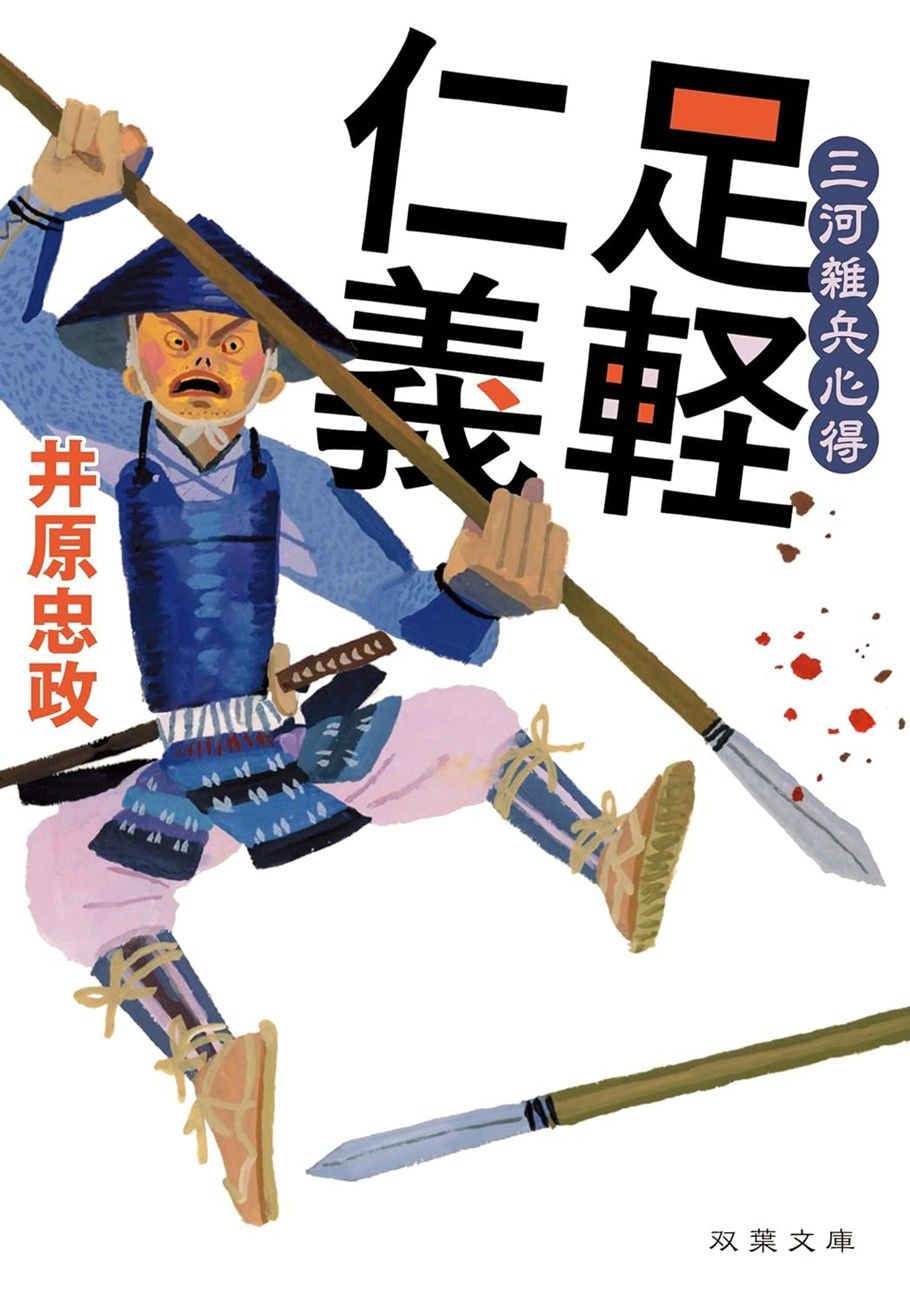
――これまでのシリーズでは、架空の雑兵・植田茂兵衛の目を通して徳川家康を、同じく架空の武将・大石与一郎の目を通して豊臣秀吉を描いてこられました。今回の「真田武士心得」も、その構想の延長線上にあるのでしょうか。
井原 その通りです。家康、秀吉と天下統一の「主役」を描いてきましたが、今回は天下に翻弄される側の代表として真田家を描こうと考えました。天下統一という大きなドラマの中で、自ら歴史を動かした人たちもいれば、その流れに飲み込まれ、必死にもがきながら生き抜いた人たちもいるわけです。その象徴として、真田家はまさにうってつけでした。
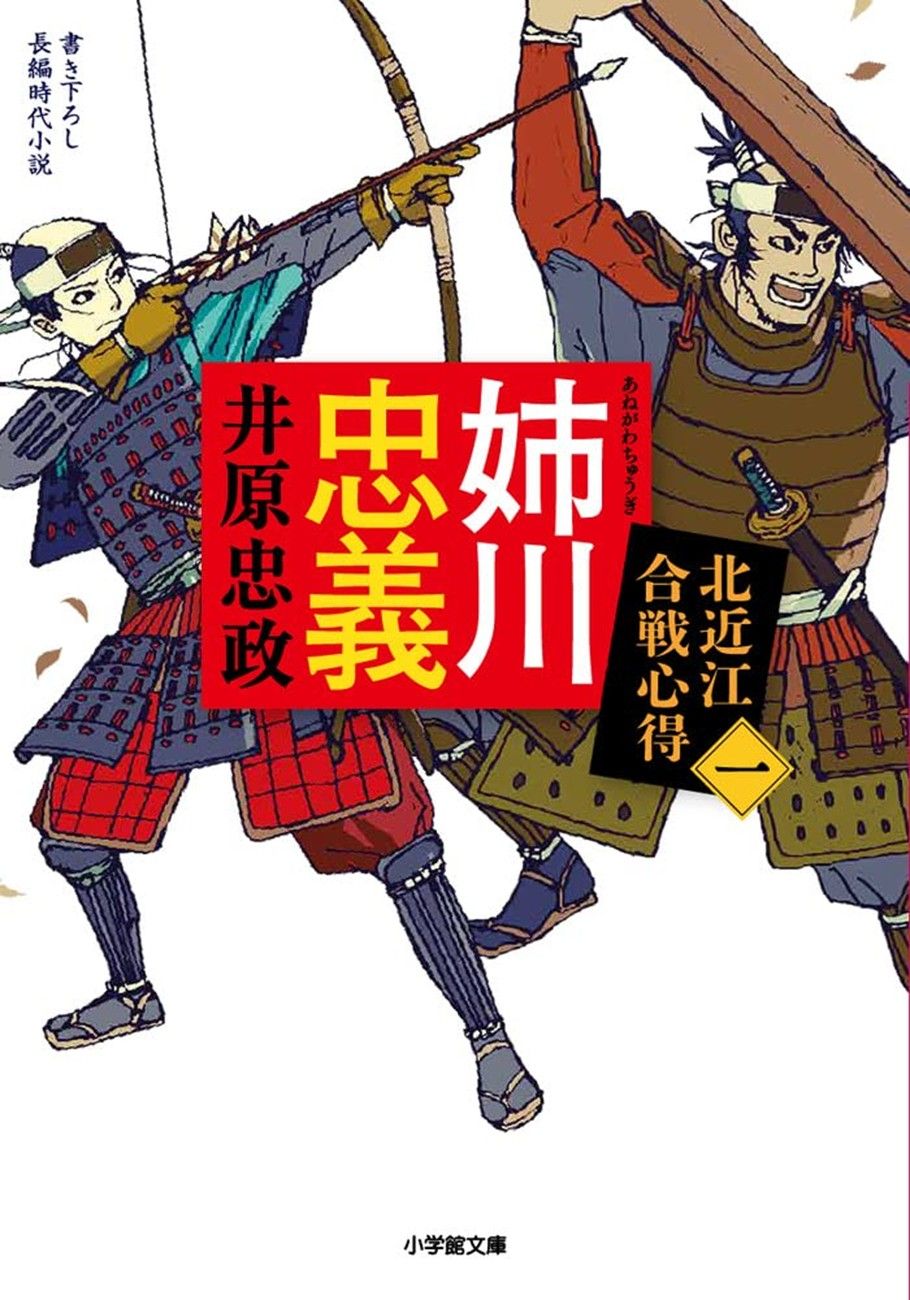
家康にも秀吉にも深く関わり、徳川2代将軍、3代将軍に睨まれながらも、幕末まで家名を残した。その真田家という存在を通して、天下を「取られた」側の人々の生き様を描きたかったんです。そして、その視点となるのが、鈴木右近というわけです。(第2回へつづく)
井原忠政(いはら・ただまさ)
2000年、「連弾・デュオ」で第25回城戸賞に入選し、経塚丸雄名義で脚本家デビュー。主な作品に『鴨川ホルモー』『THE LAST -NARUTO THE MOVIE-』などがある。16年、『旗本金融道(一) 銭が情けの新次郎』(経塚丸雄名義)で時代小説家デビューし、翌年に同作で第6回歴史時代作家クラブ賞新人賞受賞。20年、井原忠政名義で「三河雑兵心得」シリーズを刊行開始。同シリーズで『この時代小説がすごい! 2022年版』文庫書き下ろし編第1位獲得、日本ど真ん中書店大賞2023を受賞。22年、「北近江合戦心得」シリーズを刊行開始。25年、原作とシナリオを担当した『羆撃ちのサムライ』(作画・本庄敬)が第54回日本漫画家協会賞のまんが王国・土佐賞を受賞。他の著書に「うつけ屋敷の旗本大家」シリーズ、「人撃ち稼業」シリーズがある。


















