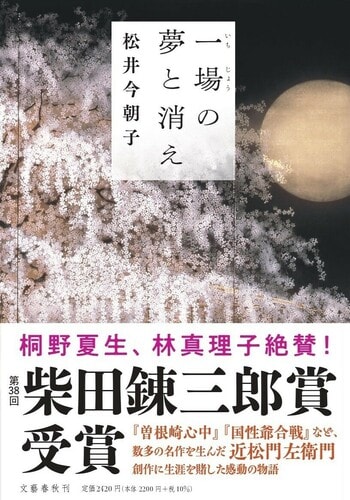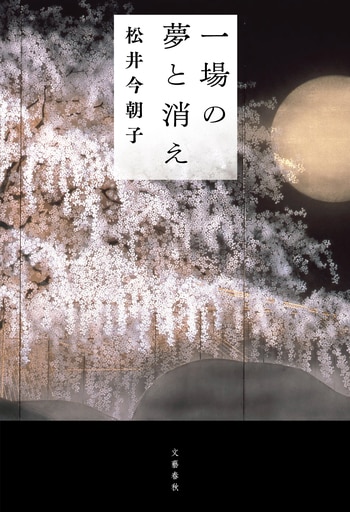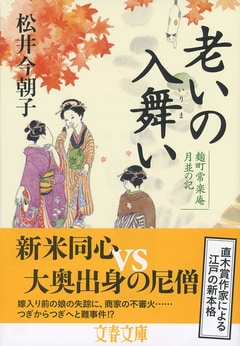第38回柴田錬三郎賞を受賞した、松井今朝子さんの『一場の夢と消え』は、「日本のシェイクスピア」とも称される大劇作家、近松門左衛門の生涯を描いた芸道小説。越前の武家に生まれた杉森信盛が、京で役者や女たちと出会い劇作者の道へ。やがて近松門左衛門として、『曾根崎心中』や『国性爺合戦』などの名作を数多く生み出し、その生涯を創作に賭した感動の物語だ。
同賞の選考委員は、熱気あふれる筆致、歌舞伎を知り尽くした著者ならではの風格、躍動する会話などを高く評価。2025年11月21日に行われた授賞式で祝辞を述べた桐野夏生さんは、「近松の偉大さを、周辺の人間模様や作品だけで説明するのではなく、今日的な『眼』を持つ天才として描いたのは、ご自身も歌舞伎の脚本を執筆する松井さんならではの力量であろう」と賛辞を寄せ、松井さんは受賞の喜びを次のように語ってくれた。
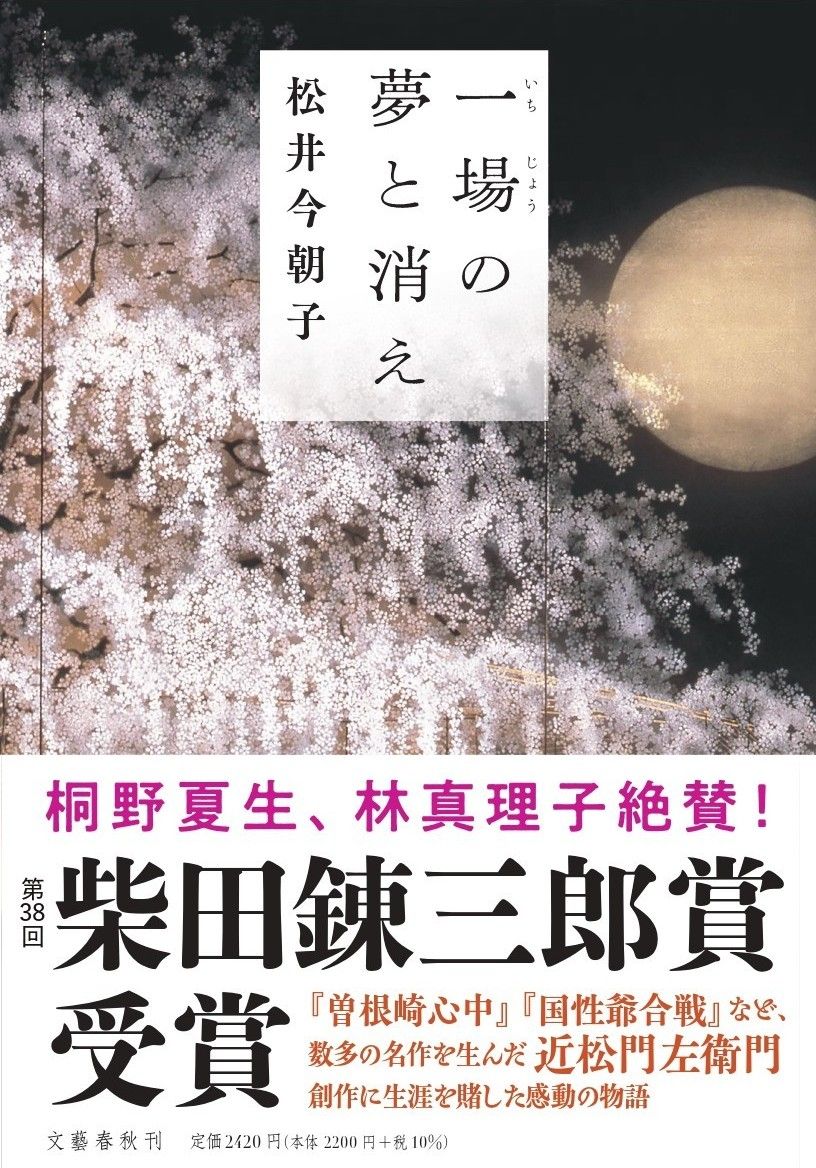
◆◆◆
私は小説というものを書こうと考えたこともなかった30代の頃、「近松座」という歌舞伎の一座で座付作者のような仕事をしていた経験があります。歌舞伎の台本というのは、ずっと昔からあるものをそのまま使っているのではなく、上演条件に応じて、その都度、新たに書き換えるわけですけれども、その際にいちばん守らなければならないもの――いろんな制約があるんですが、どうしても守らなければならないのは、時間のことなんですね。
3時間の公演で三杯道具、休憩を2回とって、芸中2時間半でまとめてくださいというような注文を受けます。要するに3場を2時間半でまとめるという、その制約だけはどうしても守らなければならないというのが鉄則でした。プロデューサーは何回か替わって、私が5、6年そういう仕事をしていた時に、新しく担当になったプロデューサーの方から、その台本を見て「松井さん、これだめよ。とにかくこれじゃあ、時間内に収まんないわよ」と言われたことがありました。
私としては、役者のセリフの緩急から下座というBGMの入れ方、道具転換の時間とかまで全部計算して、頭の中でシミュレーションを何度もした上で書いているので、絶対に収まるはずだと思っていましたが、「どうしてもこれだと収まんないわよ」って言われてしまう。割とそんなふうに人に絡むのが好きなプロデューサーだったんですけど、散々無理だと言われるうちに、だんだん私も頭に来て「いや、絶対に収まります。これで収めてみせます」と啖呵を切って、上演する前の総ざらえという稽古の時に、1分と違わずピタッと収まった瞬間、「やった!」と思ったと同時に、「ああ、私はこれでこの世界のプロになれた」と思いました。

小説家といわれるのは何となく後ろめたいような
それから20年ほど経ってから、ひょんなきっかけで小説というものを書きはじめて、もともと小説というものに対して、あまり覚悟もできていないまま書きはじめたせいか、それを20年以上なんとなくだらだら続けていても、自分で「あっ、プロになった」っていうふうに、自分で自分にGOを出すことが全然できずにいます。
最近は「作家」という肩書で容赦してくれなくて、「小説家」っていうような肩書をつけられる時があると、何か詐称しているような、何となく後ろめたいような気持ちを、私は特に感じるんですけれど……。先輩作家の方々は、自分にどうやって「自分はプロの作家なんだ」というふうにGOを出すんだろうって、ずっと考えに考え続けて、そもそもこんなことを考えるような人間は、作家というか小説家にはなっちゃいけないんじゃないか? 小説家というのは、きっと自分の書いたものが、すべて小説だと思えるぐらいの確信が持てないと、書いてはいけないんじゃないか、と悩むようなこともすごくあります。
そういうわけで何の自信もないまま、自分にGOを出せないまま、ずっとものを書き続けているんですけれども、こういう賞をいただくと、つまり自分ではGOを出せないから、いろんな先生方からGOを出してもらえると、本当にほっとして嬉しく、ありがたく思います。本当にありがとうございました。
(第38回柴田錬三郎賞授賞式スピーチより)
***
書くことの愉悦と苦悩、芸能の栄枯盛衰、そして自らの老いと死。芸に生きる者たちの境地を克明に描き切った、近松小説の決定版にして芸道小説の最高峰『一場の夢と消え』。松井今朝子さん自身が小説家として改めて向き合ったこの物語を、ぜひ多くの方に手に取ってほしい。