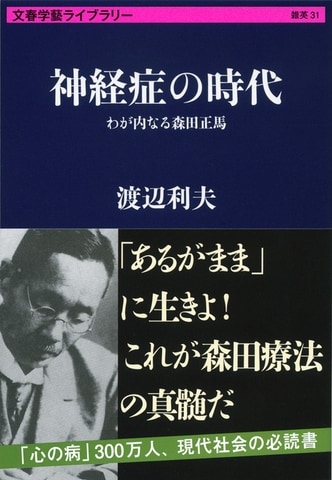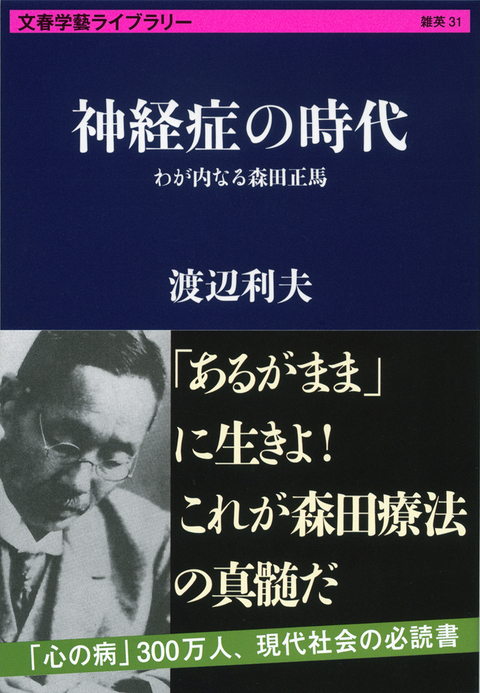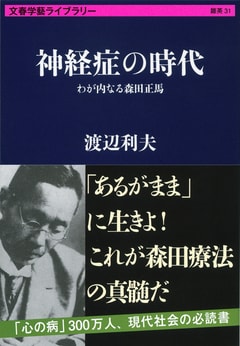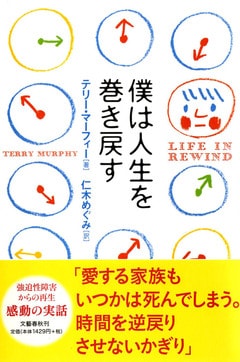日本ではこの種の実験はなされていない。日本の医学・医療界、それに抗癌剤などの製薬業界に強い既得権益があり、これが隠然たる圧力となっての不作為なのであろう。現在の日本は医学・医療思想においてはまぎれもない後進国なのである。今年七十七歳になる私が、六十歳の時にそれまで定期的につづけてきた肺癌のCTスキャン検査をきっぱりとやめたのは、メイーヨークリニック実験の論文を読んで、その高い実証性に得心させられたからであった。
説明責任も情報公開もままならぬ怪しげな根拠で癌検診を強いる権限を、誰が役所や医師に与えたというのだろうか。老化現象を生活習慣病と称して検診を強要し、人々も諾々とこれに応じているようである。ばかばかしいことに、アンチエイジングなどという医療分野がある。日本抗加齢医学会なる団体があって、そのウェブサイトを開いてみると、「受診者の検査結果に基づき、抗加齢専門医が食事やサプリメント摂取、運動方法などを指導し生活習慣の改善を図り、加齢による疾病や老化を予防し、健康長寿を図ります」とある。実は、この方針を厚生労働省が医療保健機関に義務づけ、「相談型指導」から「介入型治療」への転換だと自負しているらしい。
人間が生老病死というライフサイクルの中で人生を送らざるをえない以上、健康や長命は、これを追求すればするほど、健康と長命という観念に呪縛されて「死の観念」が人間を強く捉えてしまう。死の観念はこれを希釈化しようとはからえば、はからうほど、逆にこの観念を鮮やかなものとして人々に浮かび上がらせてしまうのである。人生の「背理」である。
医療人類学という分野で活躍するある女性研究者のエッセイを読み、次のような指摘に出会って改めて人間というものの存在の不可思議なありようを思い知らされたことがある。彼女のフィールドの一つが、雪が降れば外界との交流が完全に遮断されてしまう豪雪の山村である。この村では雪の季節の前にやってくる富山の薬売りの商人からいろんな種類の薬を購入して病に備える。しかし、薬などでは治すことのできない致命率の高い病に冒された場合には、村人はこれはもう運命だと瞑目して死を待つより他ない。
ところが、ある時、公立総合病院をもつ町とこの村とを結ぶ立派な道路が開かれ、雪の季節でも車で病人を総合病院にまで運ぶことができるようになったのだが、何とそれと同時に村の病人数が一挙に増加してしまった、というのである。ここにいたって、病は堪え忍ぶべき運命ではなく、積極的に治療を施すべきものとして新たに村人に認識されるようになったからだという。病とは病理的現実であるより前に認知的現実だということを、この研究はわれわれに説得的に諭(さと)してくれる。