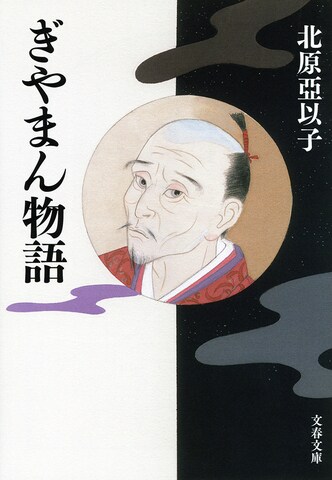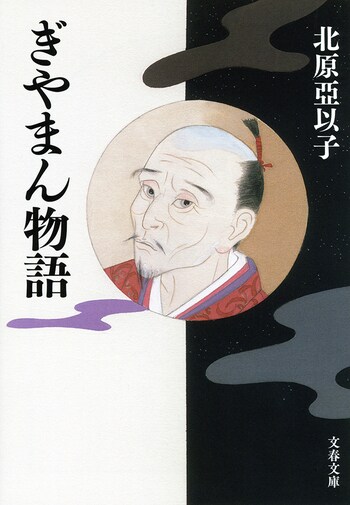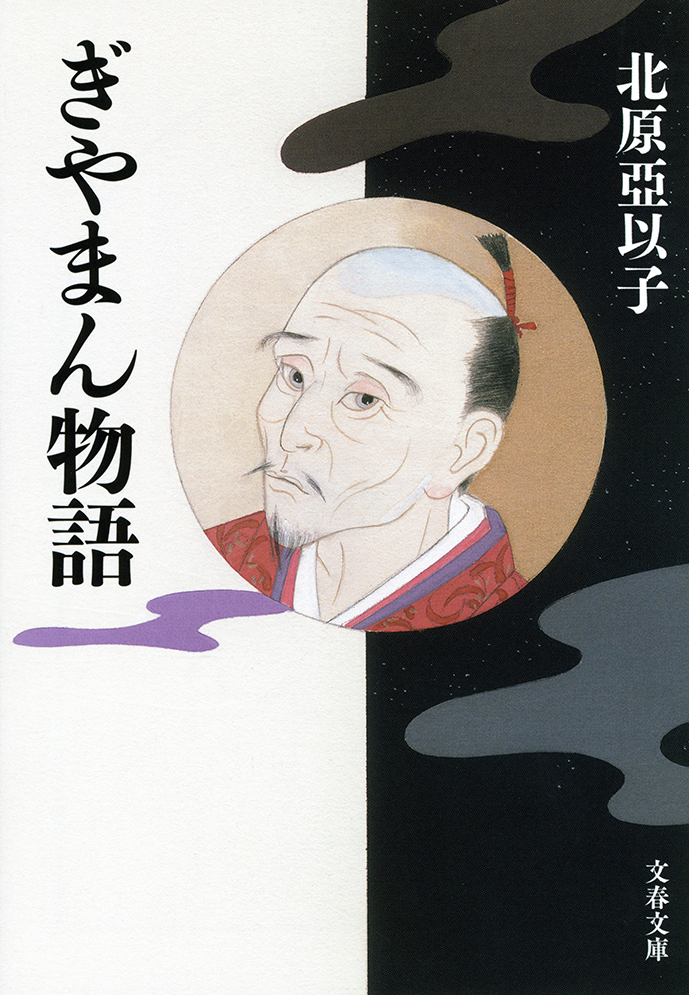
本書『ぎやまん物語』は、南蛮渡来のぎやまんの手鏡という一つの“モノ”を物語の円心部に置くことで、それを手にした者たちの人生模様と移り行く壮大な時の流れを描き出した連作長編で、北原作品の中では大変に異色な作品である。
一つの“モノ”が人から人へ、時代を越えて受け継がれていくさまを描き出すことで、時代状況のありようを浮かび上がらせる手法は、時代小説にも結構数多く存在する。一振りの刀剣をめぐる争奪戦などがその典型なのだが、本書ではそれが、主として女性が手にする手鏡であり、しかも物語の語り手に設定されているところに大きな特色がある。南蛮渡来の手鏡である「私」が、自分を覗き込む者の容貌と表情だけでなく、その内面をも映し出して語り出すところが魅力となっている。
その手鏡はポルトガル人宣教師から時の関白・羽柴秀吉(はしばひでよし)に献上されたもので、秀吉の正室・於祢(おね)や愛妾・お茶々を経てさまざまな者たちの手に渡っていくこととなる。物語の語り手である擬人化された手鏡を通して、秀吉の時代から江戸・幕末期までの歴史の流れを展望していく面白さがある。時代潮流の切り取り方と解釈は、作者の歴史観に基づくものであることはいうまでもない。
この連作長編は、平成二十五年(二〇一三年)三月十二日に七十五歳で急逝した作者が、「オール讀物」に平成十一年十二月号から二十一年五月号まで足かけ十一年間も書き継いだ作品である。平成二十六年二月に文藝春秋から刊行された初版には十三編の物語に加えて、「まえがきに代えて〜『ぎやまんの鏡』との出会い」(平成十二年十二月号)と「あとがきに代えて~ぎやまん身の上物語」(平成二十五年十二月号)が並録されていた。
今回の文庫化では、四編の単行本未収録作品を加えたことで『ぎやまん物語』『続・ぎやまん物語』と二分冊の構成、収録作品は計十七編となった。初版にあった「まえがき」と「あとがき」の章は外された。「まえがきに代えて」に記されていた作者の意図を探る前に、作者のプロフィールを紹介しておこう。
没後二年、本文庫の刊行からも分かるように、今もなお、根強い人気を示している北原亞以子は、昭和十三年(一九三八年)一月二十日に東京・新橋の芝神明宮の近くで生まれた。芝・柴井町の大名屋敷跡の家具屋横丁にあった実家は、祖父の代からの椅子専門の洋家具職人であった。幼少時の柴井町は“横丁に一つずつある芝の海”と川柳にうたわれたとおりの町で、当時はまだ江戸の風情が残っていたという。名人気質の祖父や歌舞伎好きの祖母を通して、江戸の町や戦前の東京の下町のことを知るとともに、職人の世界になじんで育った。
それだけに戦後の急速な発展の中で失われていく江戸情緒や戦前の下町の風情を惜しむ気持にはひとしおのものがあり、自分のふるさとが失われていくことへの思いがあった。自らのアイデンティティを求める心が、時代小説を書くエネルギーともなっていた。
高校時代にはシュールレアリスムの詩が好きになり、詩を通して小説を書きたいと思うようになったという。広告代理店にコピーライターとして勤める傍ら、大阪の文学同人誌「文学地帯」の同人となり、初めての時代小説を書き、同人誌「作家」にも加わった。
昭和四十四年(一九六九年)に「ママは知らなかったのよ」で第一回新潮新人賞を受賞し、時代短編「粉雪舞う」で小説現代新人賞の佳作にも入選したが、現代小説と時代小説とを書き分けているという意識はなかったそうだ。両賞が縁で直木賞作家・有馬頼義が主宰する「石の会」に入り、小説の研鑽を積んでいった。
平成元年(一九八九年)に『深川澪通り木戸番小屋』で泉鏡花賞を受賞した。江戸下町の木戸番小屋を主要舞台に、木戸番夫婦のもとに出入りする人々の哀歓模様を連作形式で綴り出した市井物で、このジャンルの有望な書き手として注目されるようになった。平成五年には江戸の町で自ら生計を立てて生きている女たちの哀歓を描いた連作短編集『恋忘れ草』で直木賞を受賞した。以来、市井物を中心とした庶民感覚で歴史の断面を抉り取ってみせることのできる作家として活躍した。
さて、「まえがきに代えて~『ぎやまんの鏡』との出会い」に戻ろう。ガラスの鏡がいつ頃に日本へ渡ってきたのか、その時期を推定した書き出しに続いて、手鏡を語り手に選んだ狙いを次のように記している。
「時代も場所も立場も違う人間たちを繋いで長い物語にしようとすると、その繋ぎ役はモノ、それも大事にされるモノでないといけない。それで南蛮渡来の鏡を思いついたんです」
「鏡は人の顔だけでなく、様々なものを映します。鏡がそれを持っている人のどういう様子を映すかで、その人の内面まで描くことができたらと思っています」
ぎやまんの手鏡を擬人化し、その語りで物語を紡ぎ出していった作者の意図が、この一文で明確に分かっていただけることだろう。
「妬心」では、「私」と表記されるぎやまんの手鏡が、まず関白・羽柴秀吉の顔を映し出す光景から始まる。小牧・長久手の戦いの翌年、天正十三年(一五八五年)のことで、秀吉はすでに唐国(からくに)遠征を考えていた、という設定になっている。秀吉が手鏡に向かって「唐国平定、唐国平定」と二度唱える場面で、当時、秀吉が置かれていた状況に触れている。
その手鏡は、秀吉の正室である北政所(きたのまんどころ)・於祢に手渡される。手鏡に己の顔を映す於祢の様子から秀吉の愛妾・お茶々への妬心の深さを、「私」は感じ取る。於祢は「私」を見つめて、「唐国平定」「お茶々不首尾」と呟く。この二つの言葉を閉じ込めさせた「私」を、於祢はお茶々に渡すのだった。
「因果」は、慶長二十年(元和元年・一六一五年)の四月、大坂夏の陣で大坂城に大筒が撃ち込まれ、鉄砲の弾が飛んでくるところから始まる。お茶々に「私」が渡って以降、秀吉の死や関ケ原の合戦など、世の中は大きく動いていた。そうした時代状況とともに、一人の愚かな女として死んでいくことを選んだお茶々の心情を、「私」が映し取っていく。
「制覇」では、「私」は落城の大坂城から江戸城のお江(ごう)のもとへと送られる。お茶々の末の妹・お江は二度の婚姻を経て秀忠の正室におさまっていたのだが、秀忠に側室を置くことを決して認めなかった。なぜなのか、と「私」はお江の胸の内を推測していく。
「葛藤」は、寛永三年(一六二六年)九月のお江の死の記述から始まる。お江が嫡男・竹千代(家光)を遠ざけて次男・国千代(忠長)を偏愛したのは、竹千代の乳母・お福(春日局)を心底から嫌っていたからと、お江とお福の違いが「私」の視点から語られていく。
「かりがね」では、忠長の自刃後、忠長夫人のもとにあった「私」が、五代将軍・綱吉の側用人・牧野備後守成貞から京の商人・越後屋へと送られる。延宝九年(一六八一年)の越後屋の繁盛ぶりに触れて、武家の経済的な内情を「私」が解き明かしていく。
さらに「私」は、鷹峰の雁金屋の次男・市之丞に手渡される。後の尾形光琳(おがたこうりん)で、実弟・権平は後の乾山(けんざん)である。ここでは「私」をくるむ繻子(しゅす)に文様を手描きで描く市之丞の華麗な絵の才能が語られていく。
「赤穂義士」は、江戸の越後屋に返還された「私」が、元禄十五年(一七〇二年)十二月十五日、つまり赤穂の浪士たちの討ち入りの翌日に、旧赤穂藩士・毛利小平太(もうりこへいた)に拾われた経緯から始まる。そして、討ち入りから七年、五代将軍・綱吉の死去で六代将軍・家宣が生類憐みの令を廃止した宝永六年(一七〇九年)の十月、小平太と旧赤穂藩士・小山田庄左衛門、討ち入りから脱落した二人の話を「私」が聞くという形で、刃傷の原因や討ち入りの理由が探り出されていく。
「奥女中の甥」は、「私」が日本へ来て百年余りの月日が過ぎた頃のことである。毛利小平太のもとにあった「私」は、その後、道具屋の藤丸屋(ふじまるや)・伊藤平五郎の手に渡り、家宣の小姓組から小普請組の身となった白井主計(かずえ)に差し出された。主計の叔母で大奥の奥女中・浦尾が大奥へ持ち帰り、「私」はまた江戸城の女たちを映すこととなった。浦尾のお部屋様は、家宣の子・鍋松を生んだ側室・お喜世、左京局である。この後、主計が改易処分となる経緯が語られていく。
「醜聞」は、「江戸城大奥の人々を映しているうちに、私は、跡目相続という言葉を知った」という語りから始まる。六代将軍・家宣が亡くなった翌年の正徳三年(一七一三年)、「私」は家宣の正室だった熙子(ひろこ)、天英院の手許に置かれていた。今、時めいているのは、落飾して月光院と号しているかつての左京局、七代将軍・家継の生母である。「私」は浦尾から月光院、天英院へと渡ったが、月光院付きの年寄・絵島(えじま)に下げ渡された。
その絵島が正徳四年正月十四日、家宣の命日に代参で芝・増上寺の御霊屋(みたまや)へ「私」を持って出かけた。ここから有名な「絵島生島(いくしま)事件」の顛末を「私」が見ていくこととなる。法会の後の芝居見物と派手な茶屋遊び、役者・生島新五郎との密会など、絵島の行状が暴かれ、多くの者たちが処罰されたことが、「私」には解せなかった。「絵島の処分が誰の勢力を殺ぐことになるか」という「私」の語りで、冒頭部の「跡目相続」という言葉の持つ意味が分かる仕掛けになっている。
「御改革」は、享保八年(一七二三年)に起こった出羽国・長瀞村(ながとろむら)の百姓一揆に材を得ている。紀州藩主から八代将軍の座に就いた吉宗が発した質地条目が原因で起こった騒動で、「私」は山瀬右近の懐の中で揺られて、三月に長瀞村に入り、騒動のなりゆきを見聞する。質地条目はその年の八月に廃止された。「いったい、何のための法令だったのか」という「私」の独白で、物語は閉じられている。
この後の『続・ぎやまん物語』の第一編では、時代と舞台が享保二十年九月の尾張名古屋城下へと飛ぶ。その地で「私」がどんなことを見聞し、何を感じ取るのか。「私」の語りを楽しみにしていただきたい。
ところで、初版の巻末に付されていた「あとがきに代えて〜ぎやまん身の上物語」のことについても触れておこう。
イエズス会のポルトガル人宣教師が来日する前の事情から書き起こされ、ぎやまんの手鏡は於祢からお茶々へではなく聚楽第(じゅらくだい)に住むお江のもとへ、というところで終わっている。
単行本に掲載された時、「本稿は逝去の一週間ほど前に書かれたもので、すでに小説誌での連載を終えていた本作の序章であり、大幅な改稿を予感させるものでした」という編集部の注が付されていた。文字通りの“絶筆”であったことが分かる。その初出から数えると足かけ十五年、構想を練り直していた作者の急逝が改めて惜しまれる。