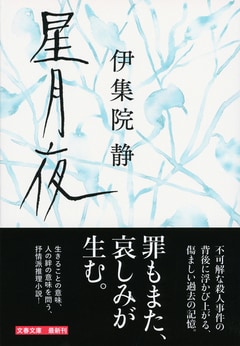一般的にミステリの面白さとして、事件がきれいに解かれるところをあげる人が多いが、きれいな謎解きは事件そのものを単純化してしまう。なめらかに解かれずに、停滞したほうが謎が輝くときがある。停滞するがゆえに謎に対する期待が大きく膨らみ、探偵は苦悩を深めていき、世界の不透明さをます。その不透明さがしばしば事件の触媒としての役割を強め、関係者のみならず主人公自身の人生にも跳ね返り、何らかの人生の意味合いをシンボライズする。本書に即していうなら、事件調査がそのまま千晶の出自へとつながり、父親が決して教えてくれなかった母親の正体と行方の解明へとむかう。絵画盗難事件の謎を解くことがそのまま父親の実像に迫り、父と母の隠されたドラマを知ることになるのである。
といっても、盗難事件、父親の実像、母親探しの三つが複雑にからまり、一筋縄ではいかない。ひとつずつ解きほぐしていくプロセスに停滞があるがゆえに、逆にそれぞれの襞の陰りを深くし、味わいを濃くしている。純文学作家でも、群像ミステリの傑作『シンセミア』の阿部和重や、ノワールの秀作『去年の冬、きみと別れ』の中村文則のように、ミステリ作家顔負けの技法を駆使してミステリファンを唸らせる書き手もいるけれど、むしろ伝統的な枠組みを踏襲しながらも予想外のところにつれていく小説のほうが新鮮な場合もある。
たとえば、海外の作家になるが、トマス・ピンチョンが私立探偵小説の形式を踏襲した『LAヴァイス』は、あえて脱力的な語りを選択し、事件の謎そのものを無効にしてピンチョン的なパラノイアを作り上げて面白いし、あるいは辻原登が女性私立探偵小説に挑戦した『寂しい丘で狩りをする』のように、リアリスティックなハードボイルドものを追求しながら、そこに存在しない映画フィルムをめぐる人生模様を交錯させて寓話的な成果をあげる場合もある。
高樹のぶ子も、ミステリに挑戦してはいるけれど、瀬川千晶を女性の私立探偵にありがちなハードボイルド風のタフなキャラクターにも、正義感の強いジャーナリスト像にもせず、傷つきやすい柔らかな感性をもつ女性に設定して、事件の渦中に投げ込んでいる。それは苦難にみちた女性たちの肖像と、引き裂かれた愛の歴史に焦点をあてるためである。心憎いのは、髪の毛やコーヒーをめぐる小道具を効果的に使って、挿話を結びつけ、事件と謎の真相をひきたて、愛の歴史の核心に導いている点だろう。ミステリ作家なみに伏線の張り方が巧妙なのである。さらにめざましいのは、ミステリにおいてはとかく人物が役割の域を出ていない場合が多いけれど、ここでは千晶も、千晶がほれこむ画家のオリオさんも、多面的で掴みづらく、独特の存在感を示して、関係者たちの犯罪の動機や思いなどを複雑に受け止める効果を果たしている。さすがにこの辺は、純文学作家の長いキャリアを感じさせて、実に厚みがある。
ともかく、本書『マルセル』は、高樹のぶ子が自在にミステリを扱って成功した作品であり、冒頭にも書いたように『少女霊異記』ではさらに肩の力をぬいて、洗練された物語世界を作り上げている。高樹文学にミステリという色彩が加わり、いちだんと魅力をましていくことを予感させる秀作といっていいだろう。