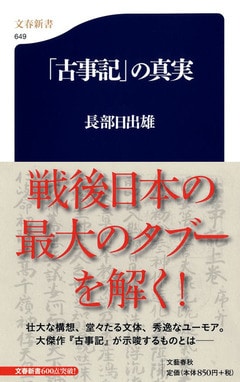還暦を迎え、『天皇はどこから来たか』(新潮文庫)から始まった長部日出雄の「歴史空想紀行」の旅は、十数年を経て、本書『「古事記」の真実』によって、着地点へとたどりついた。
歴史の息吹を伝える列島各地をわが足で踏んで確かめ、考古学の新知見と作家の想像力を駆使して幻視する古代日本の実像を提示し、そこから溢れ出ている伝統の知恵と伝統の美の再発見を確認する。それらの集約点として存在している古典『古事記』の成立を、天武天皇、稗田阿礼(ひえだのあれ)、太安万侶(おおのやすまろ)という「三者三様の群を抜いた個性と才能と努力の奇跡的な組合せ」であったことを描くことから、本書は始まっている。
「古事記」は「和歌と和語をこよなく愛する」天武天皇が、漢文で書かれる正史「日本書紀」とは別に、二十八歳の舎人(とねり)であった稗田阿礼に命じて、「自分一個の事業として」日本語の歴史を残そうとしたものである。「記紀」と並び称されてはいるが、長部によれば、「日本書紀」は学者たちの編んだ史料集であり、「古事記」は「ただ一人の作家の、脳裡の構想にしたがって書かれた「作品」なのである」。その「作家」が天武天皇であり、作家の「不可欠の助手」として働き、作家亡き後は、共作者に成長して新たな視点を加えたのが稗田阿礼であった。稗田阿礼の口述を、太安万侶が「愚直なまでに忠実に筆録」して、漢字を使って日本語に定着させた。古事記三人衆の役割分担を、以上のように長部は捉えている。
その「古事記」を忘却の闇から救い出したのが江戸中期の国学者・本居宣長(もとおりのりなが)であることは言うまでもない。以後、「古事記」は現在にいたるまで、幾多の大学者、碩学(せきがく)によって研究されてきた。第五章の主役となる津田左右吉(そうきち)もその一人である。津田は戦争中には皇室の尊厳を冒したとして起訴されても自説を堂々と述べ、戦後は新憲法公布の一年前から天皇は「象徴」であると主張して、皇室を擁護した学者である。津田の事蹟を描く長部の筆致には尊敬と敬愛の念がこもっている。
本書では「浅学の身も顧みず」「身の程を知らない」と断った上で、冒頭から津田左右吉の説にも本居宣長の説にも反旗を翻している。ともに稗田阿礼に関わるところでだ。宣長以来、阿礼は男性であるとされてきたが、長部は阿礼を女性であるとした。津田は阿礼を漢文に強い博覧強記の学者としたが、長部は口承の物語と歌謡を集めたフォークロアの徒であるとした。かかる主張は、長部日出雄が作家としての全存在を賭けて行われているところに、本書の面白さがある。