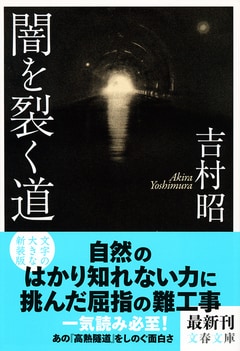一九九一年六月三日夕方、雲仙普賢岳が二百年ぶりに爆発し、火口から流れだした火砕流で地元の消防団員や報道関係者など四十三名が犠牲となった。この年の四月、フィリピンのピナツボ火山が六百年ぶりに噴火し、六月十五日には山頂部が吹き飛ぶ大噴火を起こした。噴煙の高さは成層圏の三十五キロメートル付近にまで達し、一九八二年のメキシコ、エルチチョン火山の噴火を上回る今世紀最大規模の大噴火となった。噴出物の量も、雲仙普賢岳の数百倍におよび、大量の火山灰と火砕流によって多くの家屋や田畑が被害を受け、四百人近くの尊い人命が奪われた。
このニュースを聞いたとき、私は上前氏の「複合大噴火」を思い起こしていた。二百年前に起こった浅間、ラキの噴火とあまりにも状況が似ていたからである。無論、ラキはアイスランドの火山であり、フィリピンとは緯度も経度も大きく異なっている。雲仙普賢岳とピナツボ山は、同じ環太平洋火山帯に属しているが、浅間とラキは、成因的にもまったく異質の火山である。アイスランドは、ちょうど大西洋中央海嶺が島の真ん中を通っており、北アメリカプレートとユーラシアプレートが離れていく位置にあるため、地下からマグマが出てきやすい。一方、日本列島付近では、逆に太平洋プレートがユーラシアプレートの下に沈みこんでいるため、地震や火山噴火が多い。
政治、社会状況にしても、二百年前とはまったく違っている。日本では飢饉という言葉そのものが死語と化しているし、西欧でもパンの値段が上がって暴動が起きるとは誰も考えないだろう。ピナツボ噴火による低温化のきざしも、噴火後一年たった現在、特にめだって現れてはいない。にもかかわらず、私には、いろいろな意味で、二百年前の浅間、ラキの複合噴火と今回の雲仙、ピナツボの同時噴火とがまったく無関係であるとも言い切れない気がするのである。ここでは、歴史気候学の立場から、火山噴火と気候変動がいかに関わっているかを解説してゆきたい。
津軽弘前では、飢えと寒さで餓死、病死する者があとをたたず、一七八四年夏までの死者は、領民の三分の一にあたる八万一千人を越えた。南部藩でも、餓死者四万一千、病死者二万四千、流民となって他国へ逃れた者三千で、合計六万八千におよんだ。飢えの極限に達した人々の一部には、餓死した肉親の遺体を食べるなど、想像を絶する悲惨な光景が繰り広げられた。
このように、東北地方の諸藩が軒並み大飢饉で苦しんでいる中で、松平定信が率いる白河藩だけは一人の餓死者も出さなかった。江戸でも相次ぐ災害や打ちこわしで世相は混乱し、田沼意次は老中の座を定信に明け渡さざるを得なくなる。
定信が老中に就任した翌年の一七八八年四月、フランス全土は猛烈な旱魃に襲われた上に、七月には大規模なひょう害が追い打ちをかけて、小麦は著しく減収し、主食のパン価格は異常に高騰した。翌一七八九年にかけての冬は猛烈な寒さとなり、パリのセーヌ川も凍りついた。飢えた人々はパリに流れ、至るところで暴動が発生し、ついに七月十四日のバスチーユ襲撃という結末を迎えることになる。
飢饉の原因となった異常冷夏については、浅間の噴火によるとする説があるが、噴火が起こったのは八月上旬であり、気温の異常な低下はすでに春頃から始まっていた。著者の上前氏は同じ年にアイスランドで火を噴いたラキ火山との複合噴火が、悲劇をより大きくしたのではないかと推論している。
天明三年の浅間の大噴火で忘れることができないのは、火山灰もさることながら、ふもとの鎌原村を一瞬にして襲った火砕流の悲劇であろう。秒速百メートルを越す速さで山肌を一気にかけ下った巨大な火の帯は、またたく間に数百人の命を奪ったのである。
浅間山とラキ山から噴出した膨大な量の火山灰と火山ガスは、上空を吹く偏西風にのって世界中に広がっていった。厳密に言うと、火山爆発にともなって噴き上げられた大量の亜硫酸ガスが成層圏にまで達したあと、日射(紫外線)の影響によって硫酸の微粒子(エアロゾル)に変化したのである。上空に漂う火山性のエアロゾルは、太陽からやってくる日射のエネルギーを弱め、地上の気温を下げる効果がある。
この年の六月八日朝、アイスランド南部のラキ火山が火を噴いた。一七八三年のラキ火山噴火による噴出物の量は、百億立方メートルに達したと言われ、これは同じ年に噴火した浅間山や一九八二年に噴火したメキシコのエルチチョン火山の噴出量の二十倍にも及ぶ膨大なものであった。亜硫酸ガスに富んだ噴煙は、水蒸気とともに高度十キロメートル以上の成層圏にまで達したのち、硫酸のエアロゾル(本書では「青い霧」と呼んでいる)に姿を変えて二年から三年ほど大気中にただよったために、太陽からやってくる日射のエネルギーが減少し、地上の気温を低下させたと推定される。
火山の大噴火と気候変動との関係は、実は、そう単純ではない。本書の舞台となった一七八三年の場合、浅間、ラキの複合噴火で、日本は異常冷夏をむかえたが、イギリスやフランスなど、ヨーロッパ西部の諸国では暑い夏となった。一方、インドネシア、タンボラ火山の大噴火がおこった翌年の一八一六年、北アメリカ東部やヨーロッパ西部では、異常低温を記録して「夏のない年」が出現したが、日本やインド、北アメリカ中西部などでは雨が少なく高温気味であった。一七八三年や一八一六年の例に限らず、一般的に、火山大噴火後には、気温低下に明瞭な地域差が生ずることは従来から指摘されている。
これは、次のようなプロセスを仮定すれば説明がつく。まず、火山噴火によって生成された成層圏エアロゾルが、地球上に広がってゆく過程で日射エネルギーを弱める効果に地域差を生じ、それによって熱バランスがくずれる。すると、地球をとりまく偏西風のみちすじが大きく変わるため、冷たい空気や暖かい空気の流れに異常をきたし、場所によって気温が著しく低下したり、逆に高温化したりする。本書では、複合大噴火後のこうした気温変化の地域差についても、科学的に納得のゆく説明が加えられており、単なる歴史的事実の記載に終わっていない点で、説得力がある。
再び、フィリピン、ピナツボ火山の噴火について考えてみよう。おそらく、ピナツボの場合、二百年前のラキ火山噴火に匹敵する成層圏エアロゾルが生成されたのではなかろうか。噴煙は、むしろ低緯度に位置するピナツボ火山の方が、高緯度にあるラキ火山よりも広い範囲に流されていった可能性が高い。二酸化炭素などの増加による温室効果が加わって地球規模の温暖化が進んでいる現在では、低温化の影響も二百年前ほど大きくはないだろう。しかし、噴火によって、偏西風に代表される大規模な大気の流れが変われば、世界的に異常気象が多発する可能性は十分にある。
著者の上前氏は、あとがきで、本書は歴史でもなく、気候学でもなく、ノンフィクションとも言いがたく、エッセイと思ってもらいたいと述べている。しかし、この本は単なるエッセイではない。火山噴火で大気中にひろがった噴煙で日射が弱められ、それによって生じた異常気象が洋の東西で凶作をひきおこし、飢饉による社会不安が政治体制をゆるがすという一連の図式が、最新の気候学理論と克明な史実の記載を通して見事に描かれている。気候学者は、火山噴火が気候変化をひきおこすメカニズムは追求するが、気候変化が人間社会に影響を与えて歴史を変えるといったテーマにとりくむ勇気をもたない。一方、歴史学者は、概して、気候変化を初めとする自然現象に、複雑な人間社会の歴史を変えるほどの影響力はないと考えているようだ。そうした意味で、この本は、学問のわくにとらわれずに自由な発想でものがいえる立場にある上前氏なればこそ書き上げられたのではないか。とすれば、これは、膨大な文献、資料のうらづけと緻密な分析を背景としたノンフィクションであり、日本とヨーロッパを舞台にした壮大な歴史ドラマである。
火山噴火の話にしても、科学的なメカニズムが専門的知識をもたなくとも理解できるように、図や表を使って平易に書かれている。歴史の記載も、為政者や民衆の動きを中心に、当時の社会不安がどのような過程で打ちこわしや暴動へと進展していったのかといった点に力点がおかれている。
旧ソ連、東欧の崩壊で、全面核戦争による「核の冬」の危機は去ったかに見える。一方で、石炭、石油などの化石燃料の消費がのび、熱帯地方では森林破壊によって砂漠化が進行し、大気中の炭酸ガス濃度は増え続けている。このため、人々の関心は、もっぱら温室効果による地球温暖化や、フロンガスによるオゾン層破壊に向けられる。
二百年前の浅間、ラキの複合大噴火やそれに続く天明の大飢饉の悲惨な状況などは、遠い過去のできごととして忘れ去られようとしている。そうした中で、雲仙普賢岳とピナツボ火山のあい次ぐ大噴火は、自然災害の脅威を人々に再認識させる結果となった。その意味で、本書は地球環境の過去、現在、未来に関心をいだくあらゆる階層の人々に読んでもらいたいと思う。