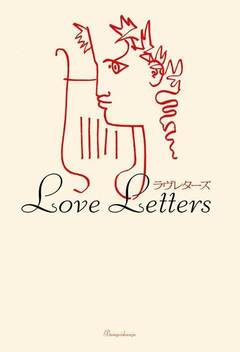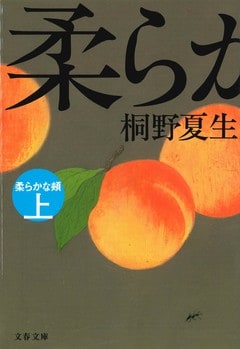実際の“トップ屋”旋風には、梶山季之、草柳大蔵、竹中労、吉原公一郎、五島勉といった名前が並んでいた。桐野は、本作に登場する遠山軍団のボス・遠山良巳のモデルは梶山季之であり、後藤伸朗のイメージは草柳大蔵だったと後に語っている(「文藝」2008年春季号)。新聞社系週刊誌に敵うはずもないと言われていた後発雑誌が見事に隆盛し、新聞社系を負かしたのは“トップ屋”の存在が大きい。そんな一つの潮流を興した彼らは、あたかも男っぽく勇ましい職業であるかのように、誤解されるようになる。
偽りの花形イメージに大いに寄与したのが、丹波哲郎が主演を務めた連続ドラマ、その名も『トップ屋』だった。このドラマを誰よりも茶化したのが“トップ屋”本人たちだった、というのが皮肉だ。梶山季之はドラマを見て、「拳銃をぶッ放したり、暴力団と殴り合うような威勢のいいトップ屋なんて、存在するはずがない」し、「脚色して、非現実的な“現代の英雄”をつくりあげたのだろうが、現実にトップ屋の仕事をしている人々にとっては、有難迷惑な話」と心底憂鬱そうだ(梶山季之『トップ屋戦士の記録』徳間文庫)。梶山のもとを訪ねてきた草柳大蔵もこのドラマを見て、同様に憤慨する。
「泣かせるねえ、全く! 四頁十五万円でトップ記事が売れたら蔵が二つ三つ建ってらァ。俺たちの地味な苦労を知らねえで……。あれじゃァスーパーマンだよ。第一、警視庁や監察医務院が、あんなにアッサリ資料をくれるかッてんだ。世間からあんな風に誤解されてるとしたら、俺はもうトップ屋を止めるよ」(同前)
トップ屋は、そんなに高尚な扱いを受けちゃいなかった。桐野が紡ぐ“トップ屋”像は勿論その辺りを誤らない。殺しを疑われた村野は、刑事からの取り調べでこのように罵られる。
「トップ屋なんて犬と同じさ。てめえの益になることしかやらねえ。うまい肉があればすぐそっちに尻尾を振るのさ」「社会の害虫だ」
“現代の英雄”であるはずがないのだ。正義のために悪を倒すのでも、より良い明日を迎えるためでもない。人様の下世話な好奇心を満たすために、地を這い、木屑を拾い集めるようにネタを探し、文字を書き、売り捌く。竹中労はルポライターという職業を語るにあたって、「モトシンカカランヌー」という沖縄の言葉を引っ張った。モトシンカカランヌーとは「資本(もとで)のいらない商売、娼婦・やくざ・泥棒のことだ。顔をしかめるむきもあるだろうが、売文という職業もその同類だと、私は思っている」(竹中労『決定版 ルポライター事始』ちくま文庫)。
経済白書に「もはや戦後ではない」というフレーズが登場した56年、「太陽の季節」で石原裕次郎が映画デビューし、上り調子の華々しい時代が本格的に幕を開ける。64年の東京五輪までは膨らみ続けるに違いないと決め込んだ人々は、その勢いを妄信する。だが、その反面、東京が抱えていたのは、激動の中で地に足を着ける難しさである。本書にはこうある。
「ものすごい速度で東京は変わっていた。道路はどこも穴だらけで、古い建物はどんどん取り壊されていく。昨日見た風景が今日はもう変わっているから、自分の記憶が違っていたのだろうかと不安になって街角で佇むことすらある」
東京五輪の前年の63年は、加速する経済成長の膿みが鋭利な事件として表出した一年でもあった。まずは本書の題材となっている草加次郎事件。62年11月、島倉千代子の後援会事務所に爆弾が届いたのを皮切りに、63年の秋まで、劇場、デパート、地下鉄などが次々と爆破される。脅迫状に残された「草加次郎」の筆跡や指紋が検出されていたにもかかわらず、事件は迷宮入りしてしまう。下町・入谷での「吉展ちゃん誘拐事件」が起きたのもこの年。出稼ぎ労働で福島から上京するも、自身が持つ障害や抜け出せない貧困に嫌気がさした小原保が起こした誘拐殺人事件だ。前例の少ない営利誘拐に警察もマスコミも翻弄されたが、そこには、東京から置いてけぼりにされる地方出身者の鬱屈があった。埼玉県狭山市では高校一年生の女性が帰宅途中に行方不明になり、身代金の要求を受ける。後に逮捕されたのが石川一雄、この事件は冤罪が疑われる事件として裁判が長期化した。