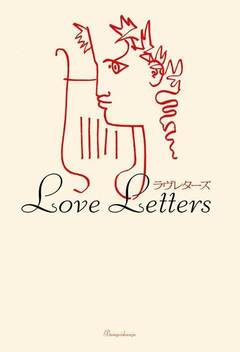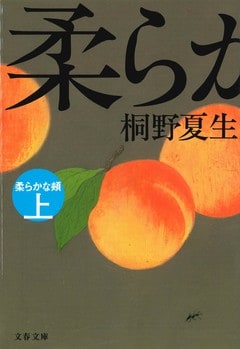大きな催事に向かうとき、そのために心をひとつにしようと大勢が試みるとき、そこからこぼれ落ちる人が出てくる。あの時代、捨てられる人々の臭いを嗅ぎ取ることは、トップ屋の仕事のひとつでもあった。村野の眼に映る東京の描写が実に生臭い。本書の単行本が刊行されたのは95年だが、桐野は本書を書くにあたり、「メンズクラブ」の編集部に出向き「街のアイビーリーガーズ」をコピーするなどして、当時の東京の風俗や風景を拾い集めたという。五輪の翌年に札幌から東京に越してきた桐野にしてみれば、五輪前夜の東京は具体像ではなくイメージの産物でしかないはず。しかし、丹念な資料探索によって紡がれた東京は、カラー映像のように鮮明である。
近年、桐野夏生は、自身の体感や記憶に基づく小説を記している。『抱く女』では、72年・吉祥寺を舞台に、学生運動に没頭する男たちの横で生きづらさを抱える女性を描いた。「夜の谷を行く」(「文藝春秋」2016年3月号で連載完結)では、連合赤軍事件に名を連ねた女性たちを今一度凝視し、指輪をはめたり、髪を梳かすなどして「女」をちらつかせた結果として、惨死を余儀なくされた若者たちの歪んだ秩序を改めて活写した。いずれも私小説ではないが、同時代を生きた事実が突き動かした小説と言えるだろう。
社会の居心地の悪さ、およびそこに潜む虚無、女という性が否応無しに感知させられる差異、桐野作品に通底するのがこれらの要素だとすれば、なぜ桐野は、95年の時点で、見知らぬ過去の男たちの群像を描けたのだろう。この生臭さはいかにして立ちこめたのだろう。
桐野は、取材をする上で「足裏の感覚や、においは忘れない」「触覚と嗅覚が一番大事」(「新潮45」2015年9月号)と語る。この感覚を前にして、今一度、竹中労の言葉が想起される。竹中は、フィクションとノンフィクションの境目を溶かすように、繰り返し「ルポルタージュは主観だ」と言っていた。
「なべて表現は作為の所産であって、“虚実の皮膜”に成立する。事実もしくは真実は、構成されるべき与件(データ)でしかありません。そもそも……、無限に連環する森羅万象を有限のフレームに切りとる営為は、すぐれて虚構でなくてはならない。活字にせよ映像にせよ、ルポルタージュとは“主観であります”。実践といいかえてもよい、ありのままなどという、没主体であってはならない」(「現代/ルポライター論」『別冊新評 ルポライターの世界』)
桐野作品は涙を盗まない。そして「ありのままなどという、没主体」を描かない。小説が「虚実の皮膜」だと認知しているからこそ、桐野はそのフレームに圧倒的なリアリティを注ぐ。フレームがグロテスクに光る。読者は時に、そのフレームを外す。あるいは、外される。
“トップ屋”の生き様を描いた桐野の筆致もまた、竹中のルポライティングがそうであったように、力強い主観だ。桐野は、あの時代の東京を生きていなかったというのに、その眼差しは、時代を貫く。2020年五輪に向かって、再び享楽的に疾走したがる中枢の姿がちらつく昨今がむず痒い。五輪前夜の臭いがキナ臭さも含めて立ちこめているこの小説は、今、改めて、いくつものメッセージを滲ませているのではないか。この鋭利な小説を、今こそ体に刺したい。