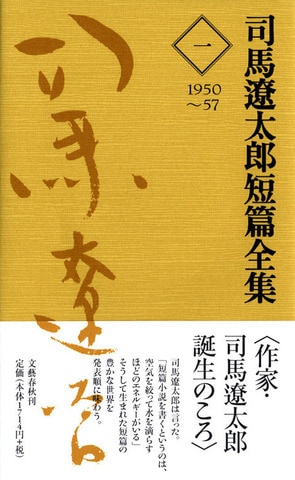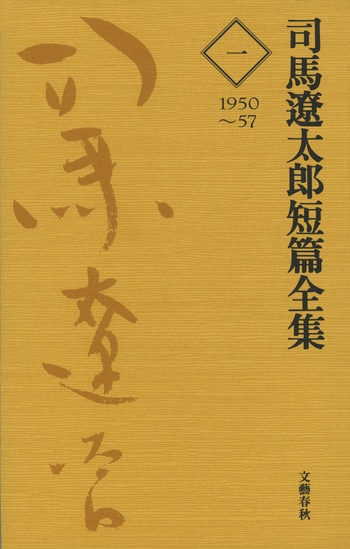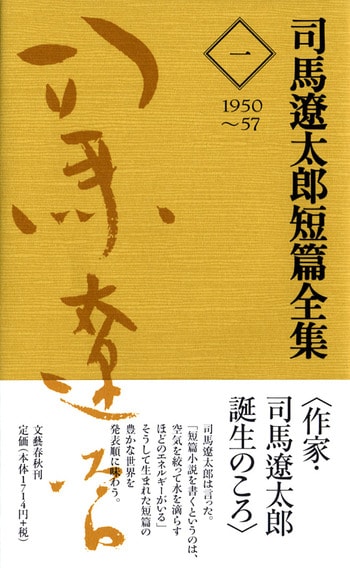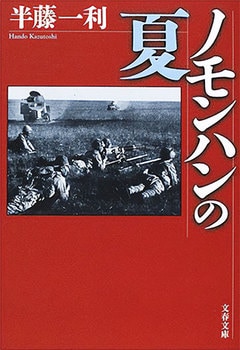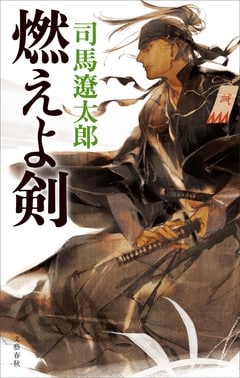海音寺潮五郎が言い当てた「野心」
東京に帰った寺内大吉は、雑誌の懸賞募集要項を切り抜いてたくさん送ってくれた。むろん純文学雑誌のものはまじっていなかった。そのうちから「講談倶楽部」を選び、「ペルシャの幻術師」という題名の七十枚ほどの小説を書きあげた。新聞記事では百行(四枚)もあれば長篇である。それに慣れていたものだから「海を泳いでいる」ような空疎な気分になった、と本人はいっている。
この小説には日本人がひとりも出てこない。そのうえ幻想的である。従来の大衆小説のイメージからははずれるかと恐れないでもなかったが、構わず応募した。
五人の選考委員のうち、源氏鶏太と山手樹一郎はまったく支持しなかった。小島政二郎と大林清は消極的支持にとどまった。ひとり海音寺潮五郎が、「大衆文学の幅をひろげる意味で、結構だと思うんです」と強く推した。パターンを踏襲しようとする癖(へき)のある通俗文学は大衆文学の名に値しないとつねづね考えていた海音寺潮五郎は、「幻想」を主題とし、かつ日本人の出てこない歴史小説をあえて書いた司馬遼太郎の果敢さに、あらたな大衆文学を、また物語のおもしろさを、あるいはいたずらに内向しつづける文学の幅をその腕力をもって押し広げ得る可能性を感じたのである。
海音寺潮五郎の言葉は司馬遼太郎の心情深くに響いた。自分の無意識の「野心」を言い当てられた気がした。司馬遼太郎は、それゆえ海音寺潮五郎を生涯徳とした。しかし彼はあらかじめ「案外当選するはずだ」というひそかな自信を抱いてもいた。
三十二歳の司馬遼太郎は、このときの「当選の辞」につぎのように書いている。
「私は、奇妙な小説の修業法をとりました。小説を書くのではなく、しゃべくりまわるのです。小説という形態を、私のおなかのなかで説話の原型にまで還元してみたかったのです。こんど、その説話の一つを珍しく文学にしてみました。ところがさる友人一読して『君の話の方が面白えや』、これは痛烈な酷評でした。となると私はまず、私の小説を、私の話にまで近づけるために、うんと努力をしなければなりません」
詩と奇蹟と科学の融けた「天国」
満州四平(しへい)の戦車学校にいた時分から、司馬遼太郎は「しゃべくりまわる」ことで有名な学徒あがりの士官候補生だった。「おもしろかったがうるさかった」というのが同期生の感想である。当選後、寺内大吉らとともに創刊した同人雑誌の「近代説話」という誌名は、その志を体現した妥当なものだったといえる。
「ペルシャの幻術師」のあと、司馬遼太郎は一年ほど小説に書き悩んだ。作品に自信はあったものの、書きつつ「自分には小説がわからない」という思いもつのったのである。自分で自分の文体がいやになることがたびたびだったのは、その生来の持味である「話体」と書き言葉の不連続を埋めきれなかったからだろう。やはり既成文学の、あるいは純文学の呪縛だったかと思われる。
「おまえ、いい作品を書こうと思っているんだろう。天下一の悪作を書けばいいんだ」という寺内大吉の示唆に何かがふっきれた。そうして書いたのが「戈壁(ゴビ)の匈奴」だった。それは、かつて隊商の交易都市として繁栄し、蒸発し去ったかのように消えた都市国家西夏(せいか)の物語である。
第一次大戦直後、広大な西疆(せいきょう)の砂の中で、ひとりの退役イギリス軍大尉にして考古学者が、大きな玻璃(はり)の壺を見つけた。鉛がふくまれているのか、打つと清涼な金属の音を発した。
砂漠で小石を拾っても、そこに死者の声が聞こえはせぬかと耳にあてる彼は、その壺を見つめるうち、「あの、考古学徒のみが享受しうる詩と奇蹟と科学の融けた『天国』が、静かに霧のように降りてくる」のを体験した。彼が「天国」の向こうに見たのは「西夏の街衢(まち)、そこを往(ゆ)き交う異風の男女」そして「暁闇(ぎょうあん)の風を衝(つ)いてゆく十万の騎馬軍団」の幻景だった。
こんな書き出しからユーラシア中央部の十三世紀の物語が展開され、司馬遼太郎の極初期代表作と目される「戈壁の匈奴」だが、この退役大尉の心境は司馬遼太郎のそれと重なる。彼もまた拾った石器に耳をあて、遠い過去の声を聞きとろうとした少年だった。