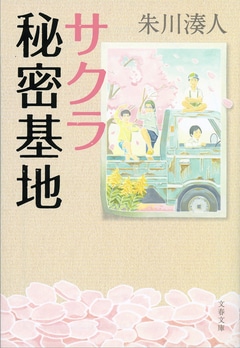現代日本文学シーンにおいて、白石一文は特別な位置にある。近年の白石の小説を特徴づけるのは、人生の真実に迫る主人公に作者自身の理念を反映させフィクションを構築していこうとする姿勢である。私は特に『この世の全部を敵に回して』(08年)以後の白石作品を、現代における全体小説、啓蒙小説、教養小説としてとらえている。白石の現在の関心は、世界を成り立たせる諸要素とその連関を、哲学や経済や宗教や科学などあらゆる学識を援用しつつ、しかしあくまで小説的な立ち位置から物語の形で情報提示することにあるように思われる。
ある状況に陥った主人公が、知識と思考と行動力を総動員して、状況を突破する。その過程で、人生と世界の神秘に心を開かれ、壮大な思弁をめぐらせていく。近年の白石作品には、そのような共通の物語構造が認められるが、一つの達成が山本周五郎賞受賞の『この胸に深々と突き刺さる矢を抜け』(09年)であり、本稿執筆時の最新作『神秘』(14年)である。両作とも、圧倒的な情報量と、とてつもない思考の渦に読者を巻きこむ。小説が小説として成り立ちうる臨界点で成立した長編小説である点で二つの作品は共通しているが、癌に罹患した出版社勤務の主人公が、直感と偶然に導かれながら、神秘体験を経て、人生の真実について深く思考をめぐらせていく設定においても共通している。
白石は同質のテーマを反復的に描き続ける。なぜ白石作品では相似的な傾向をもつ主人公が設定され、主人公として選ばれた彼・彼女は人生の目的の模索に目覚め、衒学趣味に陥りかねない豊富な引用や独特な論理展開を恐れずに、世界の成り立ちの真相を見極めようとするのか。作家論的な問題に敷延すれば、なぜ白石は同語反復的な主題にこだわり、実直なまでに描き続けるのか。白石文学は、トートロジーの罠にはまっているのではないか。そんな指摘もなされうるかもしれない。
白石一文は「小説の運動」に自覚的な作家である。ここで言う「小説の運動」とは、小説という表象行為が自律的に孕む、根源的な表現の方向性を指してのものだ。
戦後文学の継承者であり、現代日本文学において屹立した世界を提出し続ける作家に大江健三郎がいる。大江は自身の小説を、「すこしずつズレをふくみこむ繰りかえし」という言葉で説明している。大江の小説世界もまた同語反復的だ。大江は、自身に近いプロフィールをもつ男性主人公と障害をもつ子供とその家族の関係を、そして郷里の森に囲まれた谷間の村で起こる事件を、小説内部にズレをふくみこませながら繰りかえし物語化してきた。
大江と同じく、現代日本文学のフィールドにとどまらず世界文学に位置づけられる小説家である村上春樹もまた、小説におけるズレと繰りかえしの運動を意識した作家である。たとえば『1Q84』は、既存の村上作品の構成要素を圧縮・陳列したショーウィンドウ的作品であった。少女に導かれた男性主人公が現実とは位相を異にする“向こう側”の迷宮世界に招喚され、シーク&ファインドの展開に押しだされ、再び“こちら側”の世界に帰還する。春樹のメイン作品は、多かれ少なかれこのパターンを踏襲している。『幻影の星』のキーワードを使うのであれば、村上春樹の作品はまさに春樹作品の「レプリカ」として存在している。小説もまた、それ自体レプリカの産物なのだ。