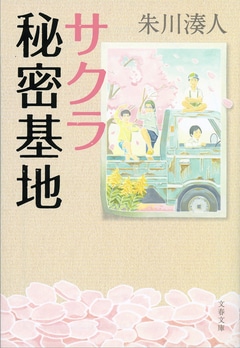小説とは、ある種のシミュレーション装置である。『幻影の星』は、シミュレーション=思考実験装置としての小説の機能がフルに活かされた作品である。本作でシミュレーションの対象となるのが「時間」である。武夫の恋人の堀江が発した「イリュージョン」という言葉がすべての契機になる。堀江は自分以外のすべての現象はイリュージョンだと言い切る。すべてはイリュージョンであるとの認識は独我論的な考えに結びつく。認識主体としての自己が常に「現在」にあり、イリュージョンとしてたちあがる周囲のすべてが「過去」の影であるとするなら、「未来」とは何なのか、という問いが武夫の中に生まれる。
もし時間という概念が人間が便宜的に生みだしたイリュージョンであることを証明できれば、人間は時間の不可逆性のジレンマから、究極的には死というオブセッションを乗り越えることができる。思考を重ねた武夫が獲得するのが、人間の寿命を超えた千年、一万年単位で物事を考える地球史的な「長尺の目」だ。生という「はかない幻影」ではなく、死という「永遠の運動」を世界観照の拠り所とすること。「唯死論」とでも命名できそうな武夫の独自の死生学(タナトロジー)は、小説的思考によって辿り着いた作者自身の境地でもある。
時間論は死生学へと結びつき、さらに東京カテドラル聖マリア教会に付設されたルルドの泉にインスパイアされたレプリカ論へと接続されることで、複写の連続性のうちに時間の概念を撥無する、そのような思考の場所へと武夫は誘われていくことになる。かくして「もとから時間の川などどこにも存在せず、過去も現在も未来も全部ここにある」という仮説が、小説的地平において証明される。
同一のコート、同一の携帯電話が、武夫とるり子にもたらされたのは、過去の記憶を現在化させるためであった。二人に記憶を喚起させようとした「主体」については、あえてここでは問わない。二人は「シュールな謎かけ」の探索の果てに、小学校時代に訪れた長崎の平和公園の手洗い場でのエピソードを思いだす。かつて発した“ある”言葉が、お互いを引き寄せる吸引力となる。
『幻影の星』は男と女の出会いの物語だ。小学校時代の武夫とるり子の間に交流はなかった。かつて手洗い場で交わしたささやかであるが大切な言葉が、二十五歳になった二人を再び結びつける。言葉は時間を超える。この世で起こったことのすべては必然である、とは白石一文の小説の根幹を流れる思想であるが、武夫とるり子もまた必然の法則によって結ばれる。武夫とるり子はコートを棄て、携帯電話を棄てる。過去の自分に再び届けるために。それは過去であって過去ではない。彼らは「始まり」と「終わり」によって統御される時間の呪縛から自由な立場にいる。
「1」からナンバリングされた章数は、「29」に到り、最終的に「0」に戻る。円環的に内側に閉じた物語構造は、時間の循環性を主張している。「無」と「永遠性」を意味する「0」という数字が刻印された最終章で描かれるのは、物語の起点であり終点である。始まりと終わりが同時存在し、イリュージョンが発現するゼロ度の場所に物語は着地する。近代的な時間意識に馴致してしまった私たちは、時間の「流れ」のイメージから自由になれない。過去と現在と未来の障壁が取り払われ、あらかじめすべてが存在する円環的で循環的な繰りかえしの運動の中に自身の想像力を解放する。直線的で計量可能な近代的な時間意識からの飛翔こそを、この作品は強く深く切実に訴えている。