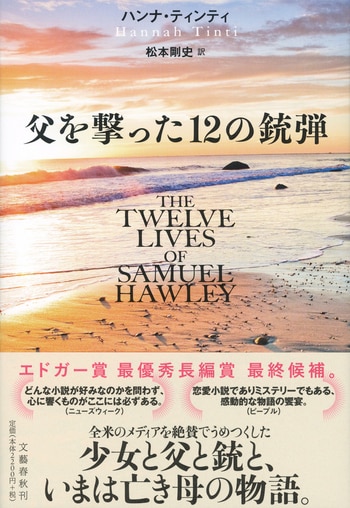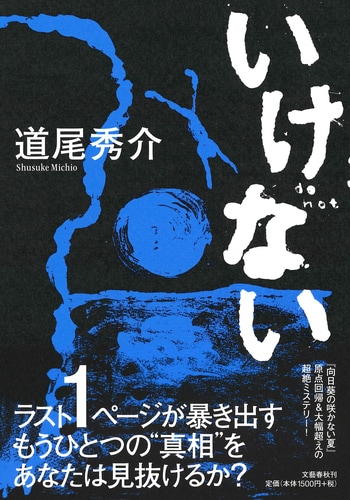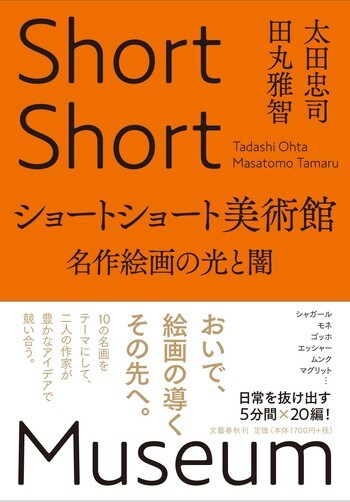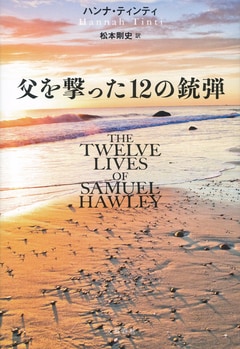司会 デルタ株を避けてリモート勤務しているうちに、気がつくと秋になっていました……! ふだんミステリーを担当している編集者が集まり、文春のイチオシ作品も織りまぜつつ、2021年上半期の必読ミステリーをふりかえる座談会。前半の[国内編]に続き、[海外編&まとめ]をお届けします。
参加者は、文庫編集部のAさん(『葉桜の季節に君を想うということ』『隻眼の少女』など担当。最愛の1作は『虚無への供物』)、翻訳ミステリー担当部長のNさん(文春初の大学ミス研出身者。海外ミステリー一筋20年。最愛の1作はJ・エルロイ『ホワイト・ジャズ』)、単行本編集部のTさん(ミステリ読みが羨ましい編集者。最愛の1作はドン・ウィンズロウ『ザ・カルテル』)、オール讀物のHさん(『いけない』など担当。最愛の1作は『シャーロック・ホームズの帰還』)、週刊文春のKさん(「ミステリーレビュー」担当。最愛の1作は『亜愛一郎の転倒』)、別冊文藝春秋のKUさん(雑食。最愛の1作は連城三紀彦『戻り川心中』)。司会はオール讀物のI(文春2人目の大学推理研出身者。最愛の1作は島田荘司『北の夕鶴2/3の殺人』)が務めます。
【まったく新しい私立探偵小説】
司会 [国内編]の最後で紹介した織守きょうやさん『花束は毒』(文藝春秋)の主人公は、いまどき珍しい職業探偵でした。台湾発の話題作、紀蔚然さんの『台北プライベートアイ』(舩山むつみ訳/文藝春秋)も職業私立探偵が活躍するハードボイルド小説ですね。担当のAさんから。


A 主人公のキャラクターがユニークで、呉誠(ウー・チェン)は元大学教授、かつ劇作家としても著名な人だったんだけど、奥さんに逃げられ、酒席でトラブルを起こして大学を辞め、演劇界とも縁を切ってしまうという設定。いわば陋巷に出て、物好きなことに探偵事務所の看板を掲げるわけですね。実はこの主人公、探偵に転身する点を除けばプロフィールが著者の紀さんとほぼ一緒。パニック障害と鬱を抱えている点も同じで、要するに、作者が主人公に自己を投影し、自分語りをしながら物語を進めていく形をとるんです。訳者あとがきに著者の言葉が紹介されていますが、「推理小説の形で日記を書いていた」そうです。
ミステリープロパーの作者でないだけに、探偵ものとしてどのくらい面白いか、翻訳を見るまで不安だったんですけれど、非常にきっちりした謎解き小説になっている点が高い評価に繋がっているのかなと思います。また、知念実希人さんの『硝子の塔の殺人』(実業之日本社)が新本格ミステリーの名作のパスティーシュになっているという話が[国内編]の座談会で出ましたが、それと同様、本書はハードボイルド小説のいろんな要素をパスティーシュとして取り込みながら物語を駆動していきます。
まず冒頭、主人公のもとに美貌の女性から夫の浮気調査の依頼がもたらされます。尾行などしてそれを解決しているうちに、今度は台北を騒がせている連続殺人事件に巻き込まれていく。シリアルキラーvs.素人探偵という図式は面白いですし、スピード感ある展開に加えて、探偵による犯人像の分析もなかなか読ませます。ネタバレになるので詳しくは言えませんが、彼がなぜその連続殺人の渦中に巻き込まれることになったのか? という謎の真相もうまく決まっていると思います。
司会 ハードボイルド小説のパスティーシュという文脈に当てはめると、本書は80年代にブームを巻き起こした“心優しき私立探偵”の流れに棹さす、いわゆるネオ・ハードボイルド路線の現代版かつ台北版と言えますね。主人公がパニック障害を抱えながら調査するところなど、ローレンス・ブロックの生んだ探偵マット・スカダーを彷彿とさせますし、依頼人の女性といきなり寝てしまうのも、ベタすぎるけれど楽しい“お約束”。主人公が次々に繰り出す親父ギャグがまた下品でひどくて(笑)、ウォーレン・マーフィーの一連のシリーズを思い出しました。
N アメリカの私立探偵小説のクリシェがふんだんに使われていて、非常に面白いんだけれども、そういう要素を詰め込めば詰め込むほど、普通なら、ハードボイルド小説って欧米的な語り口に接近していくものじゃないですか。ところがこの『台北プライベートアイ』の語り口は不思議で、どんどん欧米的なスタイルから離れていくように感じられるんです。
いま書かれている華文ミステリーの多くは、たとえば、話題の紫金陳『悪童たち』(稲村文吾訳/ハヤカワ・ミステリ文庫)に代表されるように、東野圭吾さんの影響を強く受けていますよね。それは間接的に英米のエンタメの影響を受けているとも言えるわけです。だけど『台北プライベートアイ』の紀さんはどうもそうではない。中国語圏土着の語り口が、ハードボイルドの形式を採ることによって逆説的に呼び出されてきているんじゃないかと感じられます。プロット上はしっかりとしたミステリーがあるわけだけれども、それを覆ってるナラティブがすごく変で、結果として「いままで読んだことのないもの」になりおおせている。欧米的じゃない華文ミステリーを、僕は本書で初めて読んだかもしれません。
アメリカ流の私立探偵小説って、やっぱりアメリカ的風土の上に成り立ってるものなんですよ。アメリカでは、「俺が正義だ」「公がどう言おうと俺たちの事件は俺たちで裁く」という西部劇以来の伝統的価値観が都市を舞台に展開された結果ハードボイルドが成立したわけで、ゆえにきわめてアメリカ的な物語なんですね。ひるがえって、中国語圏の精神風土ってどんなものなんだろう? 本書でも、街じゅうに監視カメラがあることが物語を推進する重要な要素になっているように、中華圏は世界最先端の監視社会、官僚社会だと言われるじゃないですか。そういう風土を背景に私立探偵小説が書かれるとき、華文オリジナルのハードボイルドが今後どんどん生まれてくるんじゃないかという興味を持ちました。
おすすめミステリー作品が盛りだくさん!
ミステリーブックガイド「文春ミステリーチャンネル」