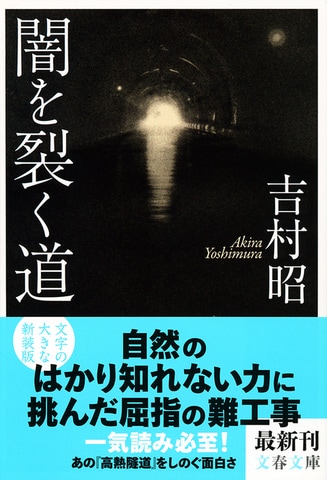坑夫として使われる者も、土地を提供する者も、自然というものをあいだに置いて見たとき、どちらも被害者のように映る。到底征服し得ぬ自然というものにたいして、いっぽうは命がけの労働を挑み、いっぽうは生活の転換と共同体の破壊を強制される。昭和九年、丹那トンネルは完成し、東京発神戸行きの列車が同トンネルを走り抜けていくシーンを吉村さんは感動的に書いているが、その七八〇四メートルの闇の底から聞こえてくる線路の軋み音には、それだけでない別の悲鳴に似た声もたくさん混じっているのではないだろうか。
第一章に登場する新聞記者のみ架空の人物で、これを小説と吉村さんが言うのは、その一点を理由としているのだろう。その他の登場人物はほとんどすべてが実名で書かれているらしく、ここに吉村さんの愛のもちかたが見えてくる。
事故死した人びとも、村の人びとも、難工事を推進した人びとも、そのひとりひとりの実名を紙に刻んで、長谷川伸いうところの「紙碑=紙の記念碑」としたかったのではないか。慰霊碑ではけっして刻み尽くせぬひとりひとりの息づかいを、こんな人たちがほんとうに実在したのだということを、紙碑として後世に伝えたかったのだ。
金子光晴のような自由人は、なんとでも言える。個人意識というものに、ほとんどの日本人が目覚めていなかった時代の話だ。金子光晴は「日本のような国では、自分たちが、ほんとうに幸せなのか、不幸せなのかがわからなくなる。だから、統治者が、日本は神国だと言えば神国ということになり(略)」「そういったことから発生する絶望や悲劇を、今日まで日本人がたくさん背負ってきたのではないか」(「絶望の風土・日本」)とも述べているが、まさしくそうした人びとのことを吉村さんは書いたのである。