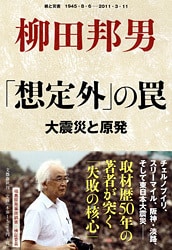――今回の作品集『爆心』には、被爆地で生きる人々の日常をテーマにした六篇が収録されています。作品を連ねていく中で、特に意識したことはありますか。
青来 デビュー作の「ジェロニモの十字架」を発表したのが、偶然ですが、被爆から五十周年に当たる年でした。今回はデビューから十年が過ぎつつあるなかで、長崎という場所の特異な歴史や風土にもう一度たちかえって書いてみようと思いました。「ジェロニモの十字架」の視線にもう一度戻ってみよう、と。当然、それは被爆から六十周年という時にほぼ重なりました。
――六篇に共通するのは、一人称のモノローグで綴られていることです。これは最初から意図していたのですか。
青来 最初の作品の「釘」では老人の内面に入っていき、次の「石」では知的障害者の一人語りで作品をつくっていくなど、いろいろな「私」や「僕」を書こうという意図は当初からありました。一人称ではありますが、オーソドックスな私小説とは全く違ったかたちで、自分ではない小説の登場人物の内面をまず創作して、そこから語るという試みは一貫して考えていましたね。
――確かに主人公の内側をありのままに表現している感じがします。各作品とも、性別も年齢もばらばらの人間を描いていますが、その難しさというのはどんな所にありましたか。

青来 むしろ楽しんでいた部分もあるような気がします。あるときは「老人」になり、またあるときは「女性」になりというように、別の「私」にどっぷりつかって書いていました。虚構の一人称による語り、虚構の私小説といえるかもしれません。別の人間になりきって、その内面を演技しながら告白してみるといった感覚でしょうか。もうひとつ、モノローグの文章の中に、さらに手紙を入れたり、主人公自身が書いている原稿の文章を入れたりと、同じ一人称の作品の中でも異なったテキストを入れて、一人称の語りに微妙なズレを出すということは意識しました。
――「釘」では、釘が一面にびっしりと打たれた密室の描写が印象的でした。この発想はどこから来たのでしょう。
青来 福祉に関係する仕事をしてきた中で、実際に見たり聞いたりした場面や話が発想のもとにはなっていますね。「釘」の中では、加害者の親という立場に寄り添って書いてみようと考えました。社会的な常識でいえば、被害者の視線で加害者が責められるというのは仕方がないことです。しかし、加害者の親や兄弟はどうなのか? 例えば、五十歳の息子が罪を犯して、八十歳の両親が責められるのは仕方がないことなのか? そのあたりになんとはなしにこだわりがあったので、あえて加害者の父親の内面から語ってみようと思ったのです。特にこの作品を書くことで社会的な強いメッセージを発したいという意図はないのですが、加害者の親の視点に寄り添うことによって、過酷でどうにもならない現実に直面している内面が浮かび上がればいいと思いました。小説を書くというのは自分と違う立場の人間を想像することからはじまると考えていますから。