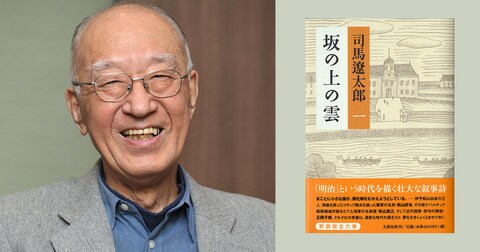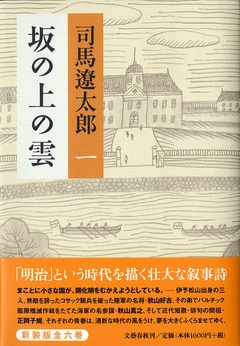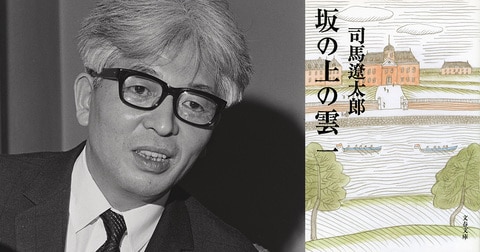〈特集〉「坂の上の雲」
・〈インタビュー〉10分でわかる日露戦争 半藤一利
・日清・日露戦争寸感 中村彰彦
・ワイパーの向こうの司馬さん 吉田直哉
中村彰彦
1949年、栃木県生まれ。東北大学文学部卒。出版社勤務を経て文筆活動に専念。94年、『二つの山河』で第111回直木賞受賞。『遊撃隊始末』『新選組全史』『海将伝』『白虎隊』『新選組紀行』など著書多数。

「降る雪や 明治は遠く なりにけり」
日露戦争勃発の三年前に生まれた中村草田男のこの秀句には、過ぎ去りし時代への郷愁が姿良く表出されている。
明治の「人と時代」を慈しんだことでは司馬遼太郎さんもおなじだが、司馬さんの場合は、その愛惜の情が軍部の暴走した次なる時代への嫌悪感につながった。この感覚は、よく知られていることだが、司馬さんに左のような疑念を抱かせた。
――日清・日露戦争のころの日本人は、健全であった。しかるにその後日本人はどこかでねじ曲がり、亡国の大戦争に突入した。どこで日本人は変わってしまったのか。
『坂の上の雲』を読んだころ、私はこのような立論の仕方になるほどと思い、自分なりにこの問題を考えてみようとしたものだった。
しかし、筆一本の暮らしに入って十三年目の今では、そのようには発想しなくなった。明治への郷愁は、つまるところ明治維新の大変革をある程度評価した時に胚胎する。私は幕末維新史を学ぶうち、維新の勝ち組の胡散(うさん)臭さが気になりはじめたので、見る目が変わってしまったのだ。
たとえば以下に列記する見解は、各種の史料によってかなり論証の可能なことどもである。
▽勝海舟が日本の海軍を育てたというのは、海舟の大ボラから生まれた話でしかない。
▽幕末の賢侯のひとりといわれる松平春嶽(福井藩主)は、尊王攘夷派に憎まれそうな役目を松平容保(かたもり、会津藩主)に押しつけてばかりいた卑怯者である。
▽坂本龍馬は梅毒を病んでいたから、もしも暗殺されていなかったら大変な姿になっていた可能性がある。
▽慶応二年(一八六六)十二月に三十六歳の若さで崩御した孝明天皇の死因は、天然痘ではなく砒素による毒殺であろう。毒を盛った黒幕は、岩倉具視。
▽同三年、幕府の遣米使節団に翻訳係として同行した福沢諭吉は、和文英訳などとても出来なかった。その上、公用金一万三千ドルを使いこんだのだから、幕府が大政奉還をおこなわなかったら厳罰に処されるのは免れないところだった。
▽薩長両藩に与えられた討幕の密勅なるものは、実は岩倉具視が玉松操に書かせた偽文書である。
▽奇兵隊は隊士たちの身分を問わない近代的軍隊だったといわれるが、その実、身分差別と給料のピンはねが日常的におこなわれる前近代的な集団であった。
以上のようなことがわかってくると、どうも明治維新を絶賛称揚する気にはなれなくなるのだ。
古武士然とした軍人たち
にもかかわらず現代人が明治という時代を懐しむ理由のひとつとして、軍人たちに古武士然とした者が少なくなかったことが挙げられるかも知れない。海軍士官第一号の元帥となった、旧薩摩藩士伊東祐亨(ゆうこう)の場合を見てみよう。
天保十四年(一八四三)生まれの祐亨の渾名(あだな)は、「桃太郎の人形」。大柄な美少年だったためだが、かれには十歳になっても一、二と指折りかぞえて五に至ると、そこで詰まってしまうというおっとりしたところがあった。六から先は折った指を立ててゆくということに、思い至らなかったのだ(小笠原長生『元帥伊東祐亨』)。
海軍軍人としての祐亨は、部下たちにやりこめられても、「わはは、またやられたわい」と破顔一笑して根に持たない器量人。艦隊戦術は「軍事の天才」島村速雄の提唱した単縦陣戦術を鷹揚に受け入れ、初代連合艦隊司令長官として日清戦争中の二大海戦(黄海海戦、威海衛<いかいえい>海戦)を勝利に導いた。
その結果、清国北洋水師の提督丁汝昌(ていじょしょう)が自殺すると、情の人でもある祐亨は、その遺体を故郷に送るために分捕った運送船一隻を独断で提供するというふところの深さも見せた。このような判断は、天皇の大権に属するものだというのに。
この行為は博文館が月三回出していた『日清戦争実記』に世紀の美談として報じられ、祐亨は当時もっとも有名な軍人となった。だが自分ひとりが英雄視されることを嫌ったかれは、一首詠(よ)んだ。
「もろともにたてし功(いさお)をおのれのみ世にうたはるる名こそつらけれ」
明治三十六年(一九〇三)十月、海軍軍令部長として海軍大臣山本権兵衛と非公式に会見し、対露開戦となれば東郷平八郎を二代目の連合艦隊司令長官に指名する、と決めておいたのも祐亨であった。その人柄に惹かれた私が、『侍たちの海 小説伊東祐亨』(読売新聞社)を上梓したのは六年前のこと。その後、御子孫たちが伊東家秘蔵の掛軸を贈って下さったため、この掛軸は私の宝物となっている。
ただし、かつては「長の陸軍、薩の海軍」ということばもあったように、海軍にあっては薩摩閥が主流であった。その点を考慮すると、祐亨の栄光の生涯はこの閥に属し、かつ武運に恵まれたため、と複眼で眺めるべきなのかも知れない。
そこで祐亨とは対極にあった人物を求めてみると、のちの陸軍大将立見尚文(たつみなおぶみ)が浮かび上がる。
佐幕派の雄藩だった旧桑名藩の出身、戊辰戦争中は雷神隊を率いて新政府軍と戦いつづけたかれのおかげで、桑名兵は佐幕派最強の部隊と高く評価された。西南戦争の最終戦、鹿児島は城山、その岩崎谷への攻撃兵を指揮して西郷隆盛を自刃に追いこんだのもかれであり、その姿は錦絵にも描かれた。
日清戦争中、つねに中央突破の強襲によって清の大軍を撃破しつづけた尚文は、「戊辰の賊徒」と呼ばれた汚名を雪(すす)ぐことをなおも願っていたのであった。米紙『ニューヨーク・ヘラルド』は、かれを「日本随一の戦術家」と呼ぶことすらためらわなかった。
この立見尚文が遺憾なく名将ぶりを発揮したのは、日露戦争における黒溝台(こっこうだい)の戦いにほかならない。
旅順を落として満州を北上しはじめた日本軍を、クロパトキン将軍率いるロシア軍は三十数万と倍以上の兵力で叩きつぶそうとした。世界最強と自他ともに認めたコサック騎兵をふくむその一部は、奉天(今の瀋陽)まで南下。結氷した渾河(こんか)を楽々わたって黒溝台という名の村を前線基地としたのだ。
大山巌をトップとする満州軍総司令部は、これをただの偵察とみなしていたのだからどうしようもない。一月二十五日、弘前第八師団すなわち立見師団に黒溝台攻撃が命じられた時、すでにこの方面のロシア軍は八個師団にふくれあがっていた。
しかも歩兵主体の日本軍に対し、ロシア軍にはコサック騎兵のほかに速射砲と機関砲が多数配備されていた。雪原が日本兵の血で赤く染まった責任は、大山総司令部のものでなければならない。
あわてた大山総司令部は、二十八日に三個師団を急派した。これによって右翼軍と左翼軍を編成することのできた立見師団は、決死隊を出して夜襲に転じた。これは敵前五百メートルまで忍び寄ってから銃剣と刀による突撃に移るという、ロシア軍には驚天動地の戦法であった。戊辰戦争の東軍中最強の桑名兵を指揮した立見尚文は、夜陰に乗じての抜刀斬りこみが敵に与える恐怖感をよく知っていたのだ。
その結果は、立見師団の死者千五百五十五に対し、ロシア軍のそれは一万以上。徴兵されて弘前第八師団に配属された東北健児たちの力戦敢闘をねぎらい、かれは狂歌を詠んだ。
「黒鳩(クロパト)が蜂(八)に刺されて逃げ去れりもはや渾河と立ち見けるかな」
ここで立見師団が壊滅していたら、大山巌とその幕僚たちは軍法会議にかけられても不思議ではなかった。
さらに三月に戦われた奉天会戦で日本が陸戦の勝利を決定づけたため、いつも話者の目はそちらへむけられがちのようだ。だが、黒溝台の勝利がなければ奉天会戦はあり得なかったのだから、日露の陸戦最大の功労者は薩摩人でも長州人でもなく、旧桑名藩出身の立見尚文と考えるべきなのだ。
欧米においてはともかく、なぜ日本では以上のような見解が定説たり得なかったのか。こんな点に注目すると、日清・日露をめぐる議論にはさらに掘り下げるべき余地がありそうに思われる。