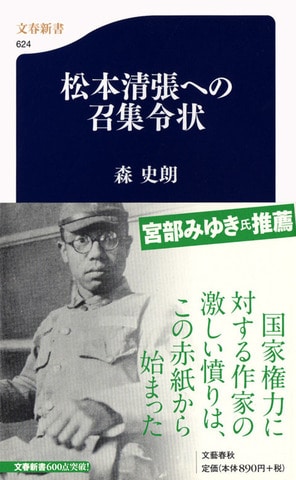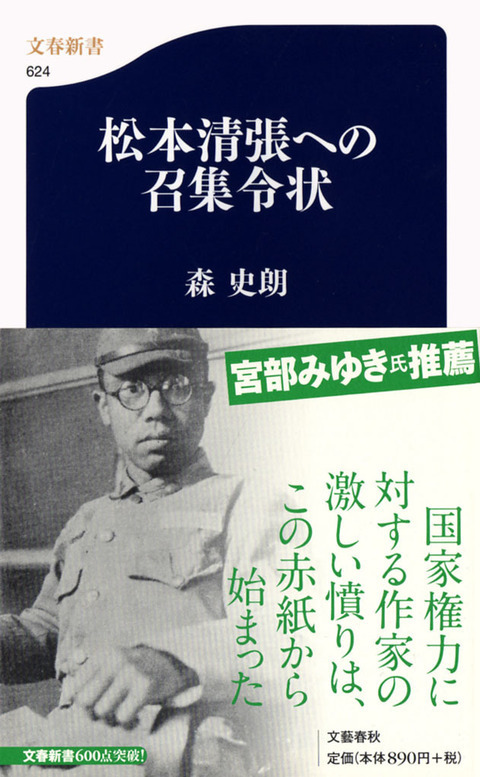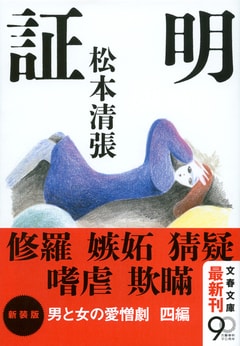清張作品にみられる権力の不正や腐敗へのはげしい憤りに共感を覚えるという氏は、その情熱の根源を探る。そして、ある仮説を立てた。
「……この作家が三十四歳のときに召集され、一家六人の家族を残して朝鮮に出征。一兵士として軍国日本の植民地統治と崩壊をつぶさに見聞きした――その巨(おお)いなる戦争体験、すなわち昭和の歴史体験が作品を生み出した根底にあるのではないか」
けだし炯眼(けいがん)であろう。これまで、そういう回路で清張作品の分析がなされた話を寡聞にして私は聞かない。
おそらく作家自身が、ベールをかぶせて戦争体験を語っているからではなかろうか。若き日の回想『半生の記』には、「新兵の平等が奇妙な生甲斐(いきがい)を私に持たせた」とあり、また植物図鑑の中の食用野草を謄写(とうしゃ)して小冊子をつくる仕事が愉(たの)しかったとも書かれている。
このくだりを読むと私など、『戦没農民兵士の手紙』(岩波新書)の、
「……軍隊も忙しい時は実に目が廻る程忙しい時もあるけれど、家の忙しさよりは遥かに楽です」
という小田島陸軍伍長の手紙を思い出す。
しかし氏は、ベールにかくされた軍隊生活の真実を看破する。十九世紀のアメリカの詩人エミリー・E・ディキンソンの言葉に、
「真実を語れ、ただし斜めに語れ」
というのがあるが、氏はまさに松本清張そのひとが斜めに語った真実を見抜いたのだ。
手がかりとなったのは、『遠い接近』である。不自然な召集令状で兵役に服した三十二歳の色版画工山尾信治が、自分の令状の発令をめぐるからくりに気づき、戦後すさまじい復讐を繰り広げるこの名作ミステリーを複眼的な視点で読み解いてみせながら、
「……語られている内容は松本清張の軍隊生活そのもの、衛生二等兵としての実体験以外の何物でもない」
という結論に導いていくのだが、一つ一つを地道に検証する手法は、それこそ極上のミステリーのようである。
とりわけ氏の父君が、町の一兵事係の計らいで召集をまぬかれたというエピソードには少なからず驚いた。そのエピソードが、『遠い接近』の生まれるきっかけの一つというのも興味を引かれる。
恣意(しい)的な動機で発令が左右されうるという召集令状の闇の部分を暴く『遠い接近』を取りあげて、松本清張を戦地へと駆り出した国家権力の実態を抉(えぐ)り出す森史朗氏の筆には、氏の敬愛する大作家と同質の憤りがあり、同質の情熱がみなぎっている。