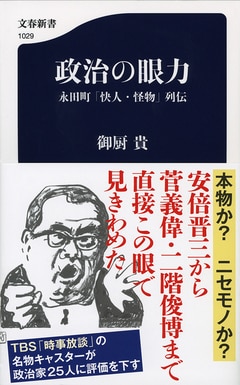角栄には独特の話術があった。聴く者はその勢いに幻惑されたが、精査すると、内容はいつも支離滅裂だった。 片言隻句だけをみてみれば、名言もあるし、何よりも強く印象に残る。 選挙民に対しては笑いを取り、ホロリとさせもする。 敵対する者に対しては、一転、その恫喝は相手を失禁させかねないほどの迫力があったという。 弊社の「文藝春秋」「週刊文春」「諸君!」が報じた言葉の中から、印象的なセリフを抜き出してみた。
人の心を掴む言葉

俺は十年後、天下を取る。お前は片棒を担げ。
一九六二年(昭和三十七年)、自民党政調会長だった角栄は、沖縄復帰について「憲法を改正して、核つき返還を考えざるをえまい」とオフレコ発言。ところが新聞記事になってしまい、国会の審議がストップする大問題に発展した。このスクープを報じたのは、「東京タイムズ」の早坂茂三記者。早坂が「自分が書いた」と名乗り出ると、角栄は、「おれが記者だったら、やはり書くよ。あれは書くべきことだ。それにしても君は優秀だな」と答えたという(「文藝春秋」1971年9月号)。
そのとき、早坂に差し出した角栄の手の握力はもの凄かったと、早坂は回想している。間もなく、角栄は上の言葉でもって早坂を自分の秘書に招いた(「週刊文春」1994年1月6日号)。
皆さん履物はわかりますか。
「文藝春秋」への読者投稿「私が見た田中角栄」の中の一編。熊本県の町会議員は、目白へ陳情に訪れた際の体験を綴った。話が終わり、帰ろうと玄関口に出ると、〈角栄がすぐ後にきて旅館の番頭よろしく声をかける。靴をはきかけてて尻を向けていた一行は、慌てて向きを変え再び深々と頭を下げる。まさか玄関口にきて挨拶しているのが角栄とは……。「やっぱ大したもんバイ」〉(「文藝春秋」1983年3月号)。
同様のことを郷里から出てきた老婆にやったとき、忙しいのに誰にでもそこまでやる必要があるのか、と聞いた早坂茂三秘書は、角栄に「阿呆っ!」と怒られたという。
「あのばあさんは田舎に帰れば、角がオラを玄関まで送って下駄を履かせてくれたと、頼まないのに言って歩くぞ。二十軒も三十軒も。俺の選挙運動になって、金は一銭もかからない。お前、何を怒ってるんだ。いいことずくめじゃないか」(「文藝春秋」1994年2月号)。
結婚式は欠席しても後でいくらでもおつきあいができるが、葬式は長いあいだお世話になった人との最後のお別れなんだ。人の道がわからなければ、ろくな政治家になれない。
新潟県議会副議長を務めた馬場潤一郎が、角栄に向かって訊ねた。「なぜ葬式ばかり行くんです。秘書に任せておけばいいじゃないですか」。すると、角栄は上のように返答した。また、「結婚式は呼ばれないと行けないが、葬式は呼ばれなくても行ける」という発言も残っている(「文藝春秋」1989年12月号)。
困ったらいつでもこいよ。
“隠れ田中派”の代議士が匿名証言する。〈カネをもらいに角さんの部屋に入る。すると角さんは、私の顔を見るなり、茶封筒や新聞紙にくるんだカネの包みを出し、“おお、よくきた、よくきた、どうだうまくいってるか”というようなことをいいながら、そのカネを渡す〉。部屋を出ようとすると、背中へこのセリフが投げかけられる。この間、金や金額に関する話はまったく出ていない。
〈いくら選挙中で非常時だとはいえ、カネをもらいにいくことは、まあ屈辱的なもんだ。それを角さんは分かっていて、そういう思いをさせないようにしてくれる。この気くばり、人間としての思いやりが、われわれを惹きつけるんです〉(「週刊文春」1983年10月20日号)。