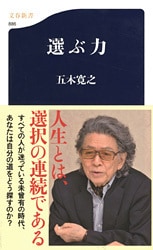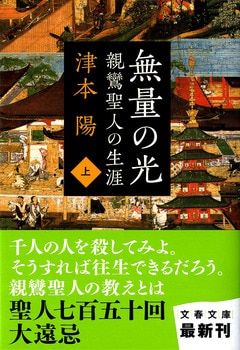この作品は四篇の中で最も早い時期に書かれただけに作品の底流には初期の五木文学に特有の音楽的リズムが響き、それが読者にある種の快感を与えているようだ。もちろん、ここには彼の初期の代表作の一つである「さらばモスクワ愚連隊」のように、ジャズの演奏が描かれるわけではない。せいぜいジャズのレコードを聴かせる店が登場する程度で、あくまでも主たる世界は人口三十万の北陸の静かな古都であるK市なのである。そして、物語はこのK市に住む三人の三十代前半の男たちによって生成されていくのだ。その中でもラジオ局に勤める魚谷と新聞社勤務の早崎はこのK市の静謐きわまりない古都のたたずまいにいらだちと反抗の思いをつのらせつつある。昭和四十三年十月二十一日(国際反戦デー)の新宿騒乱の時でさえ、この古都は美しく静まりかえっているのだ。魚谷と早崎はモダン・ジャズの珈琲店「マイルス」の店主からヒッピーの来店を知らされ、そのヒッピー達を利用してこのK市に叛乱をおこすことを企てる。それはK市の保守性を破壊すると共にニュースを地方から中央へと逆流させる破天荒な革命となるのではないか。二人は保守的な友人塩沢をもまきこんで、ラジオや週刊誌を通して、全国のヒッピーがK市に集合しつつあるというアングラ情報を流し続けていく。その結果としてK市には膨大な数のヒッピーやフーテン族が流入し、一大パニックとなるのだ。このプロセスはきわめてスリリングだが、これが恐ろしいほどのリアリティをもって現代の読者に迫ってくるのは私たちが今すさまじい情報化社会に生きているからに他ならない。作者は明らかに今日のインターネット社会を予想していたわけで、その先見性には驚かざるを得ない。それはともかくこの物語はもちろんパニックの消滅で急速に終焉となるのだが、それを読み終える読者の胸奥に「When the saints go marching in」という、サッチモことルイ・アームストロングのしゃがれ声とトランペットの音色が鳴り響くのではないか。
このように「聖者が街へやってきた」はきわめて刺激的な快作で読者を興奮させずにはおかないが、その余韻がまだただよう中、作者は実に心憎い演出をしてくれている。
一転して作者は金沢での自らの生活ぶりを私小説ふうに語ってくれるのだ。「小立野(こだつの)刑務所裏」(昭53・2『小説現代』)がそれである。他の三篇ももちろんまぎれもなく五木寛之という作家の内面から生み出された作品である。しかし、それはあくまでも小説あるいは物語というフィクションであり、事実そのものではあり得ない。その虚構性にこそ文学の面白さがあるわけで、私たちはこれまでの三作品で十二分にそれを満喫してきたはずなのだ。しかし文学の読者というものはすくいがたいほど貪欲で作家の全てを知り尽くさないではいられないのだ。だからこの『金沢あかり坂』という短篇集に収められた小説を堪能しつつも、それを生み出した金沢での作家の実生活を知りたくて仕方がないのである。この作品はそうした貪婪な読者の欲望を充分に満足させてくれる佳作と言ってよい。金沢市の小立野の刑務所裏のアパート東山荘に住む「私」(五木)は私たち読者に当時の散歩コースなどを案内しつつその土地のたたずまいなどを詳しく語ってくれる。のみならず当時の「私」の一日の小遣いが数十円であったことなどを打ち明けてくれ、私たち読者にあの時代の懐かしいほどの貧しさを喚起させてくれたりもする。しかし、この作品もまたエッセイ風の私小説として軽く味わうだけのものでは決してない。「私」は最初から最後まで金沢という都市の一筋縄では行かない怖ろしさを語ってやまないのだ。言わば「私」がこの『金沢あかり坂』を書かざるを得ないモティーフを最後に具体的に明示してくれているわけで、何とも見事な短篇集の構成となっているではないか。
それにしてもこの『金沢あかり坂』という短篇集は金沢という古都の魔的な魅力を引き出してやまない不思議な物語である。これをポケットにして、ぜひとも金沢の街をひとりあてどなく散策してみたいものである。坂の途中で凛のような女性と出会うことを夢想しつつ……。