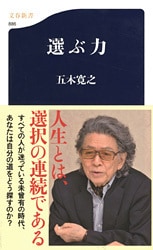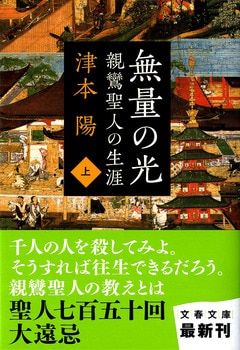五木寛之は昭和四十年から昭和四十四年までの四年間をこの金沢で暮し、その間に「蒼ざめた馬を見よ」(昭42・1『別册文藝春秋』)で第五十六回直木賞を受賞するなど華麗で鮮烈な文学的デビューをはたした。その意味では金沢という都市は彼にとって結果的に一種の文学風土と化していると言ってよいが、それら初期の作品の舞台は金沢とはほとんど無関係なのである。少なくともこの『金沢あかり坂』という一種の〈金沢ものがたり〉とでも呼ぶにふさわしい短篇集は全て金沢を離れてから生み出されているわけで、その点では曽野や古井と同じだと言ってよい。だから彼にとって金沢はしばしばエッセイで「配偶者」と呼ぶ夫人の故郷であるに過ぎず、彼自身はそこで結婚生活を始めただけの縁しかないのである。しかし、にもかかわらず五木寛之にとってこの金沢という都市は曽野や古井と同じくどうしても小説化・物語化せざるを得ない謎に満ちた不可思議な世界であったようだ。彼にとってそれはいったい何であったのか。この『金沢あかり坂』には四篇の短篇が収められているが、それらを解読しつつその謎を探ってみることにしたい。
まずはこの短篇集のタイトルとなっていて、巻頭を飾っている「金沢あかり坂」(平20・4『オール讀物』)だが、本来は最後に読んでほしい作品である。いや、もちろん、この配列に従って読んでもいいのだが、その後でぜひとも再読してもらいたい作品なのである。これはけっしてこの作品が最も新しいからと言うわけではない。五木寛之という作家の恐るべき文学的資質と力が完璧に近い形で発揮された稀有な作品だからである。
この作品の第一章で語り手は金沢という街を犀川(男川)と浅野川(女川)に代表させつつきわめて落ち着いた語り口で読者の前に紹介していく。長大な物語のオープニングにも等しい堂々たる語り口である。ただ、語り手は浅野川にかかる七つの橋をめぐる「七つ橋めぐり」という行事を紹介した後、この橋近くで「高木凛(りん)はうまれた」と唐突に語り終える。長篇の流れを急速にせき止め、一挙に短篇のリズムへ切り替えるなど実に見事な技術だと言わざるを得ない。
物語はもちろんこの高木凛という女性の人生が中心となる。彼女をめぐってかつての恋人でフリーのディレクターの黒江や金沢のテレビ局の西専務やチーフ・プロデューサーの池らがドラマを形成するが、いずれも高木凛という女性の魅力をひき立てる存在でしかない。彼女は祭り囃子の横笛の名手の娘として生まれ、その父より横笛を吹くことを叩き込まれて育ったのだ。その練習場は常に内灘海岸であった。内灘は金沢市にとって政治的傷痕が刻まれた場所であり、五木文学に特有な場に他ならない。「聖者が街へやってきた」(昭45・1『別册文藝春秋』)でもヒッピーたちがねぐらにした場として内灘の旧弾薬庫がアイロニカルに登場しているが、ここではそうした政治的な痕跡などを無化するかのように横笛の音が瀏亮(りゅうりょう)と鳴り響くのである。
現在彼女は三十一歳となり主計(かずえ)町茶屋街の芸妓“りん也”となっているが、高校卒業後のアルバイト時代はパトリス・ルコントの「髪結いの亭主」や「仕立て屋の恋」に涙するような芸術好きの少女であった。そうした時に黒江と出会い、彼の映像制作を手伝いつつ、彼との恋におちたのである。このロマンスは、「七つ橋めぐり」の伝説などを織り込みつつ「浅の川暮色」(昭53・2『小説現代』)と同じように美しく描かれていく。しかし結果的に黒江の野心と裏切りによって彼女の夢は砕け、彼女はあの懐かしい内灘海岸で笛を吹き鳴らすことで失意をなぐさめる他ないのだ。そして、その果てに彼女は西専務の勧めもあって二十三歳の時芸妓となったのである。以降、彼女は茶や踊りをはじめとして鼓、長唄、太鼓、三味線などを身につけ芸妓として一流となっていく。ただ、笛だけは父譲りの祭り囃子の強烈な音色であり、芸妓のそれではない。しかし、それ故に彼女は「両性具有のアーチスト」「笛師艶也」とテレビ番組で芸くらべをすることとなる。この浅野川ぞいの夜の河原で繰り広げられる二人の笛くらべがこの物語のクライマックスだが、こうした音楽の競い合いを言葉で描出していくことがいかに至難であることか。