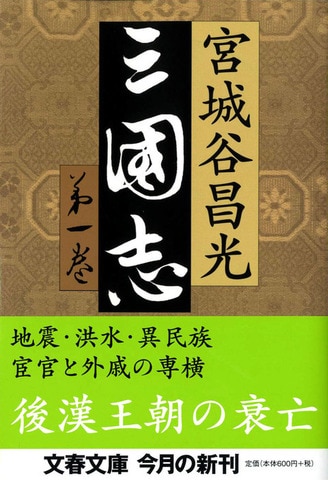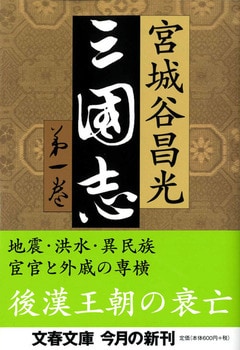〈特集〉宮城谷「三国志」
・後漢という時代 宮城谷昌光
・「三国志」の美将たち――『正史三国志』から『三国志演義』へ 井波律子
・主要登場人物
・後漢王朝皇帝全十四代在位一覧・後漢帝室系図
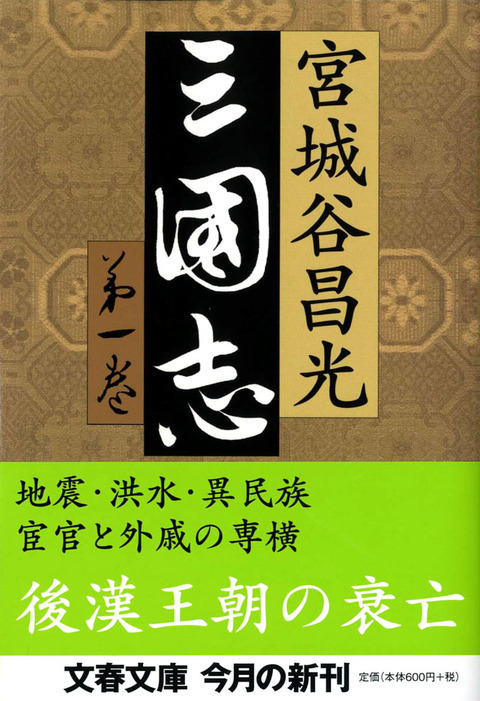
曹操(そうそう)・袁紹(えんしょう)・袁術(えんじゅつ)・孫堅(そんけん)・孫策(そんさく)・公孫【王+賛】(こうそんさん)・劉備(りゅうび)・呂布(りょふ)などが活躍するのが三国時代であると誤解している人は寡(すく)なくない、とおもわれる。
が、それら群雄のなかで三国時代まで生きていたのは、劉備ただひとりである。したがって三国時代の人を正確に書くのであれば、三国<魏(ぎ)、呉(ご)、蜀(しょく)>がのこらず皇帝を立て、年号を建てた西暦二二二年からはじめなければならない。ちなみに中国史の年表は、曹操の子の曹丕(そうひ)が帝位に即いた二二〇年を三国時代の開始とする。魏の初代皇帝は曹丕であり、蜀が劉備、呉が孫権(そんけん)であるのだが、劉備は二二三年の四月に死去してしまうので、三国時代は曹丕、劉禅(りゅうぜん)、孫権が鼎立(ていりつ)する治乱の歴史であると想うべきなのである。
しかしながら正史の『三国志』を書いた晋(しん)の陳寿(ちんじゅ)は、前漢の司馬遷が発明したといってよい紀伝体という歴史記述の手法を継承したので、時代を精密に区切らなかった。のちにその正史におびただしい注をつけて、歴史を豊潤なものとした裴松之(はいしょうし)が、「『三国志注』を上(たてまつ)る表」のなかで、

「三国の歴年は長くはありませんが、事件が漢代から晋代までつながっており、最初から最後までとりあつかうと、百載(さい=年)にわたるということになります」
と、述べているように、六十年間の三国時代が百年という延袤(えんぼう)をもつことになった。その裴松之の注のついた『三国志』を、日本でも、平安の貴族や室町の五山の儒僧たちが読んでいたにちがいないが、庶民にはそのおもしろさが知られることはなかった。読書の状況は中国でも似たようなものであったろう。
ところが明(みん)の中期に『三国志演義』が完成されると、状況は一変した。演義とは、歴史小説であると想えばよい。が、多分に講談調である。それが大衆にうけにうけて、人々は『三国志演義』を通して、時代と人を熱烈なまなざしで視るようになった。その『三国志演義』が最初に日本語に訳されて出版されたのは元禄二年であるらしい。以来、日本でも『三国志』を愛読する人がふえにふえたのだが、正確にいうと『三国志演義』ばかりを読んで、正史の『三国志』を知らない人が多い。いや、他人(ひと)を嗤(わら)うことはできない。私がそうであった。
私が読んだのは岩波文庫の『三国志』(内容は『三国志演義』)であり、それをすくなくとも八回は通読した。いまはほかにちくま文庫などでも読むことができる。ただし通読をくりかえすうちに、
――何かが隠蔽されている。
と、感じるようになり、さらに、真実の光があちこちに微かではあるがのぞいていることに気づくようになった。ああ、これは歪曲された世界なのだ、と意(おも)ったことはたしかであり、『三国志演義』への読書熱が冷(さ)めるきっかけはそこにあったといってよい。かわりに正史の『三国志』を読みたくなり、筑摩書房の翻訳が完成するまで、首を長くして待ったという憶えがある。ところがその訳本がそろったあとに、私の関心は三国時代から離れてしまい、正史『三国志』を通読することはなかった。実際、私は中国の古代にのめりこんだ。そのおもしろさは比類のないもので、中国史の深遠さに驚嘆した。その世界にとどまって小説を書きつづけているうちに、ときどき三国時代を遠望したものの、あまり魅力を感じなかった。古代のほうが人に豊かさがある。人をささえるものとその位置、いわば支点がちがうので、当然、力点と作用点がちがうということになる。古代では人をささえているものは人だけではない。そういう観点に立って三国時代をながめると、人と人の距離が短すぎて、玄妙さに欠ける。私の正直な感想はそういうものであったが、私の小説の世界が、商(しょう=殷<いん>)から周、周から秦末漢初に達したころ、三国時代を書かなければならなくなった。
――三国時代はむずかしい。
その時代の切りかたとして『三国志演義』があり、作者の趣旨も明確である。みごとな作品であるといわねばならない。が、そこには多くのものがかくされていて、時代の真実がみえにくい、と往時に感じたことを中心にすえて、歴史をじかに視るという工夫をしないかぎり、他人の小説の上にあらたな小説を載せる作業に終始するだけになってしまう。それゆえ私は『三国志演義』を忘れるということからはじめた。つぎに後漢という時代をできるかぎり正確に知ろうとした。王朝そのものが盛衰の原因である、と考え、個人の善悪の力を必要以上に擢用(てきよう)しないことをこころがけた。そういう自制のなかで、二年間ほど後漢王朝を凝視しつづけた。
曹操を知るためには、祖父の曹騰(そうとう)を知らねばならぬということであり、曹騰が宦官(かんがん)であるかぎり、宦官を識る必要があり、宦官に権力を与えた垂簾(すいれん)政治を理解しなければならない。それらの渾【肴+るまた】(こんこう)が歴史の世界なのであるが、では歴史の主体とは何であるのか。歴史の主体とは、人以外何があるというのか、といわれそうであるが、私はそのことを考えつつ、後漢の名臣である楊震(ようしん)の、四知、ということばを憶いだした。たれも知らないとおもわれることでも、天が知り、地が知り、わたしが知り、あなたが知っている。それが四知なのである。後漢の時代になっても良い伝統が失われていないことが、その短い語から感じられ、それを承(う)けて小説を書きはじめることができた。小説を書きつづけているいまも四知を忘れたことはない。
後漢の時代に紙を発明したといわれる蔡倫(さいりん)は宦官であり、章(しょう)帝の皇后の諷旨(ふうし)をうけて、宋(そう)貴人を自殺させるが、宋貴人の孫が皇帝(安<あん>帝)になったことで復讎(ふくしゅう)され、死刑に処せられそうになる。勅使を迎えた蔡倫は、薬を飲んで従容(しょうよう)と死ぬ。それは王朝の内のささいなことかもしれないが、私には興味深く感じられた。そういうひとつひとつが歴史の力点になっていることをみのがしたくない。それをつづけてゆけば、人と人とが近すぎると意った世界に、あらたな天と地が出現するであろう。