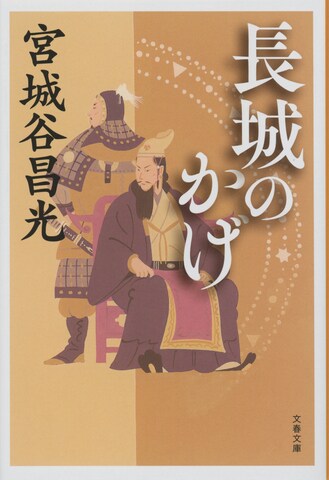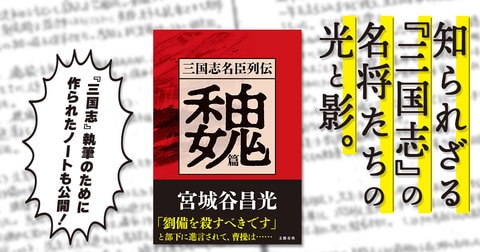1
この『長城のかげ』に収められている五篇の短篇は、いうまでもなく共通点があって、漢王朝の創始者である劉邦と何らかの関連がある人びとの物語ということである。時代でいうと、秦の始皇帝の国家統一から、劉邦の死後、呂太后の暴走的支配あたりまでである。
ただし五つの短篇に登場する劉邦は、生身の人間というより、一つの影という印象がある。影はある場合では大きく濃く、ある場合ではふつうの等身大で、しかも奇妙に薄かったりする。また影は、短篇の主人公たちからはるか遠くにいることもあれば、近くに寄ってきて主人公たちに取り憑くほどになったりもする。劉邦という影こそが、五つの短篇を読み解く秘密であるかのようだ。
この劉邦の影という話をもう少し明確に語るために、宮城谷昌光氏が書いた別の長篇小説『劉邦』について触れなければならない。
まず、短篇集『長城のかげ』と長篇『劉邦』の書かれた時期を知っておこう。
『長城のかげ』の最初の短篇「逃げる」は、一九九三年の夏の「別册文藝春秋」に掲載され、最後の「満天の星」は、一九九六年春の同誌に掲載された。一冊の単行本になったのは同じ九六年の五月である。
いっぽう長篇小説『劉邦』は、二〇一三年七月から二〇一五年二月まで、毎日新聞に連載され、二〇一五年五月から三巻本として刊行されたのである。
すなわち、『長城のかげ』が刊行されてからほぼ十九年後に、劉邦を主人公にした長篇が刊行されたのである。ずいぶん長い時間をかけて、影は生身の肉体を得た、といえなくもない。
その『劉邦』の末尾に付けられた、「連載を終えて」と題するごく短い文章に私は惹きつけられた。冒頭にこうある。
「すじの通らない人は好きではなく、ましてそういう人を小説の中心にすることはできない。」
ひきつづき、作家はいう。自分にとって劉邦はすじの通らない人であった。くらべていえば、項羽の生き方には一貫したものがあり、自分自身の好感を添わせやすかった。
それが、変わったのである。
「それから歳月が経(た)つうちに、楚漢戦争にかかわった傑人たちを調べなおす機会を得た。その作業をおこなってゆくうちに、劉邦にたいする見方が変わった」というのである。
どう変わったのかは、かんたんに書くことはできないだろう。作家は「はじめて劉邦を書いてみたいとおもうようになった」と短い言葉をつぐだけである。私たちは宮城谷氏の傑作の一つである大長篇『劉邦』を読むことができるようになったわけである。
しかし、と読者のひとりである私は思う。十九年前の連作短篇集である『長城のかげ』は、何よりもすぐれておもしろい。こんな作品に出会えることはめったにない、という感想を曲げることはできない。さらにいえば、そこでは不思議な存在である劉邦にも出会えるのだ。その劉邦は、大小さまざまな影のような存在で、登場人物のそばを通り過ぎてゆくものであるにしても、なおどこかしら魅力的なのだ。
作家は、すじの通らない人である劉邦を小説の中心にすることはできない、と語っている。なるほど、だからこそ、『長城のかげ』の劉邦は、通り過ぎてゆく影だったのか。そう考えたとき、私はさらなる驚嘆に襲われた。小説の中心に置くことがためらわれる劉邦を、影の存在として描く。それを連作短篇の手法として、劉邦とその時代を小説にしたのである。ちょっと考えられないような、作家精神の強い働きがそこから伝わってきた。しかも、できあがった作品から、何らかのかたちで大きな影を受けとめながら、動乱の時代を生きぬくそれぞれの人間のドラマが見えてくる。
劉邦の影は、各短篇のなかでもののみごとに生きている。「逃げる」の項羽は、相手の大きな影がどのようなものであるのか、はっきり認識できないまま、そこから逃げるしかなくなるのである。「風の消長」で第一子の劉肥は、心情にも行為にも妄(うそ)があると思うしかない、影のごとき父親から斉という大邦が与えられる。
項羽にとっても劉肥にとっても、影はどうにも捉えどころのないものでありながら、濃密で強力なリアリティがある。
だから、私はここまで『長城のかげ』に現われる劉邦を、「影」とか「さまざまな影」と呼んできたが、読者が影などではなく、劉邦を生身の実体として読みとったとしても、まったくさしつかえがない、と思っている。それほどまでに、私のいう影には、すごい存在感がある。しかも登場人物に対して、謎をかけるようにみごとに変化する。
宮城谷氏が、小説の中心に置くことをためらった人物を、どのようにして小説のなかに持ち込んだのか、すばらしい逆転の発想を読者に汲みとってほしい。