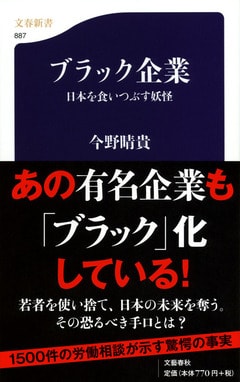ならば今度は映像で勝負だと独学で脚本の執筆を始めたがうまくいくはずもなく、次第に生活の主体は生活費を稼ぐための労働に傾いていった。
そこでこれはいかんと一念発起し、自らに課したのが一日一本映画を観るという課題だった。それも敢えて、自分が大嫌いな恋愛や家族をテーマにしたまともな映画のみという制約を付けた。早速翌日から近所のレンタルビデオ屋に通い、三本で一週間千円の所謂(いわゆる)『旧作ビデオ』を借りては就寝前に鑑賞した。初めはあまりに退屈で眠気を堪えるのに苦労したが、本数をこなすうちに少しずつ順応していき、やがて作品によっては涙が滲むほどの感動を覚えるようになった。
そんなささやかな脳内浄化が三か月ほど続いたある夜、僕はいつものように観終った三本のビデオを持って近所のビデオ屋へ行った。そして返却後、次はどの三本にしようかと店内を物色していると、不意にドアが勢いよく開く音がし「いらっしゃいませ」という店員の声が響いた。
何気なく顔を上げて入り口を見た瞬間、心臓がどくりと鳴った。
入ってきたのは若いカップルだった。二十代前半の大学生に見えた。
二人ともいかにも今時の若者といった洒落た格好をしていたが、問題は女の方だった。一七五センチはある長身で、手足があり得ないほど長かった。艶のある長い茶髪が両肩に垂れ下がり、その間には幼児のように小さく丸い顔があった。
(東京の女だっ!)
僕は反射的に胸中で叫んだ。それは何がどうというレベルではなかった。見た瞬間『異物』と分かる、大宮には決して存在しない八頭身の女だった。それは言葉を返せば、今まで東京でしか見たことがなく、東京以外にいてはいけないと本気で思えるほどの、禍々(まがまが)しさすら感じる美女だった。度胆を抜かれた僕は唖然とし、思わず女を凝視した。女は彼氏らしき男と腕を組んだまま足早に歩いていくと、店の一番奥にある黒いカーテンで仕切られたスペースへ躊躇(ためら)うことなく入っていった。
僕は仰天した。そこはAVコーナーだった。
目に映る光景が俄(にわ)かには信じられなかった。すぐにカーテンの向こうから二人の楽し気な会話が聞こえ、時折弾けるような笑い声が起きた。そして男の「これどう?」という問いに、女の「この前観たじゃん」と答える声が聞こえた時、突然異様な息苦しさを覚えてまともに息ができなくなった。僕は手にしていたビデオ(確か『レインマン』)を棚に戻すと、小走りで店を出た。
時間は夜の八時過ぎだったが、平日のためか通りに人影はまばらだった。
息苦しさは続いていた。とても家に帰る気にはなれなかった。僕は星のないどんよりした夜空を見上げながら、アパートとは逆方向へ歩いていった。歩きながら、あの女の裸体がしきりに脳裏を過り、昂ぶった声が耳元で響いた。それは不快な想念だった。女が裸体をよじる度、腹の奥がひやりと冷たくなり吐き気が込み上げてきた。五分ほど歩いていると、閉店した煙草屋の店先に置かれたベンチが目に入った。僕は老婆のような緩慢な動作で腰を下ろし、背凭(せもた)れに身を預けた。そのまま放心したようにぼんやり虚空を見つめていると、いつのまにか息苦しさが消え、乱れていた感情が揺れ動かなくなった。