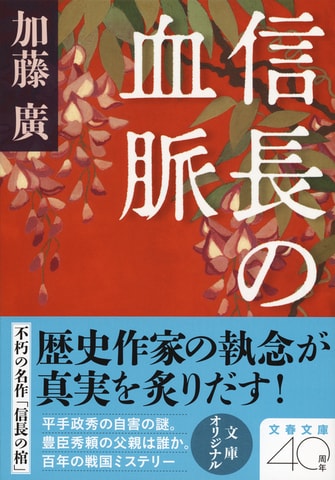第二編「伊吹山薬草譚」は、同じく『信長の棺』と第二作『秀吉の枷』の取材旅行中の車窓で見た伊吹山と、その時、小耳にはさんだ、
「あの山は薬草の宝庫。なぜか日本原産でない南蛮薬草が、二、三あるらしい」
という話題が発端である。
これと織田家の京の菩提寺である阿弥陀寺とを結びつけ、物語を追い込んでいるうちに、信長と接触していたキリシタン宣教師の側から、
「日本の信者への施薬が不足気味なので、是非、我らに薬草園を賜りたい、場所は伊吹山。広さは、五十町歩以上」
という嘆願があった(らしい)という史料が浮かび上がった。
このときひらめいたのが、
「宣教師たちが、重たい楽器や印刷機、あるいは、かさばる敷物や衣類などを船で運んでくるのに、なぜ軽い施薬が足りなくなるのか」
という疑問であった。
そこから、同時代のヨーロッパの薬草事情を調べるうちに、それが中世の魔女――実は生薬を調合する薬師――弾圧による施薬の枯渇、という話に飛躍したのであった。
今日でも生薬というと、一部ドイツ薬のほかは、ほとんどが漢方薬で南蛮薬がないのはそのせいではないのか。
これらの推理が出発点となって、この小説が生まれた。
第三編「山三郎の死」は、長編第二作『秀吉の枷』の執筆中起きた疑問、
「秀頼の本当の父親はだれか」
の追跡調査から浮かび上がった作品である。
なにしろ、秀吉は何十人もの側室と関係を持ち、その中には京極龍子のように、経産婦であり、相思相愛であった女性もいる。それでも子をなすことができなかった。
そんな中年の秀吉の元に飛び込んできた元主君・信長の姪である茶々。
それが、瞬く間に、二児を宿した不思議さ。それも計算すると、その一人秀頼は、秀吉の九州遠征中の懐胎の可能性が高い。といったところからの物語である。
ストーリーは、阿国と名古屋山三郎の美女美男のからみに、「関ヶ原の合戦」の後、大坂方の代表に押し上げられた、気の弱い、出世遅れの三等重役・片桐且元をかみ合わせたものである。
執筆者としては会心の配役であったと密かに自負している。
もっとも、そのおかげで、大学図書館で、歌舞伎発祥時からの勉強をさせられて、短編の割には、史料読みに恐ろしく手間どった。
今はそれも懐かしい思い出ではあるが。
なお、余談だが、秀頼には『秀頼の首』があるそうな。ならば、秀吉には、歯槽膿漏になってとれた歯を、加藤嘉明に与え、それも豊国神社の宝物館にあるというから、なんとか、この二つからDNA鑑定などできないものか。
そんな話を友人にしたら、
「秀吉の歯槽膿漏の歯はともかく、その秀頼の首がインチキならだめでしょう」
と、一笑に付されて終わりだった。
苦心といえば、第四編「天草挽歌」も、執筆がタフだった。
元々、明智左馬助が好きだったから、その息子も、信長、秀吉、光秀の三部作が終わったら書いてみたいとは、かねがね考えてきたことである。
だが、いざ、かかって見ると、「天草の乱」のしょっぱなに、あっけなく戦死してしまっている。これには往生した。
しかし、くじけてはならない、といいきかせて挑戦を続けた。
これまでの天草の乱に関する史料や小説は、ほとんどが、
徳川方か
キリシタン側か
のいずれかの立場から見た史観に基づくもので、その狭間にたつ、
ノンポリの悲哀
を描くものに欠けていると思いついたからである。
そう悟った時、筆が、おもしろいほど進んだ。
最後に文庫のタイトルについて一言、
当初『戦国残照』を考えていた。
これで戦国ものは、ひとまず打ち切りたいという下心があったこともある。
しかし、
「これで戦国ものから引退するのは困ります」
ということで、このタイトルに落ち着いた。
さてそうなると、これからも、戦国ものを続けるか、江戸ものに移るか、それとも一足飛びに現代ものに転向するか。
それは目下思案中である。
二〇一四年秋
(「あとがき」より)