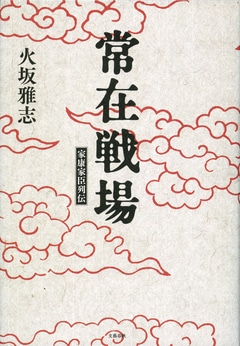武田信玄に仕えた山本勘助。織田信長も落とせなかった稲葉山城を、わずかな兵で奪った竹中半兵衛。豊臣秀吉を天下人に押し上げた黒田官兵衛。文禄・慶長の役の激戦・碧蹄館の戦いを勝利に導いた小早川隆景など、戦国時代には知将、名将がひしめいている。その中にあっても、真田昌幸、幸村父子は、特に高い人気を誇っている。
ただ、真田一族がスターなのは、今に始まったことではない。元禄時代には、昌幸、幸村、幸村の子・大助の三代と、真田家に仕えた八人の豪傑の活躍を描いた軍記物語『真田三代記』が書かれている。この作品は講談へと受け継がれ、明治に入ると、立川文庫などの講談速記本によって広まる“真田十勇士”ものの元ネタの一つになっている。そして、立川文庫の世界をアレンジした連作集〈柴錬立川文庫〉シリーズの一編として「真田幸村」「真田十勇士」などを発表した柴田錬三郎、父の昌幸、弟の幸村と敵対する道を選んで乱世を生き延び、松代藩の初代藩主となった信之を主人公にした『獅子』、集大成ともいえる大作『真田太平記』を書くなど、真田家をライフワークにしていた池波正太郎など、真田家に魅了された作家は少なくない。
“真田家中興の祖”と呼ばれる幸隆、上田城を拠点に徳川の大軍を二度も撃退した昌幸、家康に仕えて乱世を生き延びた信之と大坂夏の陣で家康を後一歩まで追い詰めた幸村兄弟を主人公にした本書『真田三代』も、歴史小説の激戦区といえる真田を題材にしているが、従来とは異なるアプローチで、真田家三代の実像に迫っている。
まず著者は、なぜ真田家が、沼田、上田といった山間部にこだわったのかを明らかにしている。気温が低く、開けた土地も少ない山間部は米作りに不向きなので、現代の目から見ると、そこに固執した理由がよく分らない。これに対し著者は、利根川水系にある沼田と、信濃川水系にある上田は、日本海と太平洋をつなぐ舟運の要衝にあり、幸隆と昌幸がここに進出したのは、貿易ルートを掌握することで、経済的利益を得ようとしたからというのだ。昌幸は、臣従していた家康に沼田を北条に差し出すよう命じられた時、一族が血を流して手に入れた領地を返す必要はないと拒否するが、これを著者は、中央の横暴に抗った地方自治体の戦いと位置付けているのである。
考えてみると、戦国時代は、各地の大名が室町幕府の支配を離れ、自治権を持って領国を支配していた。戦国大名も、江戸時代のように譜代の家臣が支えていたのではなく、一国一城の主ながら勢力が小さいので有力武将に従っている小領主(国人)の協力がなければ政権運営ができなかったので、まさに地方自治の時代だったといえる。
それなのに、戦国を舞台にした歴史小説は、中央集権的な体制を築こうとした信長や秀吉ばかりがクローズアップされ、地方に注目した作品は少なかった。国を失い、信玄に仕えることで再び領地を手に入れようとした幸隆、父と自分が切り取った領地を大国から守った昌幸の物語は、地方という視点から戦国史をとらえる新たな試みになっているのだ。著者は、上杉謙信が何よりも重んじた「義」の精神を守り、越後、会津、米沢で理想的な領国経営を行った上杉景勝、直江兼続主従を描いた『天地人』以降、中央に君臨する秀吉、家康に最後まで抗った東北の雄・伊達政宗が印象深い『臥竜の天』、中国の太守・毛利家の外交を担当した安国寺恵瓊を主人公にした『墨染の鎧』など、地方の戦国武将にこだわっている。その意味で、著者の関心が、天下統一とは無縁だった信州の小大名でありながら、その名を歴史に刻んだ真田一族に向かったのは必然だったのである。米より、寒さに強い小麦の栽培が盛んだった信州の風土と文化を再現するため、信之と幸村の母が小豆ほうとうをふるまうシーンがあるなど、ローカル色を前面に出しているのも、作品の魅力となっている。