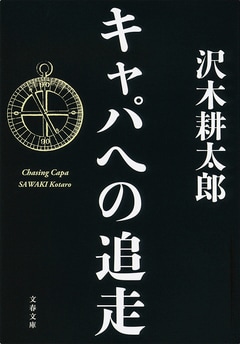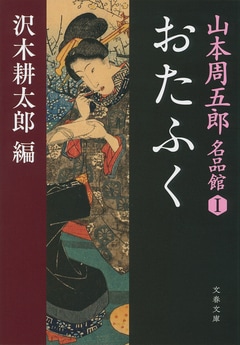カルチャー&インタビュー誌「SWITCH」を創ったスイッチ・パブリッシング代表取締役の新井敏記さんは出版界に様々な変革を起こしてきた。二〇一五年十一月に、経営・編集手腕が評価され、伊丹十三賞を受賞した名物編集者に話を聞いた。

今回選んだ三冊は、雑誌編集者として歩んだ道筋の中で、僕が最も影響を受けた作家たちの本ですね。
物語を好きになった原点は、十五歳のときに読んだ大江健三郎さんの『芽むしり仔撃ち』。閉鎖された状況に取り残された少年たちを、大江さんなりにアレンジした作品に、ある種の熱を感じたんです。僕も田舎育ちでしたから、山あいの村の原風景が共有できたのかもしれません。疫病におかされ大人たちが捨てた村で、少年らがサバイバルするのですが、僕は、この村を自分の通う学校と読み替えていたんでしょうね。先生からスポイルされ、孤立していた状況を、この小説に重ねることで自分を救済することが出来たんだと思います。
僕は幼い頃から文章を書くのが大好きで、様々な手段を使って表現したかった。例えば高校二年の夏にバイトをして貯めた三万円を握りしめて、書いた原稿を印刷所に持ち込みました。印刷所の人には「これじゃ紙代にもならないよ」と言われましたが職人さんの好意で、「活字を自分で拾うならいいよ」ということになった。でも活字なんて拾えなくて、見かねた職人さんに手伝ってもらって、「千年王国」という雑誌ができた。それを大江さんと小林秀雄さんに送りましたが当然、返事は届かなかったです(笑)。
その後、大学を卒業して、「ポパイ」編集部でインタビュー原稿を書いたりしていました。あるとき先輩編集者の紹介で親しくなった片岡義男さんからアメリカのカルチャー誌「ローリングストーン」を段ボール二箱分譲り受けたんです。創刊号は三十二ページくらいのタブロイド判で、表紙から最後のページまで、すべてジョン・レノンの写真とインタビューだった。無名な新人記者にジョンはビートルズをなぜ解散するのか、真摯に答えていた。それから約十年後、ジョンが凶弾に倒れるまでその雑誌は、一人の人間を追いかけ続けたのです。段ボールの中の束には、なぜビートルズを解散するか、なぜオノ・ヨーコと結婚するかについて、ジョンの宝珠のような言葉が綴られていました。これを読んだ時に、“僕には「ポパイ」は作れないけれど、こういう雑誌を作りたい”と考えて、一九八五年に「好きな人に会いに行き、話を聞き、書く」という編集方針で「SWITCH」を立ち上げました。僕にとってのジョン、誰にインタビューしたいかと考えたときにまず思い浮かんだのは大江健三郎さんと、沢木耕太郎さんでした。
一九九〇年に、大江さんの故郷で取材し、大江健三郎特集を作ることができたときは本当に嬉しかったです。先日、伊丹十三賞をいただいて、愛媛県松山市で基調講演をしたのですが、そのときに大江さんの故郷(現・愛媛県喜多郡内子町)の方々が、「ぜひ大瀬に足を運んでほしい」と声をかけてくださった。このことが感慨深く、二十年ぶりに再訪したんです。思い出深い時間でしたね。
沢木さんに夢中になったきっかけは、『テロルの決算』『一瞬の夏』を読んだことですね。『一瞬の夏』はスポーツ・ノンフィクションではあるんだけれど、沢木さん自身がボクシングのマッチメイクまでする。取材というものからは逸脱しているけれど、取材対象者とともに生きるという書き手の姿勢が貫かれていて、ハラハラしながら読んで一緒に僕も駆けているような気持になりました。沢木さんには手紙を書いて、在宅している早朝に電話を掛け、ようやく喫茶店で会ってもらえることに。とっておきのプランを持っていったんですが、沢木さんは「うーん、僕は書けないな。じゃあ、またね」とどこかに消えていく。後で聞くと、「当時は、流儀として依頼を受ければ会ってキチンと断ることにしていた」らしいのですが、僕は「またね」は次があるということだと受け止め、懲りずに執筆のお願いを続けました。五、六回くらい会ったときだったでしょうか、断るときは丁寧だった沢木さんが、「しょうがねぇな」という感じで「お前のために三つ、考えてきた」と言ってくれたんです。エッセイか、ノンフィクション、最後は、新しい挑戦だから成否は分からないけれど“日記”だと。僕は躊躇なく三番目を選んだんです。それから一ヶ月――。ワープロで書いてプリントアウトした原稿を沢木さんが持ってきてくれたんです。連載のタイトルは「246」。『深夜特急』を書き始めた頃の旅の過程や取材の話も興味深く、また当時三歳だった娘さんとのふれあいが綴られていたことも心動きます。沢木さんの『一瞬の夏』という物語は僕にとって原稿をいただく時間と重なって、ある青春の一時期のかけがえのない世界だったのです。
最後の一冊は、もうひとり僕が憧れた星野道夫さんの本です。「アラスカに面白い写真家がいるから会ってみない?」と友人に紹介されて、御茶ノ水で会ったのですが、二人ともお酒も飲まないし、食事も早くて好物が珈琲ととんかつ。すぐに意気投合しました。彼の魅力は、その語り口の柔らかさ。「アラスカはですね、すごく自然が豊かで悠久の時間が流れている……人が誰もいない光景を新井さん、想像してみてください」。こんな言葉を投げかけられて、わくわくしたことを今でも覚えています。当時の星野さんは、アラスカに自分の家を持っておらず、夏はアラスカの丸太小屋で暮らし、冬になると帰国して、フィールドノートや撮影したネガの整理をしていた。で、会うのは冬、日本でいろんなことを話したんですが、見えない世界に価値を置くという彼の写真と文章に魅かれ、雑誌で特集しようと願ったんです。
星野さんはその後、アラスカに土地を買い、家を建て『イニュニック[生命]』という本を書きました。「自然や旅をテーマにした、星野道夫責任編集の旅雑誌を作りたい」、星野さんと夢を温めていた一九九六年――。モンゴロイドがシベリア、ベーリング海を経て、アラスカに渡った足跡をたどる旅の途中で、星野さんはヒグマに襲われて急逝してしまった。“旅雑誌を作る”約束というか、自分の中の宿題がなかなか果たせずに、十年近くたった二〇〇四年にようやく「Coyote」を創刊できたんです。
雑誌作りの秘訣は?と、よく聞かれるのですが、“自分が面白いと思ったものにこだわる”ことと、“好きということを見つける”だと思います。「SWITCH」もいつしか雑誌としての評価を得て、こちらからオファーしなくても取材してほしいという人も現われるようになった。編集者はどこか狩猟本能を失ってはいけないと感じていた。こういうやり方をしていてはだめだ、という気持ちが湧き上がってきたんです。“もう一度、この雑誌を揺らしたい”というのは、口で言っても伝わりにくいから、昨年、編集長として現場に戻りました。
この九月には、文芸誌「MONKEY」の連載をもとにした村上春樹さんのエッセイ集『職業としての小説家』を刊行しました。中身に自信がありましたが、流通を担う取次会社が、中小の出版社に突き付ける条件は厳しかった。悪戦苦闘しているときに、紀伊國屋さんが「小さな本屋がドンドンつぶれる状態を打破するために新しい取り組みをしたい」と、初版の大半を買い取り、一般の本屋に流通するという提案をしてくれた。紀伊國屋の独占販売ではなく、“紀伊國屋が町の小さな書店に流通させ集客の起爆剤とする”というプランが成功し、二十万部のヒット作となりました。
これからも、雑誌や本を舞台に、何かをしでかしていけたらと思っています。
お勧めの3冊
・『芽むしり仔撃ち』 (大江健三郎 著) 新潮文庫
・『一瞬の夏』(上・下) (沢木耕太郎 著) 新潮文庫
・『イニュニック アラスカの原野を旅する』 (星野道夫 著) 新潮文庫