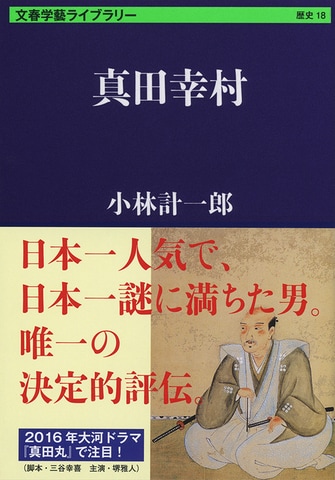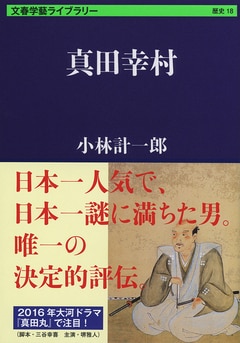前編より続く
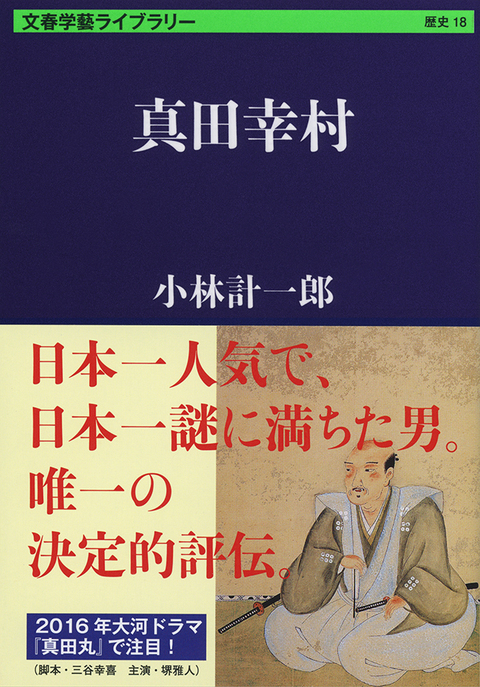
○
これから、史実ではなく文学作品における幸村像の生長をたどってみる。現代の歴史小説まで続くのであるが、本稿では『真田三代記』以前を区切りとする。
なお以下の文章は、拙著『大坂城の男たち―近世実録が描く英雄像―』(二〇一一)、及び雑誌『文学』二〇一五年七・八月号「特集 実録 文学の語る過去と人」所載の拙稿「幸村見参―大坂の陣の実録と講釈」と重なるところが多いことをお断りしておく。
大坂の陣を描いた文学作品中、成立の最も早いのは、『大坂(おざか)物語』である。冬の陣が終わって、「天下太平、国土安穏、めでたき事」と祝して出版したところ、夏の陣が起こったため、終結後に新たに上下二巻として出された。下ができたため、それより前の作が上となったわけである。禁令より早かったので、この作は刊行されている。
文学作品なので、やはり原文を読んでもらいたい。ただし、表記にはかなり手を加えた。( )の中は筆者による注、口語訳である。以下の実録作品でも、要約を掲げることが多いが、引用する場合は同様。
(真田丸の戦い)真田左衛門佐がたて籠る取出(とりで/砦)の前に、篠山(ささやま)といふ藪あり。その陰に、城より鉄砲を出して、つねに打たせけり。松平筑前守(前田利常。利家の子)先手の本多安房守これをみて、「あの篠山に籠りたる者どもを、うち取らん」といふまゝに、ひし〳〵とこしらへ、夜のうちに押し寄せ、篠山をおつとり巻き、時(鬨)をどつと作る。されども敵には音もせず。不審に思ひ、人を入れ見せければ、敵は城のうちへ引きこもり、こゝには一人もなし。寄せ手も興ざめ顔にて引かんとする所に、真田、城の矢切(やぎり/矢を防ぐ楯)に立ちあがり、「かた〴〵は篠山に勢子(せこ)を入れ、雉狩りをし給ふか。日ごろは雉もありつれども、この程の鉄砲にゆか(寝床)を替へて候。御つれ〴〵にも候はゞ、この城へ懸からせ給へ。いくさして遊ばん」とぞ申しける。
敵を挑発する智将真田左衛門佐(この作では幸村という名は見えない)。東軍はまんまとこれに乗って、大敗を喫する。真田丸で東軍を挑発する場面は後続作に受け継がれるが、幸村ではなく、家来が声を懸けることになっている。
(幸村討ち死に)真田は、味方うち負けたりと見ければ、誰(た)が陣ともいはず駆け入り〳〵戦ひけるが、越前少将(松平忠直。家康の孫)の手にて、大音あげて名乗りけるは、「関ケ原の一乱以後、高野の住まゐを仕り、むなしく日月を送る所に、幸にこの乱出できて、かたじけなくも故太閤相国の御子、右大臣秀頼公に、一人当千と頼まれ申したる、真田左衛門佐とは我が事なり。心あらん若者ども、我が首取つて、将軍の御感に預からぬか」と呼ばはつて、あたりをはらつて(威儀堂々として)見えけるが、鉄砲にて胸板を射ぬかれ、馬よりまつ逆さまに落つる所に、越前少将の郎従折り合ひて、つゐに首をぞ取つたりける。
越前家の手によって幸村が打ち取られたのは史実らしい(本書「幸村戦死」)が、最後の幸村の科白を、戦闘の最中に誰が書き留められよう。作者の想像である。「むなしく日月を送る所に、幸にこの乱出できて」というあたり、十四年の蟄居生活を余儀なくされた幸村が、いかにも口にしそうな科白ではないか。よくできた創作というべきである。『大坂物語』下の末尾はこう結ばれている。
かゝるめでたき天下の守護は、上古にも未だなし、末代とてもありがたし。たゞこの君(家康)の御寿命、万歳〳〵万々歳と祝したてまつる。
徳川による平和を寿(ことほ)いで終っており、この作品全体は徳川贔屓である。大坂の陣の終結によって、天下は徳川に帰したという「宣伝」が刊行の目的であったとする説もある。そういう『大坂物語』の中で、大坂方の武将真田幸村の活躍は鮮明に描かれていた。