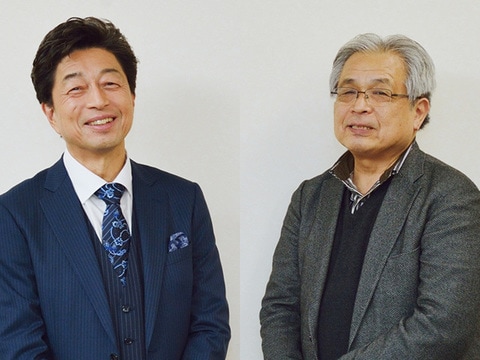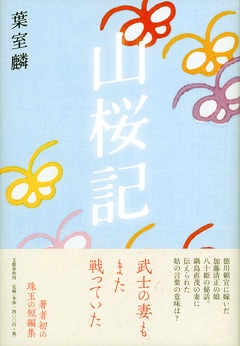時代小説とは何だろう。いや、歴史小説とは何か。
よく言われるのが山本周五郎の作品が時代小説で森鴎外の作品が歴史小説という例えだ。その後の作家で言えば、藤沢周平が時代小説、司馬遼太郎が歴史小説である、という区分になるのだろうか。
しかし、この区分は、実ははなはだ怪しい。それぞれの時代を生きているひとも歴史の中にいるのだろうし、歴史として描かれる人物も自らが生きた時代から切り離すことはできない。
そう考えると歴史や時代を鳥瞰するか等身大のひとの視点で見るかの違いだけではないか。
江戸時代を描いた小説にも歴史はこめられているし、戦国時代を描いた小説にも当然のことながら時代の匂いはあるだろう。
こんなことを細かに述べるのは、『黄蝶の橋』が江戸の市井を題材にした体裁をとりながら、ひそかに、いや、むしろ大胆に歴史が込められているからだ。
ひょっとすると、読者に歴史の知識を要求し過ぎているかもしれない、という危うさを踏まえて、作者が伝えたかったのは何なのか。
それを知るには前作『墨染の桜』での設定から見なければいけないようだ。
主人公は京の呉服屋更紗屋のひとり娘おりん。父を亡くし、店がつぶれたため叔父を頼って江戸に出てきた。
叔父夫婦と長屋で暮らしつつ、様々な事件と出会いながら、更紗屋の再建を目指す。江戸情緒の中でひとりの娘が苦難にめげずにひととふれあい、成長していく物語であろうとうかがわせる。
だが、その発端となる更紗屋がつぶれる経緯はかなり特殊なものだ。
幕府の大老酒井忠清は四代将軍家綱の没後、皇族の有栖川宮幸仁親王を将軍にしようと企んだ。
更紗屋は幸仁親王の母の実家である清閑寺家に出入りする呉服屋だった。
将軍家の相続をめぐる暗闘で清閑寺家が力を失うとともに更紗屋も店を畳むことになるのだ。
家綱が死去した際、酒井忠清が皇族を将軍に迎えようとしたとされる説は昔からある。
真偽のほどはともかくとして、家綱を補佐して権勢を振るい、江戸城大手門下馬札付近に屋敷があったことから〈下馬将軍〉とまで言われた忠清ならいかにもありそうだ、と当時のひとも思ったに違いない。
皇族を将軍に据えるというのは、現代から見るとありえない話のようだが、実際にはそうでもない。
徳川家康は将軍になり江戸に幕府を開いたとき、本当は心もとない思いをしていたのではないだろうか。
なぜなら、それまでの足利将軍は京の室町で幕府を開いた。当時の大名たちにとって将軍は京にいるものだった。
織田信長が足利義昭を擁して上洛し、天下取りへの道を歩みだしたように、戦国時代は一面では京から逃げ出した将軍がいかに京に戻るかという時代でもあった。