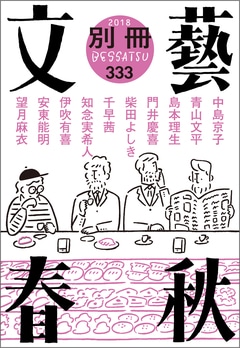そう言うと、シャネル風ジャケットの女性は喜和子さんを引っ張り上げるようにして、また、追い立てるようにして、施設の建物のほうに去って行った。喜和子さんは捕まった小動物のような表情でこちらを振り返ったが、声を出さずに口だけを動かして、
「ごめん。またね」
と言うに留まり、わたしはなんの説明も受けなかった。しばし呆然と、わたしはその場に残された。
そのまま帰ってしまうわけにはいかない気がした。なにしろ、久しぶりの再会なのだし、そこへ、あきらかに喜和子さんと敵対するように見える女性が現れたのだから、放っておくわけにはいかないと思えてきた。
そもそも、喜和子さんに子供がいるなどという話は聞いたことがなかった。だから、あの女性が親族であるかどうかだってわからないではないかという想像が、むくむくと胸に広がってきた。しばらく会わないうちに、施設にまで入ってしまったのだ。ひょっとして認知症めいたものが進行して、あの女性に騙されているのではないだろうか。
「おぼえてないの、わたしですよ、お母さん」
とかなんとか言われて、なけなしの年金を騙し取られている可能性だってあるのではないだろうか。お母さん、お母さんと、言い立てるあの口調に、愛情がみじんも感じられない。ビジネスくさい、他人行儀な響きがある。いままで見たことのないような、頼りない表情を浮かべて、喜和子さんは引きずられて行ってしまった。なぜ喜和子さんは抵抗しないのか。魔法にかかったようにおとなしくなってしまった喜和子さんは、むしろ病気にでもかかっていると考えた方がいいのではないだろうか。
つらつら考えていたら、ほんとうに心配になってきて、わたしは早足で施設に向かった。
案の定、といっていいのかどうかわからないが、施設からは、あの女性のキンキンした声が響いてきた。
「そういう問題じゃないでしょう。こっちは勝手に名前を使われたんですよ」
「まあ、そう、感情的におっしゃられても」
なだめているのは施設の人のようだった。
「そちらだって、いわば、この人に騙されたわけでしょう。ほんとにこわい人」
「うちとしては、改めて、お嬢様に書類作成にご協力いただく形で対処できれば、この件に関しては・・・・・・」
「そんな、事後承諾みたいなこと、わたしはできません。夫にも相談しなきゃならないし。主人には何も言わないで来てるんです。知られたらたいへんですから」
「しかし、そうなると、ご本人様が・・・・・・」