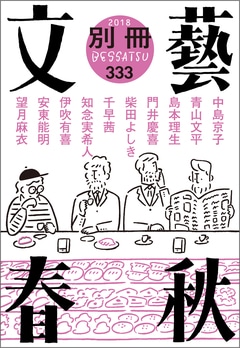「いままでまるで娘なんかいないみたいに生きてきて、ここに来て急に。どこまで勝手な人なんだか」
黙ってその場をやり過ごそうと思ってか、下を向いて静かにしていた喜和子さんがふと顔を上げ、わたしの方を見た。わたしは笑顔を作って手を振った。喜和子さんの頬にも、少しの笑みが戻った。
「何を笑ってるんですか? 笑うとこですか?」
女性はカッとなって喜和子さんに食ってかかり、その視線をたどってわたしの方をすごい形相で振り向いた。
わたしはちょうど、施設の入口の自動ドアを抜けて、建物の中に入ったところだった。
喜和子さんはわずかな笑顔をさっと消して、それからとても静かな表情になった。これから起こることを知って、あらかじめ諦めておこうというような顔つきだった。
ずっと奇妙に感じていたのは、そうした彼女のいわば受け身の態度で、初めて上野公園で会ったときからこっち、喜和子さんには清々しいような自由がいつもまとわりついていたのだったが、その気持ちのよさ、風通しのよさのようなものが、すっかり影をひそめてしまっていることだった。喜和子さんにこんなふうにずけずけ物を言う人を見たことがなかったと同時に、そんなふうに言われっぱなしで反論もしない、窮屈そうな喜和子さんを見たことがなかった。なんとも、彼女らしくなかったのだ。
「あのう」
と、わたしはもう一度意を決して声をかけた。
施設の人と、シャネル風ジャケットの女性、そして喜和子さんが一斉にこちらを見た。少なくとも施設の人と喜和子さんの目には、どうにかしてこの場を打開してほしいと言いたげな光があったような気がした。
しかし、わたしが何かに貢献できたとはまるで思えない。
結局のところ、その怒っていた女性は解決を曖昧にしたまま帰って行ってしまった。
わたしは喜和子さんのために少し長く施設にいた。
見たことがないほど沈み込んだ喜和子さんは、一段と小さく見えた。わたしに、これまで見せていなかった一面をはからずも見せてしまったことも落ち込みの要因かもしれないと思って、一度はその場を辞そうと思ったのだけれど、喜和子さんは力のない声で、
「居て」
と言ったのだった。
「あの子が来ると知ってたから、この日を指定したの」