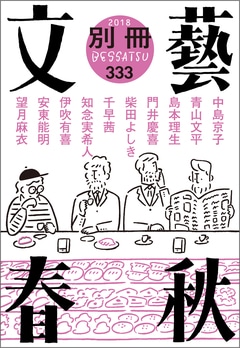前回までのあらすじ
フリーランスの雑誌記者だった「わたし」が喜和子さんと知り合ったのは、十五年ほど前のことだった。彼女は上野図書館に並々ならぬ愛着を抱いていて、唐突に図書館そのものを主人公にした小説を書いてよ、と「わたし」に持ちかけてきた・・・・・・。とにもかくにも「わたし」と喜和子さんの友情は始まったが、やがて疎遠になる。新しいパートナーができたり、小説原稿の依頼が増えてきたりと「わたし」の生活環境が変わったからだ。久しぶりに会ったとき、喜和子さんは老人ホームに入っていた。旧交を温めていたわたしたちの前に、喜和子さんのことを「お母さん」と呼ぶ女性が突然現われる。喜和子さんに娘がいるなんて話は聞いたことはないけれど・・・・・・。
その女性は小柄できめ細かい肌をしていて、プリント地のワンピースに衿のないシャネル風のツイードジャケットを羽織っていた。のしのしと歩いてくる足元は五センチほどのヒール高のパンプスだった。こうした服装は、およそ喜和子さんの知り合い、もしくは義理であろうと実子であろうと娘らしくはなかった。
しかも、肩まで垂らした髪はきちんと栗色に染めていて、丁寧にカールを描いていた。パーマヘアではなく、毎日自分でヘアアイロンをきれいに当てなければ作れないように思われるものだった。「名古屋マダム風」という形容が思い浮かんだが、実際に名古屋のマダムがそういう髪型をしているのかどうかは、定かではない。
「今日、来るって、施設の方にはお伝えしておいたんですけど。どうしてこんなところにいるんですか」
のっけから好戦的で、目つきも悪かった。
わたし自身はむっとして、喜和子さんがぴしゃりと言い返すのを待ったが、彼女が困ったような怯えたような表情を崩さずに下を向いてしまったのも意外な気がした。
「施設の方といっしょにお話しすることになってたじゃありませんか。時間ですから戻ってください」
女性の口調じたいは丁寧だったが、態度がまったく丁寧ではなかったし、傍らにいたわたしには目もくれないでまくしたてるのも不愉快だった。そこで、少し抵抗の意を示しておくべきだと考え、わたしは小さな声で主張した。
「あのう」
「何ですか? どちらの方か存じ上げませんけど、ちょっとハハと施設の方と話があるんで失礼します」