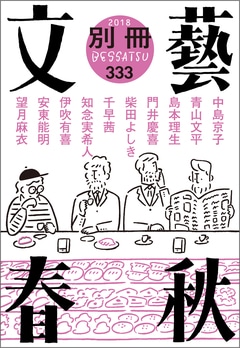と。だから、わたしはあらかじめ、あの場面を目撃すべく呼ばれていたようなのだった。あるいは、わたしという他者が闖入することで、収まりのつかなくなったなにかを棚上げにしておく効果を、期待されていたのだとも言える。
喜和子さんがあの女性に騙されているのではないかというわたしの想像はとてつもなく的外れだった。騙すというか、言わば利用したほうが喜和子さんで、あの女性は迷惑を被った側だった。しかしそれは、迷惑というようなものなんだろうか。
「息子さんのお嫁さん?」
少し落ち着いてから尋ねると、喜和子さんは不思議そうな顔をした。
「ううん。娘。あたしの実の娘」
「そうなんですか! なんかこう、似てませんね」
「そうよね」
「それに、話し方が、なんというか」
「他人行儀?」
「まあ、そう。すごく」
「嫌いなんでしょ、あたしのこと」
淡々と、事実を告げるように喜和子さんは言った。
実の娘! あまりに多くの情報がいっぺんにやってきて、わたしは混乱した。
「変なところを見せちゃって、悪かったわねえ」
そう言う喜和子さんは、まだ少しこわばっていたが、ゆっくりと本来の表情を取り戻しつつあるようにも見えた。わたしたちは、彼女の小さな部屋に戻り、空調をつけた。喜和子さんはベッドにもぐりこみ、わたしはその脇に置かれた、子供用のような小さいサイズの応接セットの椅子に腰かけた。応接セットにはかろうじて二脚の椅子があったけれど、そこに二人座るとなんだか近すぎて話がしづらく、一人はベッドにいたほうがいいくらいの距離だった。
その狭い部屋を手に入れるために、喜和子さんは思い余って娘の名前を借りたのだった。
谷中の木造長屋を引き払うには、別の住まいを見つける必要があり、体調と、この先の人生を考えて彼女は、その老人ホームにたどり着いた。入居費用や月々の利用料は、年金その他の彼女の持ち金で賄える計算だった。だから、入居に際して問題になったのは、身元引受人を誰にするかだった。
「よくわからなかったのよ。施設の人には、ご親族の方でないと身元引受人にはなれませんと言われる。身元引受人がないと入居できないって。死んだ後のことを娘に見てもらう気持ちがないんだと言っても、それはそれで遺言でも書いておけばいいじゃないですか、入居のための、書類だけのことですよと言われて、切羽詰まっちゃってね。しょうがないから、あの子の名前を勝手に使ったの。迷惑かける気はないわよ。お金は自分のがあるんだもの。とにかく入れればいいんだからって。ああ、でも、やっぱり、もちろん、間違ってたわよ」
そう言うと、喜和子さんはベッドの上でくしゃくしゃに顔を歪めた。