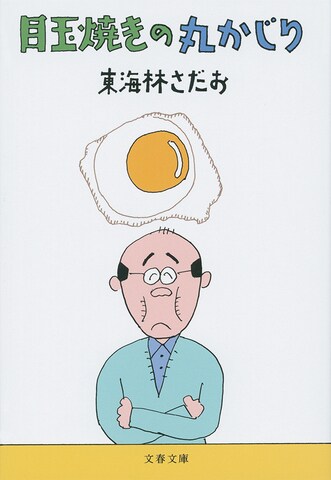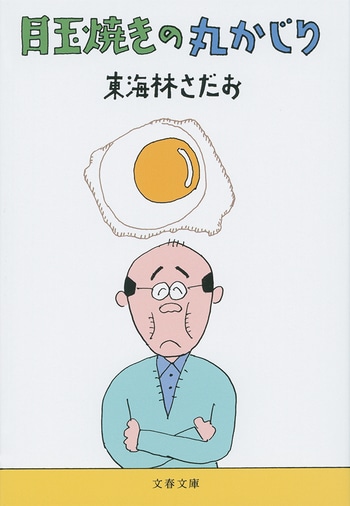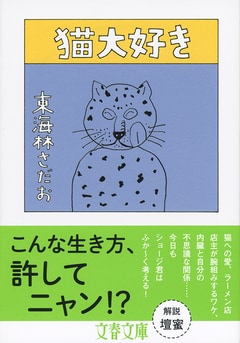ほかにも、ちょっとした例えにアンコものが登場したりするので、それらも組み入れたら相当濃厚なアン(コ)ソロジーになるだろう。完成した私家版をあらためて頭から読む。わかっていたのに涙が出るほど面白い。読み進めるうち、ただ面白いだけでなく、この一冊(?)に東海林さんの魅力がアンコ玉のように圧縮されている気さえしてきた。小豆と砂糖と水だけでできたアンコというつかみどころのない対象だからこそ、東海林さんの描写とキュートネスが冴え渡っているのをダイレクトに感じられるのだ。
中でも私は、東海林さんが食べものを人格化する瞬間が好きだ。「出た!」と思う。「キンツバのチョロピリ」に登場する、弟にスケスケのボロ下着をつけさせられたキンツバ姉さんの絵! 「豆大福の豆は何粒が適正か」で「あたしだって何かしたい」と豆製品の小商売を始める大福の皮専業主婦も憎めない。「栗で悶悶栗蒸し羊羹」の冒頭で鮮やかに書かれている栗大福の栗の「いた感」に匹敵する「出た感」である。
もちろん、本書の「アンコかわいや」でも、「出た感」を堪能した。東海林さんは和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを機に世界の檜舞台に立つかもしれないアンコの無防備な身なりを案じる。小豆相場で夜逃げした過去を持つアンコの先祖の存在を認め、今なお取り立てにおびえて布団のスキマから外の様子を窺うどら焼きのアンコを憐れむ。
アンコ自体の描写もすばらしい。「農業の甘さ」「ざらつく甘さ」「粉感」。「つぶアンはスキマが多いからその分損。こしアンはスキマがないから得」。これまでアンコの表現に心を砕いてきたつもりだが、こんな形容、こんな発想、思いつきもしなかった。
東海林さんの食欲の掘り下げ方には、ある種の「型」を感じる。分解の美とでも言おうか。その昔、ラジオを分解しては組み立て直して遊んでいた子供のひとり遊びに似た好奇心と記憶力。執着ではなく愛着。自分の好き嫌いにぴったりと添うてやるぞ、一行たりともズレないぞ、という決意のすごみ。その型を畏れ多くもお借りして「食う」という行為をしてみると、たどたどしい足取りながら自己の世界に没頭できて、その間、不思議と心がなぐさめられる。何を食べるかではなく誰が食べるかが重要なのだ、だからキミもせいぜい好きに食えよ、と東海林さんにやさしく肩をぽんぽんされているようで気持ちが落ち着く。「ケチでみみっちくてせこくて猜疑心が強くて根性が曲がってる」と後ろ指をさされようとも、こしアンつぶアン両方好き、と素直に開き直れるのだ。
ともあれ、丸かじりシリーズの〇〇だけ食い、楽しいので是非ともおすすめしたい。卵だけ食い、ジャムだけ食い、おにぎりだけ食い、カツだけ食い。「ニッチャコニッチャコ」「メシャッ」「ヘギヘギ」などのショージ君的オノマトペだけ食いもできそうだ。食育が叫ばれる時代に偏食をすすめていいのか? いいんです、好きに食べれば。