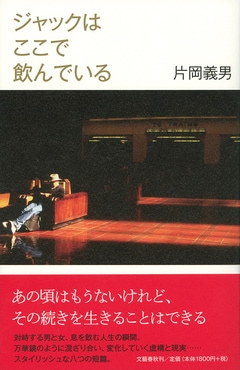大人たちが、いや、国が選んだ方法は、僕の育て直しだった。
とある一人の医師はこう言ったそうだ。
「神さまの恵みがあれば良くなる可能性はあるかもしれない。もし発育が遅れていたとしても、まだ追いつく可能性はある。とはいえ、最終的に彼がどうなるのかはまったく分からない」
まるで僕は新種のウイルスみたいだった。けれど、ニュータイプならまだましだ。どちらかといえば、僕はルー(引用者註*晴信が少年時代に母に連れられて過ごした新宗教教団の中堅幹部で医師)が細い指で解剖していた、あのマウスみたいじゃないか。自分自身がマウスになりたくないと、あんなに思っていたのに。
あのときの僕は、国に解剖され、骨の配置を変えられ、皮膚の色を変えられてしまう、そんな恐怖にかられていた。しかし、この医師が言った神さまとはいったい誰のことなのだろう。僕の神さまでないことだけは、わかっていたけれど。〉(285~287頁)
個人の魂を国家が管理して、国家に不都合な世界観や思想を持つ者に関しては、それを徹底的に改造する。これはファシズムの思想だ。本書で描かれているのは、「正常」「人権」という名で、知らず知らずのうちにわれわれの思考を支配しているファシズムのグロテスクな姿を浮き彫りにすることなのである。医療少年院以後、倫太郎こと晴信は、国家による男性的ファシズムの完全な監視下に置かれる。しかし、ファシズムはこのような形態に限られない。社会の側からの女性的ファシズムもあるのだ。
〈「母は僕たちのすべてを吸いつくす。すっかり包み込んでだめにしてしまう。子と一心同体になって、時には死を選ぶことも躊躇しない」
ルーが言葉にする「母」と、自分の母親が僕のなかでは一直線に結びつかなかった。ルーの言う母には顔も体のカタチもない。なんだか、やわらかくて、ぐにゃぐにゃしていて、手のひらに載せたら、指の間からだらんとたれてしまうゼリー状のもののような気がした。