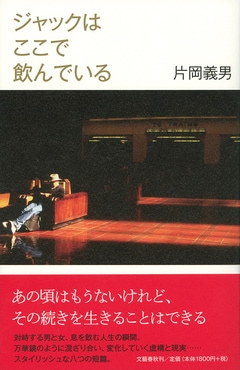「この国のすべての病は、母から起こる。母を意識的に自分から切り離さないといけない。けれど、家族、という檻のなかではそれは難しい。母は家庭の権力者であるから。母はその場所でファシズムを強行する。僕らはその場所から逃げ出さないといけない。間違った接合を解いて、その関係に自覚的であるべきだ、と、お父さまは言う。接合されたままなら、その人は一生閉じて、分離して、孤立したままだ」
ルーの言っていることは正直よくわからなかったし、僕の質問の答えでもないような気がした。けれど、この日だけでなく、母というものを語るとき、ルーがいつも以上に饒舌になっているのを僕は感じていた。〉(165~166頁)
この小説の登場人物は、女性的ファシズムと男性的ファシズムのいずれかに組み込まれている現実から脱出することを試みているのだが、誰もそこから逃げ出すことに成功していない。まさに21世紀の日本社会を『さよなら、ニルヴァーナ』で描かれている世界と類比的にとらえることができる。
作家とは、誰もが常識と思っている事柄の奥にまで踏み込むことをせずにはいられない習性を持っている。このことを窪美澄氏は、挑発的な表現で語る。
〈Aは人間の中身が見たくて、七歳の子どもを殺した。中身。それは少年Aが、事件を起こしたときに、何度も口にしていた言葉だ。人間の中身が見たかった。だから僕は、あの子を殺した、と。彼は何度もそう言った。けれども、当時、誰も、その真意をくんだ者はいなかったと思う。
私も中身が見たいのだ。人がひた隠しにして、心の奥底に沈めてしまうもの。そこに確かにあるのに見て見ぬふりをしてしまうもの。顔は笑っていても心の中で渦巻いている、言葉にはできない思いや感情。皮一枚剥がせば、その下で、どくどくと脈打っている何か。それを見てみたい。
そういう意味では、私とAは同志なのだ。〉(402~403頁)
作家が書くことに固執するのは、「人間の中身を見たい」からなのだ。これは、小説、ノンフィクションのジャンルにかかわらず、すべての作家が持つ病理なのだ。その意味で、私もAの同志なのである。