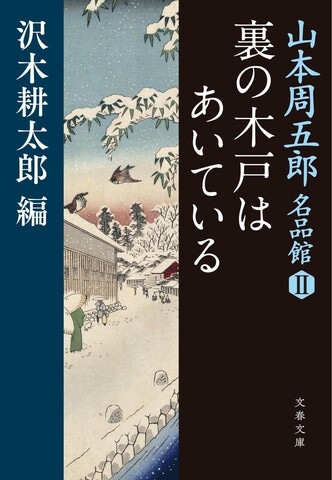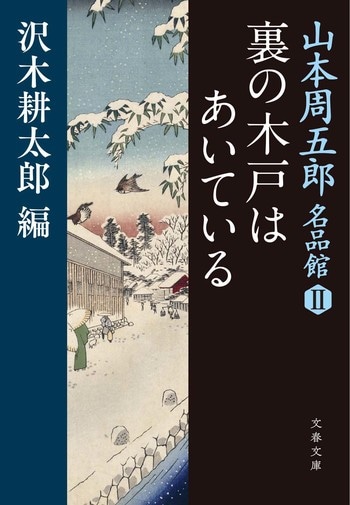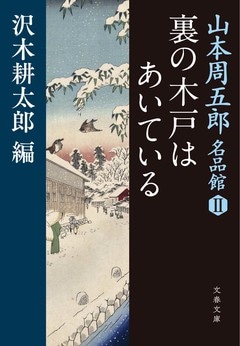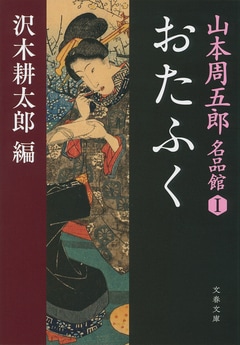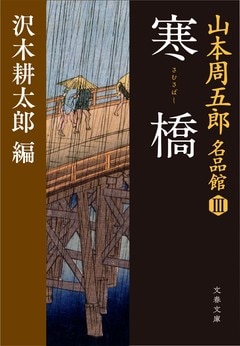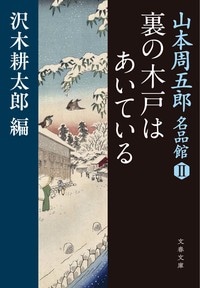
「こんち午の日」
これは耐える男の物語である。それは一見すると意気地なしと見間違えられかねない男の姿でもある。
豆腐屋の職人である塚次は冴えない男だが、気がやさしくて真面目な働き者である。作る豆腐にちょっとした工夫を加えるという熱心な職人でもある塚次が、家付きの一人娘と結婚することになる。ところが、その三日目に娘は出奔し、男とどこかに消えてしまう。取り残された塚次は、病んだ義父とおろおろするだけの義母を抱えて、ただ豆腐を作り、売っていくだけの日々を送ることになる。
しかし、ある日、勝手に家を出て行ったはずの娘が、勝手に家に帰って来て、やくざな男と二人で塚次を追い出しにかかる。
そのとき、塚次は……。
ここには、耐えに耐えた男が最後に爆発する姿を見るという快感がある。それはかつての東映のやくざ映画で繰り返されたパターンでもある。
だが、豆腐屋の塚次は、高倉健や鶴田浩二が演じるような男たちとは違って、憎い敵を討って華々しく散るというわけにはいかない。豆腐屋を守らなければならないというだけでなく、討つべき相手にさえ「あいつだって可哀そうなやつなんだ」と思ってしまうようなやさしさを持っている男であるからだ。
しかし、こういう男の良さをわからない女がいる。だからこそ、物語が生まれるというわけなのだが。
この作中に、客のおかみさんが塚次に向かって「賽の目にして一丁」というシーンが出てくる。私も子供の頃、近くの豆腐屋におつかいに出され、「さいの目に切って下さい」と頼んだ記憶がある。それは味噌汁に使うということを意味していたのだろうが、いま考えれば、自分の家で切ってもよかったのではないかと思う。ただ、あの豆腐屋に独特の薄く平たい包丁で、親父さんが水槽の中に浮いている豆腐を手のひらに乗せ、スッスッと切っていくのを見るのは楽しいことだった。
その包丁を、江戸時代の塚次も使っていたかどうかはわからないのだけれど。