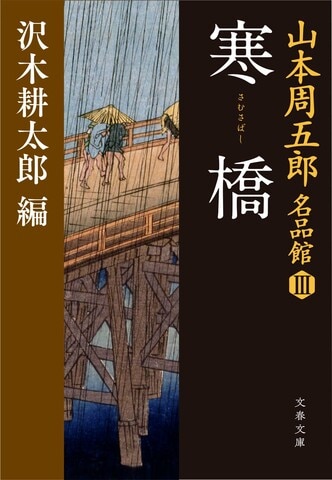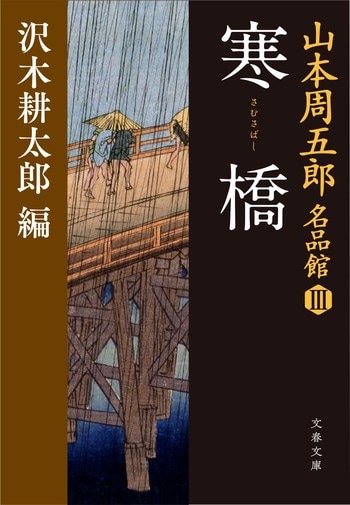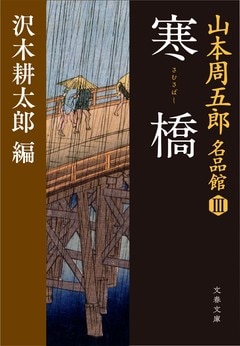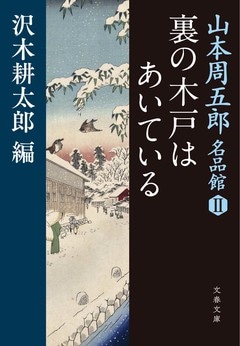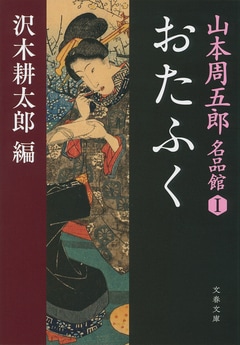父にとっては、その小田原町がことのほか愛着深い土地だったらしく、通信機器の会社を興してちょっとした成金になった祖父が山の手に引っ越しても、本籍地をそこから動かそうとしなかった。だから、必然的に私の本籍地も小田原町だった。いや、いまは町名変更で築地に抱摂されてしまったが、私の本籍地が旧小田原町であるのは変わりないのだ。
調べて見ると、父が「小さな島のような」と表現しているように小田原町はとても狭いエリアである。
もし山本周五郎の「寒橋」の主人公であるお孝が実在の人物で、その子孫が明治、大正時代にも生きていたとしたら、父と一緒に隅田川で川遊びをしていたかもしれないし、少なくとも旧築地小学校には一緒に通っていたにちがいない。
そして私はといえば、山本周五郎の「寒橋」を読みながら、不思議なトリップ感を味わってもいた。
冒頭、主人公のお孝が鏡の前で自分の体をうっとりと眺めているという情景が描かれる。その部屋が、父の母が鏡台に向かって髪を結ってもらっている部屋と重なり、いつの間にか幼い父が小田原町のような町を歩きまわっている姿が見えてきて、やがて私自身が寒橋のような橋を渡っていく……。
私が父の俳句に心を動かされるのは、たぶん私の、父を深いところで敬愛しているという「情」のなせるわざだろう。そして、父が幼いときに失った母の「冷たさ」を憶うのも、父の、その母への思慕という名の「情」からだろう。
そう言えば、「寒橋」もまた、「情」の世界を描いたものであった。お孝の、亭主の時三への恋着に近い「情」と、父親の伊兵衛の、娘のお孝に対する憐憫に近い「情」の交錯がストーリーの骨格をなしているのだ。
しかし、山本周五郎は自分の作品を「人情物」と簡単に片付けられることを嫌ったという。
この「山本周五郎名品館」の第二巻に収録した「こんち午の日」の舞台化に際して寄せた文章では、うんざりした調子でこう記している。
《こんど劇化される「こんち午の日」が雑誌に掲載されたとき、或る女流評論家が──こんな現代ばなれのした話は興ざめであり信じ難い、というふうに仰せられた。なにを隠そうこの話の骨子は私の住居のすぐ近くで、昭和三十年以来、現になお進行している出来事なのであり、登場人物のうち豆腐屋の若夫婦や出ていった家付き娘などは健在しているのである。もともと、私の小説は一部の批評家から「古風な義理人情」というレッテルをよく貼られたものだ。(中略)こういう諸賢が「古風な義理人情」と一蹴する生活倫理や隣人関係は、いまなおそのまま生きているし、それらによって貧しい庶民たちの生活が支えられているのである》(「小説と事実」)
その苛立ちはよくわかるが、「古風な」という形容詞を取り去り、「義理」という言葉を取り去った「人情」は、山本周五郎の短編世界の背骨のようなものになっていることは間違いない。
そして、その人情からさらに「人」を取り去り、ただの「情」になったとき、それは山本周五郎の世界を、日の光のようにあまねく照らすものになっている。
かつて開高健は、山本周五郎の描く女は結局ひとりである、と書いたことがあった。作家がひとりの女のイメージを追い求めているというのは文芸批評の常套(じょうとう)的な手口であり、開高健にしては月並みすぎる評言のように思える。実際は、山本周五郎は多種多様な女を描き分け、結果として多種多様な「情」の様態を書き残すことになった。
女の、男への情。妻の、夫への情。少女の、少年への情。母の、子への情。岡場所の女の、客への情……。
だが、「意地」が男の専有物ではなかったように、「情」も女だけのものではない。