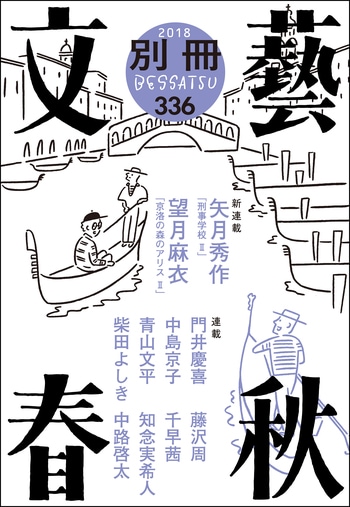「年齢にもよるんじゃないですか。僕も一番最初の記憶は四歳くらいになってからだから」
雄之助くんは小さなグラスに入ったグラッパをちびちび飲んでいた。アルコールがあまり強くないわたしは、古本屋夫妻の芋焼酎ですでにふだんの酒量を超えていたから、バージン・ブラッディ・マリーをストローですすった。
いつだったか、喜和子さんにその話を聞いたことがあったように思い、自分の脳裏にしまい込んである思い出を取り出そうと試みた。それは確か、喜和子さんの家でおいしい冷や汁をごちそうになった夏の日で、あのとき彼女は子どものときのことを話してくれたのだったが、少しためらうような、不安そうな身振りで、こんなふうに言ったのだった。
「ねえ、あんた、自分のちっさいときのことって、どれだけ覚えてる?」
あれは、自分は思い出せないのだ、という意味だったのだろうか。続けて、覚えている限りの話をしてくれたものの、どこか自信なげで、違うかもしれないとかよく思い出せないとか、言い訳めいたものがくっついていた。
しかし、バラックでいっしょに暮らしていたお兄さんの話は、もちろん図書館の話と同じように、はっきりした記憶のようだったし、確かにあのときわたしには、はぐれた両親と再会して宮崎に帰ったと話してくれたのだった。
「だけど、親兄弟の記憶がないということはないんじゃないですかね。だって、何年、そのバラックで暮らしたのかはわからないけど、宮崎の両親と連絡が取れて引き取られたわけでしょう」
それを聞くと古尾野先生は、うん、と言ってごくりと水割りを喉に流し込み、
「それは、僕もあのとき聞いた。喜和ちゃんとあなたと三人であそこの家であの人自慢の郷土料理を食わせてもらったときだろう。覚えてるよ。それで僕は少しびっくりしたんだ。前に聞かされてたのと違ったからさ。まるで一時的に両親と離れて暮らしてたみたいな話になってて、気にはなったんだが、訂正するような件でもないしさ」
「両親といっしょに東京に来て、迷子になったって話は」
「うん、だからさ。そこだよね、僕が聞いてたのと大きく違うのは。覚えていない、バラックで暮らしていたより前のことは思い出せないと言ってたからさ」
「宮崎の両親は、小さい頃のことを話して聞かせなかったんですかね。わたしなんか、自分の幼少時の記憶の大部分は、親とか兄の思い出話を自分の記憶にしてるようなところがあるけど」
「宮崎のお父さんというのは、実は伯父さんなんだと聞いたこともあるんだよ」