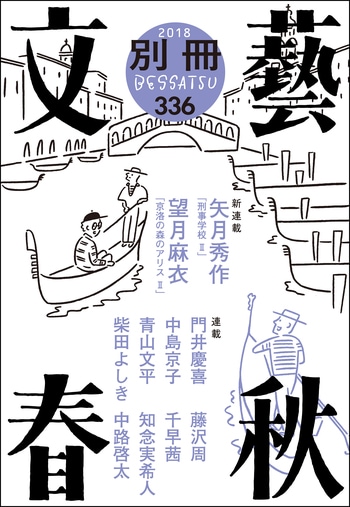ここに喜和子さんと来たことはあるのだろうかと、わたしは一瞬想像した。
古尾野先生が喜和子さんとつきあっていたころは、先生が借りていた無縁坂の部屋で会っていたのだから、もし来たとすれば二人が別れたあとのことになるのだろうか。喜和子さんの小さな谷中の部屋には、人が二人泊れるだけの広さはなかった。あの日、谷中の夕やけだんだんで再会した後、やけぼっくいに火がついたりしただろうか。わたしは、自分から見ると相当に年の行った二人になにかあろうとは思わずに過ごしていたけれど、まったくなかったわけでもないのかもしれない。
そんなことを思ったのは、喜和子さんの娘に会ったり、元女将のフユミさんの話を聞いたりしたからで、最初の結婚があまり幸福なものでなかったとするならば、古尾野先生との、フユミさん言うところの「ロマンス」は、喜和子さんにとってそんなに小さな存在ではなかったに違いないという感慨が湧いたのだった。
わたしが喜和子さんと会ったばかりのころ、彼女は、官軍の大砲の弾がこの不忍池を超えて寛永寺に届いた、その大砲はアームストロング砲といって、アメリカの南北戦争で使われた中古品だったんだなんて話をよくしてくれたものだった。喜和子さんのエピソードのうちの何割かは、この話好きの学者先生が教えたものだったりしたのかもしれない。とはいえ、無縁坂とは、なんという響きの場所に恋人を住まわせていたものか。
夜の不忍池がビルの灯りを映して揺れているのをぼんやり眺めながら、そんなことを考えていると、すっかりおじいさんになった古尾野先生が、ウィスキーの水割りで唇を湿らせて、ぽつりとつぶやいた。
「喜和ちゃんはね、子どものころの記憶が、あるときまですっぽり、ないんだそうだよ」
「すっぽり?」
「うん。かろうじて思い出せるのが、血縁者ではない二人の男とバラックで暮らしてたころのことなんだそうだ。まあ、ねえ、すっぽりと言ったって、ふつう、赤ん坊のころの記憶なんてものは、誰にだってないだろう。だから、それほど特殊なことではないんじゃないかと思うけども、親兄弟の記憶がないわけだから、本人は辛かっただろうな」
「戦災で?」
「うん、まあ、そういうことになるんだろうが、その戦災という記憶自体もないというんだな」
「焼け出されたとか、親とどこではぐれたとかいったことを覚えていないと」
「うん。親戚だか知人だかの家に預けられていたこともあるようなんだが、思い出せないと言ってた。そういうことがあるものかね」