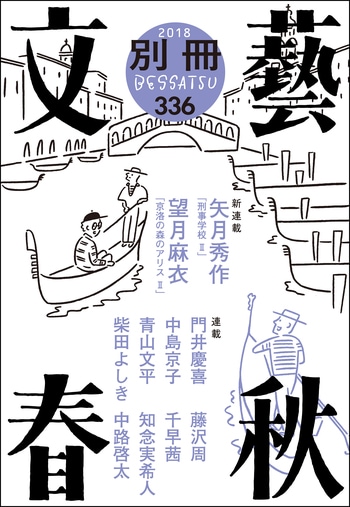「伯父さん?」
「引き取ったということなんだろうね、身寄りがなかったから。まあ、あの時代、そういうことはよくあることだったからね」
「じゃ、どうしてあのとき」
「わからんが、もしかしたら、僕が聞いた話のほうが現実ではなかったのか。いまとなっちゃそれもわからない。ただ、まあ、どうなんだろうね」
わからないことを三人で話していてもしかたがないし、ちょうどよい潮時だと思って、わたしはバッグから「としょかんのこじ」のコピーを取り出して、二人に見せた。バーの暗い照明の下で、老眼の古尾野先生がいかにも読みづらそうだったのを見かねて、雄之助くんが紙を取り上げて読んでくれた。
「ふろへも はいりたいから あくびをして おもてへ でます。」
という最後の一文を聞くと、老名誉教授はちょっと笑った。
「なんだか知らないけど、たくまざるユーモアがあるね。いや、たくまざるではなくて、たくむのか。あまり上手いような気はしないが、そこはかとなく笑える」
「これを書いたのが、幼い喜和子さんといっしょにいた男なのかな」
ひとしきり「としょかんのこじ」を論評したのち、わたしはバッグからまた別のものを取り出した。
「今日ね、わたし、これを五十森さんにもらったんですよ。喜和子さんから預かってたって言って」
「喜和ちゃんから?」
「まだよく見てないんだけど」
「私信を僕らみんなで見ていいの?」
「いや、私信というような感じではなく」
とはいえ、もしも喜和子さんが五十森さんへの恋心を赤裸々につづった手記かなにかを遺していたらたいへんなことになると唐突に思いつき、わたしもいきなり二人に見せていいのか自制が働いたので、とりあえず隠すようにして封筒を開いてみた。そこには、横に罫線の入ったルーズリーフが入っていて、とてもとても小さい字で、びっしりとなにかが記されてあった。それは喜和子さんの字であると思われたが、鉛筆の字の薄さとあいまって、なにしろバーラウンジの照明では読みづらく、それをそこで読むのは断念して、封筒の中に入っていたもう一つのものを引っ張り出した。
古い葉書だった。
あて先は、
「いとうきわこさま」
と、平仮名で書いてあって、差出人は、
「瓜生平吉」
と、あった。
「これ、なんだろう」