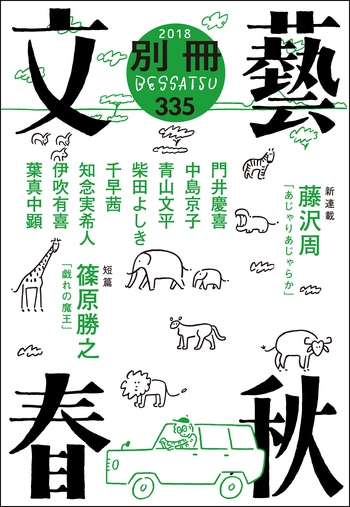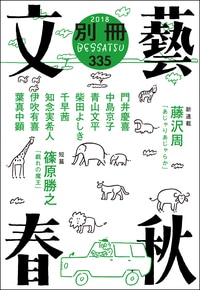
前回までのあらすじ
雑誌記者だった「わたし」が喜和子さんと知り合ったのは十五年ほど前のことだった。彼女は上野図書館に並々ならぬ愛着を抱いていて、図書館そのものを主人公にした小説を書いてよ、と「わたし」に持ちかけてきた……。こうして「わたし」と喜和子さんの友情は始まった。一時疎遠になるが、久しぶりに会ったとき、喜和子さんは老人ホームに入っていた。友情は復活したものの、喜和子さんは肺炎で入院し、そのまま亡くなってしまった。「わたし」は偶然喜和子さん行きつけの古本屋の店主と知り合い、「喜和ちゃんを偲ぶ会」を開くことになった。
その日、集まったのは、妙なメンバーだった。
古本屋の店主とその妻、わたし、古尾野先生、ホームレス彼氏。谷永雄之助くんは少し遅れてくるということだった。店主の妻は厨房を担当していて、わたしはテーブルセッティングや給仕を手伝ったりした。会場は古本屋の建物の屋上であり、古本屋は十坪ほどの建坪の、その三階建てのビルを所有し、かつそこに居住しているのだった。
御徒町に近いそのビルは、たいして眺めもいいとはいえないし、おそらく空気もあまりよくなかったが、専有されたビルの屋上という空間がなんだか心地よくもあり、しばしば人を招いて宴会をしているという古本屋の店主とその妻の仕切りは堂に入ったもので、前日から水で割っておいた芋焼酎とか、少し茹ですぎの枝豆などが、やけにおいしく感じられたりしたのだった。近所にあるお菓子の卸問屋で賞味期限切れをもらってきたという乾きものや、「残り物」の煮物やカレー、炒めたソーセージ、フライドポテト、焼きそばという、色合いの地味なメニューではあったがボリュームがあり、これを会費五百円で提供してくれるのは古本屋夫妻の好意でもあったろう。わたしは喜和子さんの供養と思って、根津のたいやきを持参した。
「偲ぶ会」とかいっておきながら、誰かが司会に立つわけでも、スピーチがあるわけでもないらしく、ただ人が集まって飲んでいるだけなのだが、それはそれで喜和子さんを追悼するにはふさわしい場所でもあった。大袈裟なことは、きっと喜和子さん自身が嫌がっただろうから。
最初のうちは、ホームレス彼氏(このあだ名はやはり少し失礼なので、名前を知ってからは五十森さんと呼ぶべきだろう。イソモリさんと読むらしい)は古本屋の脇に、古尾野先生はわたしの隣にぴたりと張りついて、けっしてお互いに会話しようとはしなかった。