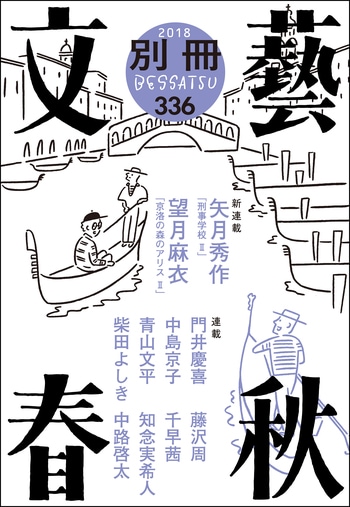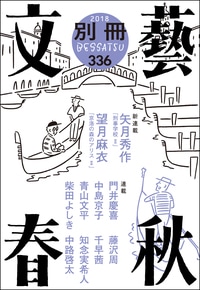
前回までのあらすじ
雑誌記者だった「わたし」が喜和子さんと知り合ったのは十五年ほど前のことだった。彼女は上野図書館に並々ならぬ愛着を抱いていて、図書館そのものを主人公にした小説を書いてよ、と「わたし」に持ちかけてきた……。こうして「わたし」と喜和子さんの友情は始まった。一時疎遠になるが、久しぶりに会ったとき、喜和子さんは老人ホームに入っていた。友情は復活したものの、喜和子さんは肺炎で入院し、そのまま亡くなってしまった。喜和子さん行きつけの古本屋の店主の声掛けで、「喜和ちゃんを偲ぶ会」が開かれたが、そこで「わたし」は喜和子さんの意外な一面を知ることになる。
古本屋夫妻の家を出たのは十時を過ぎた頃だった。
元女将のフユミさんと、多摩川在住の五十森さんは、それぞれさっさと帰ったが、飲み足りない古尾野先生がわたしと雄之助くんを誘って、三人で先生がその晩泊ることにしているという池之端のホテルのバーに行った。
上野界隈というのは、それなりに時代に対応して新しいものだっていろいろできているし、いつもたいそう賑わっているのに、どこかで時間を止めてしまったような風情が漂うのはどうしてなのだろう。化粧煉瓦に電飾をつけ、ホテルの名前が刻まれた丸みのあるファサードが、なにやら古いアメリカのサスペンス映画に出てくるロッジやモーテルのような雰囲気で、わたしと雄之助くんは一瞬入るのを躊躇したのだったが、慣れた宿なのか古尾野先生は怯むことなく突き進み、いいから、こっちだからと年季の入ったエレベーターにわたしたちを誘った。
「これで、露天風呂のついた部屋なんかあるんだ。眺めがよくてさ。都心にしては、リーズナブルなんだよ」
リーズナブルというカタカナ英語が、エレベーターの中でどことなくユーモラスに響いたことなどは一顧だにせず、ほうれ、ここだよ、一杯くらいつきあいなさいよと、老名誉教授が手招きした空間は意外に奥行きのあるバーラウンジだった。時間帯によっては演奏もあるのだろう、グランドピアノなども置いてあり、なにより、不忍池と都心の夜景を切り取る壁一面のガラス窓が、階下のごたごたとは隔絶した眺望を作っていて、雄之助くんはほぉ、とため息を漏らした。
「悪くないだろう」
合皮張りのゆったりしたソファに腰を落として、古尾野先生は満足げに呟き、わたしと雄之助くんは口々に、階下で想像したよりもゴージャスだという意味の讃辞を返した。