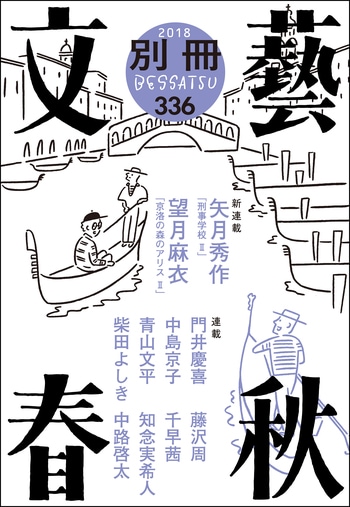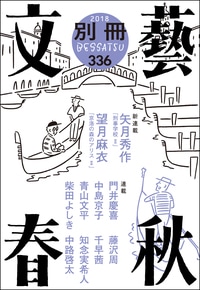
前回までのあらすじ
「私」が父の友人だった全さんに再会したのは、父が亡くなった二十歳の夏だった。全さんは左腕を血で染めて玄関先に立っていた。その後全さんの実家である廣瀬写真館の前で、「私」は全さんを追いかけてきた恋人に出会う。彼女を見た「私」は自分と父を捨て、男と逃げた母親のことを思い出していた。全さんと鶴岡にいる母親のもとへ行ったが、「私」の居場所がないことを改めて理解するだけだった。旅から帰ると、全さんと連絡が取れなくなり、「私」は不安を募らせる。そんなある日、街中で全さんを見かけ、見失うまいと車道を横切ろうとしたとき、車と接触事故を起こした「私」は、全さんに付き添われ、病院に運ばれてしまう。
私はあの夜まで、人の体温を知らなかった。
父の手の温もりや背中の匂いは知っていた。あたたかく、安心できるものだった。友人たちのちょっとひやりとした柔らかい腕は、私をこそばゆい気持ちにさせた。どれも優しい風のように私を撫でていった。
同じ大学の多田との滑稽な初体験未遂は、バタバタした印象しかなく、肌の温度など覚えてはいなかった。
だから、驚いたのだ。
畳にごろりと寝そべっていた全さんが、私の足首を掴んだ時の、その手の熱さに。
けれど、声はあげなかった。触れられる前から、どこかで全さんの温度を感じていたような気がした。
いつからだろう。診察を終え病院から出て、ぬるい夜気に包まれた時か。深夜までやっている中華料理店のカウンターでビールを頼もうとして怒られた時か。それとも、タクシーを降りた全さんがうちの門扉を当たり前のように押しあけ、軋んだ音を耳にした時からか。私が台所へ行っている間に父の仏壇の扉が閉められていたのは気付いた。鶏の唐揚げを頬張り、炒飯をかき込む私を見つめる全さんの目はいつもと同じようで、いつもとは違う温度を宿していたのだろうか。もしそうだとしたら、私の体は無意識にそれを受け取っていたのかもしれない。
中華料理店の白々とした照明の下で全さんと目が合った。口に放り込んだ蒸したての焼売が熱くて、ごくりと呑み込んだ。熱い挽肉の塊は喉から食道へとゆっくり落ちていった。その感触を思いだす。台風がきているらしいぞ。店の奥のテレビに目をやりながら全さんが言った。醤油差しの口で茶色い液体が結晶化していた。
あの時に呑み込んだ焼売が、胃の底でまだ熱を放っている気がする。腹の下の辺りがやけにもったりして重い。掴まれた足首も熱い。全さんの体の熱を感じて、かくんと腰が落ちた。
ああ、体温って流れ込んでくるものだったんだ。
ぐい、と脚を引き寄せられ、皮を剥ぐようにジーンズを脱がされる。