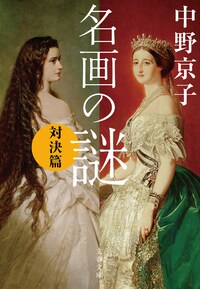
二〇一七年、兵庫県立美術館と上野の森美術館で「怖い絵」展が開催されました。両館合わせて七〇万人近い人々が訪れたこの「怖い絵」展、本書をお読みの皆さんには今さらでしょうが、中野京子さんのベストセラー『怖い絵』を出発点にした展覧会です。同書や『名画の謎』シリーズなど中野さんのファンの来場を当て込んではいたものの、ここまでの成功は予想できませんでした。無粋な話ながら、海外から作品を集める展覧会は存外お金が掛かるもので、正直黒字にならないことが多いのですが、そちらでも結構な成果が出たので、主催者一同大いに喜ぶところとなりました。
ここでこのようなお話をするのは、私が関係者の一人だから自慢したかった、というわけではもちろんありません。中野さんの世界を不完全ながらも展覧会という形式に移植しようという今回の試みが、現在の日本の美術館業界に一定のインパクトを与える出来事だったからです。そのことをお伝えするために、展覧会の裏話を少しばかりご紹介しましょう。
企画展というのは一朝一夕に実現するものではなく、長い準備期間が必要です。基本となるコンセプトから実際の展示に関する諸々の仕様まであらゆることを決める過程では、様々な試行錯誤や葛藤も生まれます。五年ほど前、中野さんとの最初の打ち合わせでお伝えしたのは、ご著書で取り上げられた名作はおいそれとは貸してもらえないので新たに出品作を選び直す必要があること。そして、作品を選ぶにあたっては、歴史的背景やシチュエーションから「怖い」解釈が生まれるようなものは少なくして、視覚的に直接「怖さ」が伝わるものをなるべく多くしたいということでした。
こうした提案、特にふたつ目のそれは、中野さんからすれば少々心外だったかもしれません。というのも、中野さんの『怖い絵』の本領は、直接的な描写の怖さよりは、一見怖くない作品の背後に横たわるコンテクストを丹念に読み解くことで浮かび上がる、ある種デリケートで間接的な怖さのほうにこそあるからです。なのに、そのような話をあえてしたのは、展覧会場に文字情報を提示することの難しさを危惧したためです。プライベートな空間で自由に時間を使っておこなうことができる読書とは違い、不特定多数が公共の場所に集まる展覧会では、個々の作品の背景を丁寧に読み込んでもらう余裕はないだろうと考えたわけです。
最近の展覧会では、作品の横に解説パネルがつくことが常識ですが、その扱いはあくまで添え物の域を出ません。鑑賞に極力影響を与えないよう、良く言えばニュートラル、悪く言えば無味乾燥な文章になってしまいがちです。これは、もしかしたら我々美術館人が本来的に有する先入観、美術館とは複製でなく本物の絵画や彫刻を見るための場所であり、夾雑物(きようざつぶつ)たる文字情報はなるべく排除した状態で作品そのものとの対話を楽しむべきという、ある種の実物至上主義に由来するのかもしれません。対して、中野さんのスタイルは遥かに自由です。広範な知識を語りつつも、選ばれる言葉は直感的でさえあり、今まさに作品を目にした感動に寄り添ってくれるかのようです。
結局のところ、言葉を駆使して絵を「読む」ことの醍醐味を伝える中野さんの意図を汲むべき企画のはずが、私のほうでは絵は「見る」ものだという旧態依然とした考えに囚われていたのかもしれません。今思えば、臆病なうえに頭の固い学芸員の話をよくぞ辛抱強く聞いてくださったものです。話し合いを重ねるうちに、見るからに怖い絵でもなく、コンテクストを深読みすることで初めて怖さが生まれる絵でもなく、歴史や神話の分野で怖い事件や物語をテーマにした絵を展覧会の中心に据えるという方向性が定まってきました。そういった作品もまた中野さんの得意分野ですし、怖さのエッセンスを比較的短めの文章でも伝えることが容易だからです。
さて、この展覧会では、最終的に百点を超える作品を国内外からかき集めましたが、すべてに中野さんの解説をつけるのは難しいため代表的な出品作に絞って大きめのパネルを掲出(各四百字)、それ以外の作品については学芸員が分担して小さなパネルに百字あまりのミニ解説をつけることにしました(全部の作品について中野さんの文章を読みたかった皆さんごめんなさい)。書籍としての『怖い絵』と比べたら遥かに小規模とはいえ、会場全体で原稿用紙五十枚分近くの量の文章を読んでいただくことになります。来場者に強いる負担の大きさをしつこく心配しましたが、幸いなことに杞憂に終わりました。開催中に寄せられたアンケートでは、パネルの小ささに関する苦情はさておき、内容や文字の多さについての文句はほとんどなく、短いとはいえ解説がたくさん読めてよかったという声が多数を占めました。
さらに好評を博したのが音声ガイドです。これは、先述のパネル解説とは別に会場二十か所で中野さん書き下ろしの解説をイヤホンで聴くシステムで、入場料とは別途料金が発生するにもかかわらず、兵庫会場で約三割、東京会場では実に半数近くの来場者が利用、内容の面白さ分かり易さがアンケートやネット上で絶賛されました。吉田羊さんの語りの巧さもさることながら、中野さんの言葉がいかに流麗かつ訴求力があり、鑑賞体験を豊かにしてくれたかの証でしょう。普通の展覧会であればせいぜい総入場者の一、二割程度しか使わないこの音声ガイド、私個人としてはあくまで展示のおまけ程度の認識しかありませんでしたが、本展に限っては展覧会の本質を構成する核心的要素として機能したといえそうです。
もうひとつ、頭が固いということでは、六つの章を展示室に設けたこともそうかもしれません。本来、中野さんの本に章立ては存在しません。美術史を縦横無尽に駆け巡りながら様々な「怖い」絵を拾い集め、切れ味鋭い言葉で鮮やかに捌いてみせるのが最大の魅力なのに、章を設けるということは、バラエティ豊かな作品を無理やり窮屈な枠組みにはめ込むことになりかねません。それでも、本より遥かに多くの作品を扱う展覧会でひたすら絵を羅列するのも不親切に思われたので、「神話」、「怪物」、「現実」、「歴史」……といったそれらしい章を置きました。いってみれば通常の展覧会の体裁に合わせたわけですが、本当に必要だったかどうか悩ましいところです。
また、これらの章立てを巡っては、いくつかの作品をどの章に入れるかで中野さんと意見が一致しないこともありました。例えば、フランス象徴主義の画家ギュスターヴ=アドルフ・モッサの《飽食のセイレーン》と《彼女》という二枚の絵(ご存じない方、ネットでご検索ください)の場合。当初私は同じ画家の作品なので「怪物」の章に並べて展示したいと考えていたのですが、中野さんは、「怪物」の章に置くのは後者のみとし、前者は「神話」の章でイギリスの画家ハーバート・ジェイムズ・ドレイパーの《オデュッセウスとセイレーン》の隣に置くべし、と主張されました。
その時は渋々中野さんの意見に従いましたが、結果的にそれが正解だったのです。というのも、実際に展示してみると、一人の画家が複数の主題を似た様式で描く様子を穏当に示すより、別々の画家が同一の主題にまったく違う様式で取り組む「対決」を見せるほうが遥かにスリリングに主題の「怖さ」を伝えることができたからです。無理に我を通さなくて良かったと後で安堵したことを告白しておきましょう。
異質な作品同士を独自の視点で「対決」させる鮮やかな手腕は、本書でも遺憾なく発揮されています。まず冒頭の、クリムトとカラヴァッジョの対決からして意表を突きます。世紀末美術の代表を差し置いて、バロックの巨匠が如何に淫靡な世界を隠微に表現したかが語られているのですから。あるいは、テニールスとアルマ=タデマの対決(12章)では、伝統的な魔女像と古代ローマの貴婦人に擬態したイメージを並べる発想の面白さが際立っています。最終章のホッパーとモンドリアンの対決も、具象と抽象の両極をあえてぶつける力業(ちからわざ)が痛快です。
こうして見ると、ヌードをめぐるティツィアーノvs.マネのような、直接的な影響関係が明白な“正統的”対決はほとんどなく、中野さん独自のアンテナに引っ掛かった共通項をもつ二作品が対決させられるパターンが多いようです。それらは一見突飛な組み合わせに見えながら、実はそれぞれの画家の意図や時には時代精神の違いまでもが巧妙に対比されている点で読み物としての奥行きを備えていることは見過ごせません。中野さん、「怖い絵」展の第二弾がもし実現するなら、この「対決」の趣向を大々的にフィーチャーしてはいかがでしょう?


















