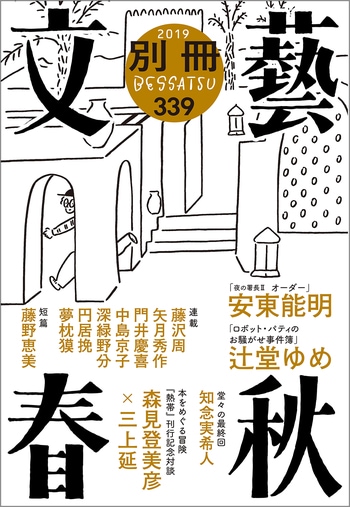朝香は「かしこまりました」と営業スマイルを作った。それから、会議室の後方で待機している内藤怜央を見やる。ぴしっとしたスーツ姿の辻原や朝香と違って、エンジニアの怜央はベージュのチノパンにスウェット生地の青いジャケットという格好をしていた。もう一台のパティを膝の上に抱え、手元のノートパソコンを凝視している。さらさらとした長めの黒髪が、その目元にかかっていた。
ここからが今日の正念場だった。このデモを成功させれば、きっと――いや、必ず道は開ける。
「そういや、どうして今日は二台もロボットが用意してあるの?」
例の課長が、痛いところをつく質問を投げかけてきた。朝香はにっこりと微笑み、「それはですね」と答える。
「お客様が、VIPだからですよぉ」
「営業さんだけでなく開発部署の方まで来てくれたのも、うちがVIPだから?」
「はい、もちろんです」
「やっぱりロボットって、技術に詳しい人間がいないと扱いが難しいのかな」
「全然そんなことないですよ。弊社のほうですべてプログラミングしてからお渡ししますから、使い方はとても簡単です」
やや冷や汗をかきながら、パティの背中にある電源ボタンをそっと押す。パティがむくりと顔を上げて『ハァイ、パティです』と起動時の台詞を言うと、三名の客は「おお」とどよめいた。機械を立ち上げただけで喜んでもらえるのは、人型ロボットのいいところだ。
『コンニチハ、パティです。これから、ボクの使い方を説明しますネ』
頬をピンク色に光らせながらパティが喋り始める。
その声を聞いて、怜央がぱっと顔をこわばらせた。一瞬遅れて、手前にいる辻原も眉を寄せる。
朝香は蒼白になりながら、背中の電源ボタンを長押しした。『バイバーイ』とパティが甲高い声を発し、がくりと頭を垂れる。
「ん、どうした? なんか急にぐったりしたぞ」
課長が無精髭をさすりながら首を傾げた。朝香は何事もなかったかのように笑みを浮かべ、「少々お待ちくださいね」とノートパソコンに屈みこんだ。投影用のケーブルを外し、大型モニターに自分のデスクトップが映っていないことを確認してから、内藤怜央へのチャット画面を開いてSOSを出す。