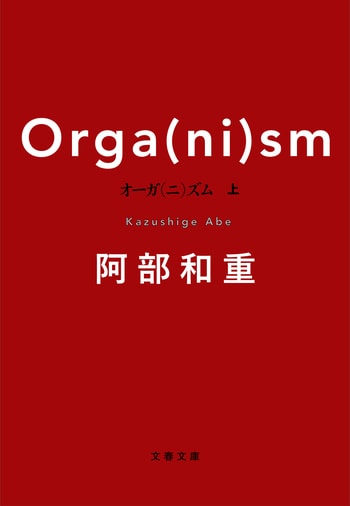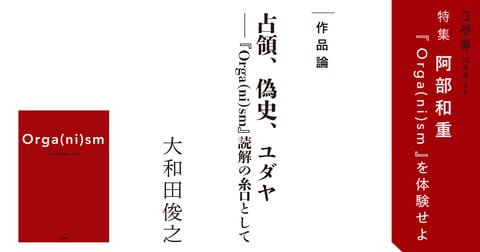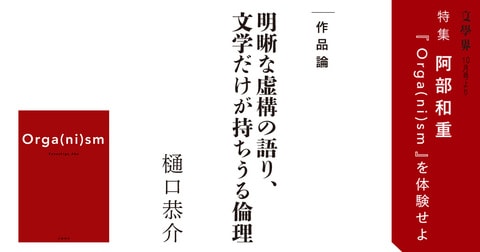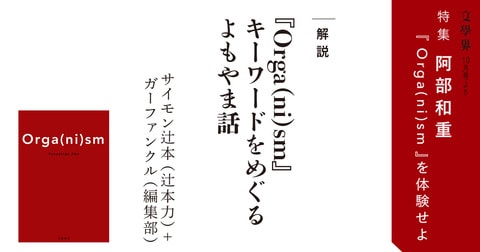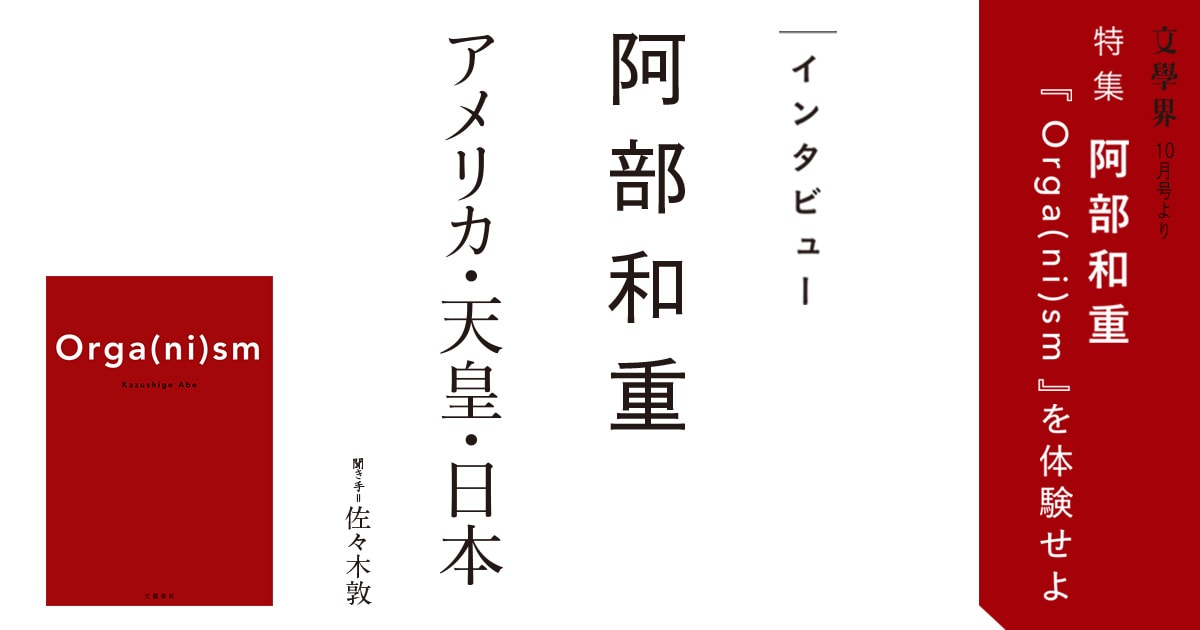
- 2019.09.17
- インタビュー・対談
<阿部和重 ロング・インタビュー> アメリカ・天皇・日本 聞き手=佐々木敦 #2
文學界10月号 特集 阿部和重『Orga(ni)sm』を体験せよ
出典 : #文學界
『シンセミア』連載開始から二十年、『ピストルズ』刊行から九年。
神町(じんまち)トリロジーの完結篇にして、数々の謎が仕掛けられたエンターテインメント巨篇『Orga(ni)sm[オーガ(ニ)ズム]』がついにヴェールを脱ぐ。
二〇一四年、日本の首都となった神町を舞台に展開する、作家「阿部和重」とその息子・映記(えいき)が巻き込まれたCIAと菖蒲(あやめ)家の対立、そして日米関係の行方は――。
私小説/メタフィクション/現代文学がアップデートされる瞬間を目撃せよ!
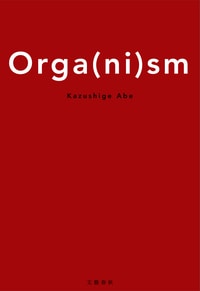
東日本大震災をどう語るか
――どの時点でどこまで設定を考えていたのかを驚くほどくわしくさかのぼることができるのが阿部さんの小説世界の凄いところです。
阿部 とはいっても、現実にいろんなことが起こり、そのつど対応を迫られたことはもちろんあります。その最大の出来事は東日本大震災です。小説の舞台となる東北の出来事でしたし、二〇一一年以降は震災をどう語るかを考えざるをえませんでした。
――『クエーサーと13番目の柱』もそういう作品でしたね。
阿部 はい。二〇一一年以降、いわゆる「震災文学」がたくさん出てきた。現実の出来事や事件をダイレクトに作中に取り入れながら書いてきた小説家として、あの出来事をどう扱えばいいのかは大きな問題でした。
ただ、この三部作に関しては案外早く答えが出たんです。この小説の世界ではあの大震災自体が起きていないとすることで、逆説的に震災を感じ取らせるやり方しかない、と。幸か不幸か、すでに自分が考えていた設定の中にそのヒントがありました。
――それは、『ミステリアスセッティング』で、二〇一一年にすでに爆発が起きていることですか。
阿部 そうです。それで象徴的に見せることはできるだろう。二〇一一年に国会議事堂がなくなったことと、東北の震災が起きたこととは、読者には十分パラレルにとらえてもらえるだろうと。さらにいえば、放射能汚染の問題も『ミステリアスセッティング』に出てくるスーツケース型の小型核爆弾からつなげられる。震災が起きた時は「どうしよう」と思いましたけれども、だからこそ余計に、「これでいけるんだ」と確信が持てました。
――実は過去の作品に伏線があったことがあとから発見されたわけですね。それはすごい。だって、二〇一一年七月にスーツケース型の爆弾が爆発していたことを、二〇〇六年の時点で書いていたわけだから。『シンセミア』にも、渋谷でダンプカーが暴走して人を何人も轢き殺す場面があり、後の秋葉原の通り魔事件を思わせて予言的といわれていたでしょう。つまり、フィクションを小説家が書く時、小説が現実に起きることを先取りしていることがやっぱりあるのですよね。
『エンドゲーム』で泣いた夜
――『シンセミア』よりも今回の『Orga(ni)sm』のほうが分量が多くなったとツイッターに書かれていて驚きました。読んだ時にそこまで長いと感じなかったので。
阿部 『シンセミア』は原稿用紙換算で一五〇〇から一六〇〇枚の間、『Orga(ni)sm』は一七〇〇枚近いです。
――阿部さん史上最長の長篇になったわけですけれども、ものすごくリーダビリティが高い。視点人物が固定されていて、その人物がどんどん事件に巻き込まれていくストーリーのあり方もそうだし、会話がすごく多かったり、地の文もノリツッコミ的で、意図的に同じフレーズを繰り返していたりして、読みやすさを意識して書かれているように感じます。『Orga(ni)sm』を書き始めるに当たっていろいろな文体を検討されたと思うんですが、こういう読みやすいものになったのはどんな理由があったのでしょうか。
阿部 最大の理由は、まさに視点人物が「阿部和重」なので、デビュー作である『アメリカの夜』に戻ろうと思ったことです。
――おお、なるほど。
阿部 『アメリカの夜』を書いていた頃は右も左もわからず、ただ自分の好きなもの、書きながら思いついたことを片っ端から作中に取りいれていました。いま思うと、遊ぶように小説を書いていた。デビュー前でしたし、三度目の新人賞への応募でしたから、もうこれで書くことがなくなってもいいや、ぐらいの開き直った気持ちで、好き勝手に書いていたんですね。十年、二十年と仕事をしていく中で、その自由さみたいなものがどんどん失われていっていると感じていた。
――そういえば、『ピストルズ』執筆時は、ただひたすら「書くのが苦しかった」とおっしゃっていたのが印象に残っています。
阿部 自分で形式をすごく固めながら書いた究極が『ピストルズ』でした。あれは本当に、一字一句において緻密に文章を組み立てたと思っている作品で、自分の中でも特殊な位置にある。自分のクリエーションとしてのある理想的なかたちなんです。でも、あまりにもガチガチに組み立てすぎてしまったことによる弊害もあり、しばらくその書き方の影響下から逃れられなくなってしまった。その次に書いたのが『クエーサー』だったのですが、『ピストルズ』の頭で書いていたせいで、なかなか自然なかたちにならないまま一〇〇枚くらい書き進めてしまった。
――モードを切りかえられなかったんですね。
阿部 それを編集者に見せたらやはりあまり感触がよくなくて、「あ、やっぱりこれは間違いだ」と思い直し、もう一回あたまから書き直した。『クエーサー』はかなりリハビリとしての側面が強いんです。
――『ピストルズ』の影響を一回リセットする必要があったわけですか。
阿部 着ぶくれしちゃっていたのを全部脱がなければいけなかったんですね。大きかったのは、伊坂さんと合作で『キャプテンサンダーボルト』を書いたことです。あれで、久しぶりに小説を楽しんで書くことを思い出せました。伊坂さんの書いたパートを読んで「面白いなあ」と感服しながら、「これに対してどう返せるだろうか」と考える。本当に二人一緒に、ただ純粋にエンターテインメントの物語を考えていくことを通して、初心を取り戻すことができた。あと、伊坂さんの作風に現場で触れることによって、キャラクターの育て方など、すごく勉強になりました。
その後に蓮實重彦さんの『伯爵夫人』の評論を書く機会があったことも大きな経験でした。蓮實さんの小説を読むのは久しぶりでしたが、論じなければいけないから、すごく細かく読む。すると「なるほど。蓮實さん、こういう場面はこう書くんだな」と気づかされる。『伯爵夫人』を読んで自由になれたところがあったんです。
『キャプテンサンダーボルト』での伊坂さんとの共同作業と、『伯爵夫人』を読み解く作業と。自分以外の著者の言葉に深くかかわることで、『ピストルズ』で着込んだ服が一つ一つ脱げていった。そのあとで『Orga(ni)sm』を書こうとした時に、これは阿部和重の言葉で書かなきゃいけないと自然に思えた。実際、視点人物は「阿部和重」なので、一文書くごとに連想として僕の頭に浮かんだことをそのまま小説の文章にするのが正しいあり方となったわけです。
――すると、連載は三年ぐらい続いたと思うんですけど、『Orga(ni)sm』の執筆は、気持ちとしては『ピストルズ』より楽しくできた?
阿部 『ピストルズ』は本当に苦しみしかなかったですからね……。『Orga(ni)sm』を書いている間はものすごく楽しかったです。ずっと笑ったりしながら書いていて、その感じはいままでなかったことでした。しかし、一方で徐々にしんどくなっていったのは、ある時期から「これ、終わるのかな?」という気持ちが湧いてきて。『シンセミア』『ピストルズ』の二作を引き受けながら、最終的に三部作全部で広げた風呂敷をたたまなければいけないので。
――全部回収しなければいけないというプレッシャーが。
阿部 「終わらせるだけだから最後は楽ですよ」みたいに周囲にいってたけど、そんなことないじゃん、とだんだん気づいて焦りました(笑)。
――処理しなければならないチェック項目がいっぱいありますものね。すると全体のボリュームは、もうちょっと短くなる予定だったんですか。
阿部 たぶん『ピストルズ』と同じぐらいかなという予感があったんです。でも、そんなことは全くないと半分ぐらい過ぎたところでわかってきた。MCUとの比較で「こっちはアーベルだ」なんていいましたけれども、ちょうど『Orga(ni)sm』の連載が終わった直後に『アベンジャーズ/エンドゲーム』を観たんですよ。あれもシリーズの完結篇という位置づけですが、夜中に一人で映画館で観たら、泣けてしょうがない(笑)。「制作陣のつらさ、よくわかる……」みたいな気持ちになって。
――最終作ならではのつらさを感じて。
阿部 どの場面を見てもその意図がクリアに伝わってきて、「これを終わらせることの大変さはだれよりもわかってるぞ」って変に共感してしまいました。泣けて泣けて仕方がなかったですね。
――そういうところでもMCUとつながるんですね。
阿部 つながりました。もちろんかかっている予算は比較にもならないですけど、『エンドゲーム』は他人事ではなかったですね。
傷だらけのアメリカ
――『Orga(ni)sm』をゲラで読んだ時、これは間違いなく『キャプテンサンダーボルト』以降の作品だなと思ったんです。とにかくストーリーがどんどん展開していく。今作はCIAのケースオフィサーが「阿部和重」の家に転がり込んでくるところから始まり、神町を舞台とする巨大な陰謀らしきものをめぐって話が展開するわけですけど、スパイ小説などで、具体的なモデルを想定していましたか。
阿部 小説もありますが、一番は海外のドラマですね。スパイスリラーやポリティカルアクションで念頭にあったのは、アメリカの『HOMELAND』です。
――どういう作品ですか。
阿部 女性が主人公のCIAもので、いわゆる現代のスパイスリラーとしてよく出来ている。いまはシーズン7ぐらいまで行ったのかな。次のシーズンで終わりらしいんですけど。
――長く続いているシリーズなんですね。
阿部 このドラマの特徴は、中東の事件やアメリカのテロとの戦いのような近年の国際情勢が、「これはあの事件をもとにしてるな」とすぐに連想できるかたちで組み込まれているんです。その上で印象深い人物模様を描き、ドラマ部分を非常にうまく作り込んである。『24』と同じ制作スタッフなんですが、『24』は二十四時間以内に事件を解決するというドラマ様式を優位にすえた虚構性の濃い作品ですよね。その後に同じスタッフでスパイ劇をどう作るかとなったときに、現実の事件を連想させる、リアリティーを重視した内容という答えになったのではないか。
-
『圧勝の創業経営』
ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
応募締切 2025/07/26 00:00 終了 賞品 『圧勝の創業経営』5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。