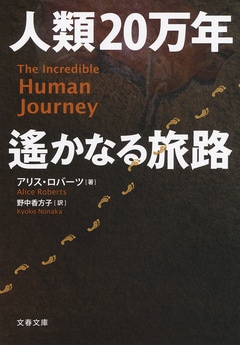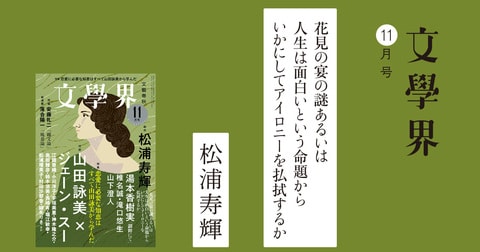帝国に抗うためには、なによりもまず帝国を生み出した「生産と蓄積」の論理そのものを再検討しなければならない。それとともに、「生産と蓄積」の論理によって成り立ち、帝国の基盤となった国家という在り方そのものをも再検討しなければならない。「生産と蓄積」の論理とは異なった、つまりは「国家」の論理とは異なった、もう一つ別の論理、もう一つ別の社会体制の在り方を探らなければならない(マルクス亡き後のエンゲルスが共産主義の可能性を探ろうとした方向でもある)。「未開」や「野蛮」と称された社会は、国家の形成に抗う社会であった。その内実が、このとき、ようやく正確に理解され始めたのだ。国家に抗う社会とは、「生産と蓄積」の論理に抗う、「消費と蕩尽」が貫徹された社会であった。「価値」の置かれ方がまったく異なっていたのである。「未開」の社会、「野蛮」な社会では、社会の規模を拡大していく要因となる「蓄積」が、一年に一度、その多くは時間と空間の境界――季節が移り変わる瞬間にして内と外を区別する場所――で行われる祝祭によって、ほとんど跡形もなくすべてが「蕩尽」されていた。生産に対して消費、蓄積に対して蕩尽という論理が貫かれていた。
岡本太郎もジョルジュ・バタイユも、そのような国家に抗する社会、そうした社会で執り行われる祝祭のなかに新たな芸術表現の可能性を探ろうとしていた。国家に抗する社会は、ヨーロッパの空間的な外に存在するだけでなく、時間的な外にも存在していたはずだ。当時積み重ねられていた考古学的な知見によって、国家に抗する社会とは、国家に帰結する「生産と蓄積」の起源である新石器革命、灌漑という技術を利用した大規模な水田稲作(灌漑水田稲作)を現在まで受け容れなかった人々の共同体であったことが分かってきた。農耕を採用せず狩猟採集という生活手段を守り続けた人々の……。極東の列島たる日本を対象とした考古学の現状においても、縄文と弥生を区別する最大の指標として「灌漑水田稲作」の有無をあげることが現在においても最大公約数的な理解となっている。それを「農耕」一般と置き換えることについては種々の問題を孕むが(安定した狩猟採集社会では「採集」が発展した、初期農耕と称することも可能な「雑穀」栽培は行われている場合が多い)、本稿では対立項をあえて強調するためにそうする――以下、現在の縄文理解のスタンダードとして、山田康弘『縄文時代の歴史』(講談社現代新書、二〇一九年)を参照している(そこに展開された歴史観をもとに国立歴史民俗博物館の「先史・古代」の展示がリニューアルされた)。縄文の「農耕」については小畑弘己『タネをまく縄文人 最新科学が覆す農耕の起源』(吉川弘文館、二〇一六年)が先鋭的な問題提起を行っている。