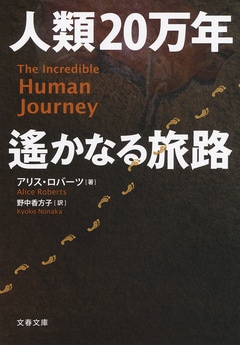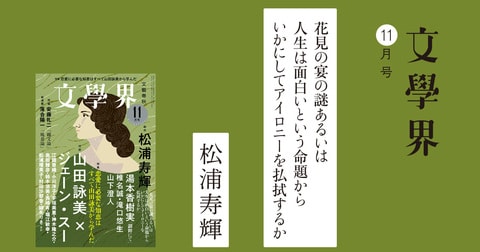二度目の世界大戦がはじまった直後の一九四〇年、数人の少年たちによって、ほとんど偶然の機会にラスコーの洞窟、そこに描かれた無数の壁画が発見された。もちろん前世紀からフランスとスペインの国境地帯に存在する数々の洞窟のなかに古代人たちが残した芸術表現である壁画、動物を主題として描かれた見事な絵画があることは知られており、その研究も進んでいた。しかし、そのなかでもラスコーは量的にも質的にも格段に優れたものだった。絵画表現の起源に位置づけられる作品群が、同時にある種の絵画表現の完成をも指し示していたからである。日常とはかけ離れた非日常の場所、それまでまったく知られていなかった地下の迷宮(前に進むことさえ困難な箇所もあった)、自然が形成した「大聖堂」に残されていたという点においても衝撃的であった――研究者たちはごく自然に、壁画が残されていた巨大な地下の洞窟を、教会建築の術語を用いて説明していた。
しかも、その壁画を残した人々は、磨き上げられた石器(磨製石器)を使っておらず、いまだにただ打ち割られた石器(打製石器)しか使っていなかった。つまり、新石器革命が可能にした農耕以前の社会、狩猟採集社会に位置づけられる人々、旧石器時代の最後(後期旧石器時代)を生きた人々であった。氷河期(現在からみれば「最終氷期」、つまりは最後の氷河期)を生き抜いた狩人たちであった。絵画の起源にして絵画の完成、すなわち芸術の起源にして芸術の完成は、歴史以前にして国家以前に位置づけられるのである。ヨーロッパの空間的な外(「未開」にして「野蛮」な社会)と時間的な外(「氷河期」の狩猟採集社会)はリンクする。芸術の起源にしてその完成は、「生産と蓄積」の論理以前、「消費と蕩尽」の理論が貫徹された狩猟採集社会に位置づけられるのだ。太郎が縄文に向かい、バタイユがラスコーに向かわなければならなかったのは必然であった。
この続きは、「文學界」11月号に全文掲載されています。